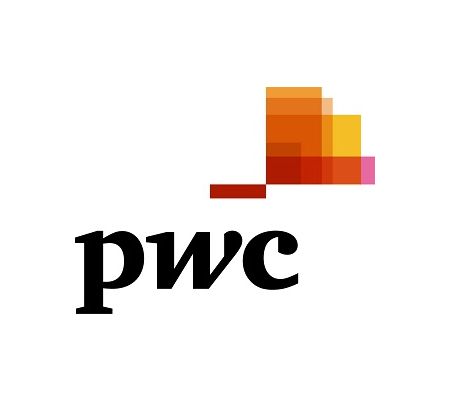プライベート・エクイティによる「価値創造」 「買収先」「投資先」の企業をいかに成長させるか

PEファンドとは
PEファンドの定義について、PwCアドバイザリー合同会社 パートナーでPwC JapanグループのPEセクターの共同リーダーを務める名倉英雄氏は「主に複数の機関投資家から集めた資金で非上場会社の株式、コントロール権を得てその経営に関与し、企業価値を高めてIPO(新規株式公開)や売却で利益を得ることを目的としたファンド」と解説する。ただし、その対象企業、経営への関与の仕方といった細部はそれぞれのファンドで異なるという。

インテグラル
パートナー
国内独立系PEファンドであるインテグラルは、佐山展生氏らが2007年に設立し、現在の4号ファンドは約1,200億円規模を運用する。これまで再成長、事業承継、カーブアウト、事業再生、上場に向けた資本増強などのテーマで資金・経営支援ニーズを受け、さまざまな規模・業種の29社に投資をしている。同社の二井矢聡子氏は「現場と同じ目線、時間軸でバリューアップを図り、世界に通用する『日本型企業改革の実現』を掲げて活動している」と説明する。
インテグラルの特徴の1つは、ファンド資金のほかに、役職者が出資した同社の自己資金を合わせて投じるハイブリッド型投資である点だ。5年程度でファンドがエグジットした後も、同社の自己資金は投資を継続し、より長い目で成長支援を続ける。もう1つの特徴は、企業革新支援チーム「i-Engine」(以下、iエンジン)による投資対象企業の事業成長、管理体制、財務面などのサポートがあること。二井矢氏は「メンバーは現場に常駐して、何でもやる」と強調する。同社では、企業の現場と一体になって日本企業ならではの信頼関係を築きながら企業価値向上を図っているという。
KKRの創業は1976年。ニューヨーク証券取引所に上場し、世界23拠点でPEファンド投資のほか不動産・インフラ、スタートアップ投資なども展開する、運用残高70兆円超の総合資産運用会社だ。その特徴はグローバルの豊富なリソースを生かした投資先支援にある。
KKRには、オペレーション改善などの事業課題の解決から、投資先がM&Aを行う場合のデューデリジェンスやPMI(買収後の企業統合)まで、さまざまな支援を提供する専門チームとして「KKRキャップストーン」、資金調達やエグジット時のIPOなど資本市場関連のアドバイスを専門とする「KKRキャピタル・マーケッツ」、そして、地政学リスクやマクロ動向の調査によって、意思決定を支えるシンクタンク「KKRグローバル・インスティテュート」がある。
KKRジャパンの谷田川英治氏は「日本では2006年に東京オフィスを開設以来、ノンコアの子会社や事業部門を分離する大型カーブアウト案件を数多く手がけ、過去10年で約2兆2,000億円を投じてきた」と豊富な実績に言及した。
日本の事業会社の課題とPEファンド活用の可能性
日本でもコーポレートガバナンス改革は進んでいる。最近では東京証券取引所が提起したPBR1倍割れ問題などもあり、事業ポートフォリオの見直しも含めて、企業価値向上のための適切な経営資源配分が求められている。PwCの調査では、「直近の事業年度でM&Aを検討」、あるいは「実行した」と回答した日系上場企業は約8割に上った。カーブアウトM&Aが日本でも浸透したことで、国内M&Aの案件数は堅調に推移している。
一方、撤退や売却を決断するうえで、対象事業を選定する基準や検討プロセスが明確でないといった課題や、規模縮小に対する経営者の根強い抵抗感も同調査の結果から浮き彫りになった。取締役会で定期的に事業ポートフォリオを議論していない企業は半数以上(55%)に上り、PwCアドバイザリー合同会社 パートナーの森隼人氏は「事業ポートフォリオの見直しが、バリュークリエーションに直結するという意識を持つ必要がある」と指摘する。
さらに、コーポレート機能の分離や社名・商標、取引先などとの契約等、カーブアウトされて独立企業となるために解決すべき課題は山積している。その際、カーブアウト後の事業経営や企業価値創造に高い専門性を持つPEファンドが受け皿となるはずだ。

KKRジャパン
パートナー
大型カーブアウト投資に注力してきた谷田川氏は「本来は競争力が高く優良な事業であっても、グループの中でノンコアと位置づけられたために、その潜在性を開花させられない事業は数多く存在している」と語る。“ノンコア事業”という評価も、「グループ戦略に合わない」という評価であって、「事業内容が優れない」という意味ではない。収益のボラティリティー(変動性)が本業と異なることを理由にノンコアとされることもあるが、そのボラティリティーを受け入れ、事業者自らが描いた戦略を中長期的に支援できるパートナーと組めれば「その事業と人は今まで以上に輝く」と力を込める。
また谷田川氏はKKRには、グローバルネットワークによる海外事業展開への支援に加えて、過去の豊富な実績があることに触れ「役員や社員の適切な処遇や、売却後の事業発展を任せられるという安心感もある」と言う。
日本企業がグローバルに成長するには選択と集中が重要であり、コア事業回帰への市場圧力も強い。にもかかわらず、ノンコア事業の売却が進まない背景には、“身内”を切り離すことへの抵抗感があるという“日本的”な要素や、従業員、サプライチェーン、顧客からの反発が考えられる。二井矢氏は「カーブアウトはハレーションが起きやすく、それが作業的にも心理的にも負担となり、つい後回しにしてきたのではないか」とみる。他の事業会社に譲渡する場合は、競合相手も受け入れへの抵抗感を持つことがあり、同業他社の中で譲渡先を見つけにくいという課題もあるが、その点について二井矢氏は「譲渡先の受け皿を中立的なPEファンドが担うことで、日本でもカーブアウトは進みやすくなるのではないか」との見解を示した。
PEファンドには、旧来のしがらみにとらわれず、成長のための意思決定を合理的かつ迅速にできるという利点がある。日本社会には、まだファンドに対する否定的な先入観も根強くあるが、カーブアウト案件で売却する側は、規模の大きなコングロマリット企業であることが多い。そうした大手企業は、金融的な知識やファンドに対する正確な理解を備えているので先入観にとらわれることもない。「PEファンドとカーブアウトという組み合わせは相性がよいと思う」(二井矢氏)。
インテグラルはその点を踏まえ、日本企業に合った支援、提案をしてきたという。現場に常駐して一緒に改革に汗をかくiエンジンによる支援を提供するほか、株式保有割合についてもバリューアップを最大化する観点から、全株取得以外にも保有割合の希望について柔軟に考えている。
最近のM&Aの背景には、アクティビスト(物言う株主)の活発な活動も影響しているとされる。2014~15年のスチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードの導入以降、日本企業でも社外取締役が増え、ステークホルダーエンゲージメント(関係者の意見を自社のガバナンスや意思決定に反映させるプロセス)も進んでおり、谷田川氏は「日本のガバナンスがさらなる高みのフェーズに入ろうとしている」と捉える。二井矢氏は「経営陣は、アクティビストが来てから、焦って対応を考え始めるのではなく、日頃から事業ポートフォリオのあり方を考えておくべき」と主張した。
PEファンドの企業価値創造アプローチ
買収した企業のバリューアップ支援について、PwCでは持続的成長を支援するフレームワークを用意している。そこでは、投資前の伝統的なデューデリジェンスだけでなく、投資後の①戦略的事業改革(事業ポートフォリオ合理化や経営体制刷新)、②オペレーション改善(クロスセル・アップセルによる売り上げ拡大、コスト改善、独立したコーポレート機能の構築)、③ストラクチャーの最適化(バランスシートや税務の適正化)、④ESG(環境・社会・ガバナンス)をはじめ非財務情報のリスクの改善やオポチュニティの実現――の4点にフォーカスしているといい、森氏は「幅広く価値創造を考えていくべき」と語る。
また、谷田川氏は企業価値創造について、「ゴールの設定、意思決定体制の構築、リソースの確保、モチベーションを保つインセンティブの導入といった、価値創造に入る前のセットアップが大事だ」と指摘する。まずはグループの制約からフリーになった独立事業体として「どんな会社になりたいか」というゴールを定義することが重要だという。その達成に必要な意思決定体制を構築する際、PEファンドが経営権を握って参画する場合は、取締役会と株主総会が実質的に一体になるため、迅速な意思決定が可能になる。改革リソースやノウハウもPEファンドから提供できる。その際、役員・社員向けのインセンティブプログラムを導入することも大事だという。

PwCアドバイザリー合同会社
パートナー
PwC Japanグループ
プライベート・エクイティ セクター
共同リーダー
谷田川氏は「役員・社員のモチベーションを維持・向上させるには、改革や価値創造で得られた成果・リターンを株主のファンドが独占してはいけない。役員・社員がそのリターンをともに享受できる仕組みが必要だ」と強調した。
主に日本企業を投資対象として、日本型の企業改革、価値創造を目指しているインテグラルは、投資先企業の社内のリソースを生かすことを重視しているという。とくに事業のトップについては「外部から経営陣を連れてきても、うまくいかないことが多い」(二井矢氏)ことから、投資前のデューデリジェンスの段階で、トップを任せられる社内人材を見極め、現場に常駐して信頼関係を築く「日本的なバリューアップ」を図っている。
カーブアウト案件では、経営、事業、財務面の改革支援に加えて独立企業として運営していくための「スタンドアローン化の支援」も大事だ。自前のコーポレート機能の整備や、親会社のITシステムからの切り離し、オフィス・製造拠点の分離、グループ企業同士で貸し借り・共有していた資産の整理など、やるべきことは多く、プロの支援が望まれる。独立後の人事制度なども「元親会社が現行の雇用条件を下回らないようにすることはよくあるが、逆に上げすぎることを望まない場合もあり、さまざまな配慮が必要になる」(二井矢氏)という。
ESG視点での企業価値創造
PwCの調査では、M&Aを行うにあたって約半数の日系企業がESGデューデリジェンスの必要性を感じている。グローバルPEファンドの72%は買収投資前の段階でESG関連リスクのスクリーニングを実施し、70%がESGのリスクと機会をバリュークリエーション計画に組み込んでいると回答した。森氏は「一般企業のESGに対する意識はかなり高まっているが、PEファンドはそれ以上に高い意識を持って先進的な取り組みを進めている」と指摘する。

PwCアドバイザリー合同会社
パートナー
PwCアドバイザリー合同会社でも、ESGデューデリジェンス、投資先企業におけるサステナビリティ戦略の立案、CO2削減のために社内で炭素価格を導入するインターナルカーボンプライシングの推進など、業界に先駆けてESG関連の支援メニューを幅広く用意しており、森氏は「ESGは、規制による負担増などのリスクがあるが、顧客ロイヤルティー改善や社員エンゲージメント向上などによる価値創造や成長機会にもつながる」と語る。
KKRは2009年、国連の責任投資原則に署名してESGの先駆けとなる取り組みを進めてきた。コントロール権を持った投資先企業に対しては、事業活動に伴う排出(スコープ1)から、他社から供給されたエネルギー使用に伴う排出(スコープ2)までの温室効果ガス排出量を測定。2人以上の女性やマイノリティーの人たちを取締役会に入れて多様性を確保するなど、ガバナンス面でも先進的な取り組みをしている。
これには「ファンドに資金を提供している年金基金などの意識が高まり、リターンだけでなくESG対応もしなければ資金調達が難しくなる」(谷田川氏)という背景もあるという。
一方で、国内企業を主な投資対象とする二井矢氏は「多くの投資が必要となる中で、ESGを最優先とすることを投資先企業に求めるには難しい面もある」と認める。つまり、ESG投資はトレードオフではなく、バリューアップと両立させるトレードオンで考えることが必要であり、同社も経営理念をESG観点から見直すワークショップを開催するなど検討を進めているという。
二井矢氏は、日本のPEファンド業界全体で女性パートナーが極めて少ない現状についても言及し、「業界にダイバーシティをもたらすため、どうしていくべきか考えている」と語った。