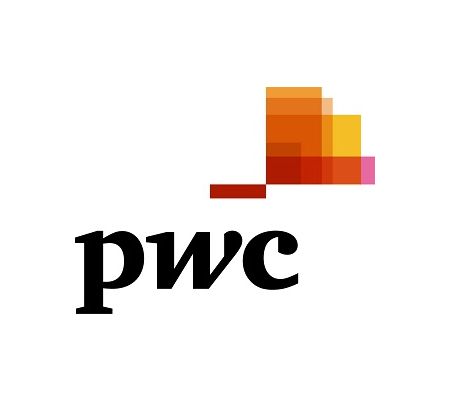日本のあるべき事業再編とグローバル展開とは 求められるガバナンスと、地政学リスクの動向

クロスボーダーM&Aと対日M&Aの関係とは

事業ポートフォリオ再編とM&Aの歴史を振り返ると、内部成長が中心だった日本企業は2000年代以降、積極的にM&Aを展開するようになった。当初は国内企業同士の合併・再編が主流だったが、10年代にはクロスボーダー(海外)M&Aが本格化。10年代後半になると、逆に海外の企業や未公開企業、不動産に対して投資を行うプライベート・エクイティ(PE)ファンドに対して、日本企業が事業を売るという対日M&Aも増えてきた。

早稲田大学 常任理事
商学学術院 教授
早稲田大学高等研究所 顧問
企業統治やM&Aが専門で、経済産業省の対日M&Aをテーマとする研究会の座長を務めた早稲田大学の宮島英昭氏は「国内市場の成熟を踏まえ、海外市場へ進出を図るクロスボーダーM&A(海外企業の買収M&A)を進めるには、国内事業のポートフォリオ再編を並行して進めることが重要になる」と指摘する。なぜなら、対日M&Aを通じて子会社や事業をカーブアウト(切り出して売却)することにより、海外M&Aの原資を得られるからだ。さらに宮島氏は「その意味で、海外M&Aと対日M&Aは相互促進的な関係にあると言える」と説明する。
国内事業再編の背景には、コングロマリットディスカウント(複合企業体の企業価値が、個別事業の価値の合計より低く評価されること)に対する投資家の厳しい視線もある。経済産業省の安藤元太氏は、日本企業は規模拡大や多角化が進むと利益率が米国企業に劣後する傾向があることをデータで示し、ノンコア事業を抱えていることが利益率低下につながっている可能性を指摘する。
そのうえで「複数事業を持つことは経営リスクを分散させるなどのメリットもあるが、コア事業に集中すれば、経営者が専門的知見に基づいて課題に向き合い、迅速な意思決定ができる。両者のバランスが課題」との見解を示した。
事業再編を進めるうえでのガバナンスの課題
大手企業がノンコアの子会社や事業部門を売却する場合は、親会社が意思決定できれば取引がまとまる可能性が高い。こうした大手企業は、機関投資家の株式保有率が高く、社外取締役の導入も進んでいるため「外部の目によるポートフォリオ見直しの圧力が働きやすい」と宮島氏は語る。
ただし、ノンコア事業と判断するための評価基準があいまいだと再編の意思決定が妨げられてしまう可能性がある。そこで経産省は評価基準について、「事業再編実務指針」において事業評価のフレームワークを提案している。まず、資本収益性と成長性の2軸に従って事業をプロットして4象限に分類する。そのうえで、資本収益性は高いが成長性が低下した事業が生み出すキャッシュを新規の成長事業に振り向ける。さらに、収益性・成長性ともに低い事業については売却して、得られた資金も使って新規の成長事業に充てることを検討する。

経済産業省
経済産業政策局 産業組織課長(当時)
安藤氏は「カギは事業評価の仕組みをつくること」と強調する。というのも従業員出身の経営者の場合は、仲間がいる事業から撤退し、売却を決断することに抵抗を感じるからだ。「取締役会がそれぞれの事業について、自社がベストオーナーなのか、もっと事業価値を高められるオーナーが別にいるか、といった視点も含め議論することが大事になる」(安藤氏)。
ベストオーナーとなりうる買い手は、国内事業体のほか、海外の事業体、PEが考えられる。近年対日M&Aを活発に進めているPEは、カーブアウトされた事業・子会社に対して、組織や財務を強化するリソース、ノウハウを提供。これにより事業成長を促し、企業価値を創出することで利益を得ることをビジネスモデルとしている。安藤氏は「国内事業体同士でもさまざまな形のM&Aが行われるようになり、国内企業同士がオープンイノベーションにより価値を生み出すことも期待できる」と語った。
中堅企業が成長機会をつかむために
カーブアウトという形で大企業の事業再編が徐々に進んでいる。一方で、PEなど外部の資本を入れるM&Aについては、専業度が比較的高い中堅企業が成長機会をつかむために有用であるものの、ほとんど手つかずの状態だ。こうした中堅企業は株式が分散していることが多く、株主から買収の同意を取り付けることが難しい。宮島氏によれば、それこそが再編を遅らせる要因であり、「成長機会を捉えられていない企業のM&Aの促進は、日本経済全体から見て重要な課題だ」と指摘した。
海外に進出したいが、ネットワークや人材が不足している中堅企業にとっては、海外PEの投資対象となることで、その海外ネットワークを活用した支援などを受けることができ、目標実現のステップとなりうる。「自社の潜在力を認めたPEから投資の提案を受けた場合、経営陣は予断的に拒否せずに真摯に耳を傾けるべきだ」(宮島氏)
安藤氏もまた、分散した株主構成の企業に対する「望ましい買収」は企業の企業価値向上に資すると期待を寄せる。
カーブアウトとは別に、大企業から子会社・事業部門を分離させて独立企業とするスピンオフについても、多角化した事業ポートフォリオを再編する手段として制度が整備されており、国は障害となっていた税制上のハードルを下げる「スピンオフ税制」を2017年に施行した。2023年度からは、元親会社と一部の資本関係を維持したままにできる「パーシャルスピンオフ」も導入され、スピンオフ税制の使い勝手を高めることが期待される。

PwCアドバイザリー合同会社
パートナー
最後にPwCアドバイザリー合同会社 パートナーの東輝彦氏は「企業価値向上には、コングロマリット企業の一部事業をベストオーナーへカーブアウトすることを含めた事業ポートフォリオの入れ替えが重要である」と指摘した。成熟した国内市場で潜在的な可能性を発揮できていない専業企業はPEなどからの出資を通じて海外に進出し、成長を探ることが必要であり、事業再編・M&Aの活性化に向けたガバナンス見直しや制度変更が進むことで日本企業の活性化が期待される。
政治による経済への介入が強まる時代へ

事業ポートフォリオを見直すうえでは、地政学リスクに対応するサプライチェーンの再構築も重要なテーマとなってくる。実際、冷戦後の世界は国家による市場への介入を避ける新自由主義的な規制緩和や、自由貿易によるグローバリズムが潮流だった。しかし、近年は経済安全保障の視点が重視され、政治が経済に介入する場面が目立つ。
「ウクライナ侵攻に伴うロシアへの経済制裁は、その典型的な動きの1つだ」と話すのは国際政治が専門で経済安全保障などに詳しい東京大学の鈴木一人氏だ。西側諸国が経済制裁によりロシアに侵攻政策の変更を迫る一方で、ロシアは穀物やエネルギーの輸出制限で対抗。中国やインドなどグローバルサウスの国々は、より安価なエネルギーを求めてロシア産石油の輸入を増やしており、その結果、西側の経済制裁は決定的な成果を上げられず、世界は混沌としている。

東京大学公共政策大学院 教授
国際文化会館 地経学研究所長
また、鈴木一人氏は、冷戦後から続いてきた大きな流れは変わったことを強調。「各国の相互依存がなくなることはないが、運動や思想としてのグローバリズムは終わりに近づくのではないか」と語り、政治による経済への介入が強まる「ポストグローバリズムの時代」の到来を予想する。またその流れの中では、「企業のサプライチェーンマネジメントも変化が必要になり、リーンやジャストインタイムといった効率性の追求に専心できた時代は終焉を迎え、ジャストインケース(念のため、何かあった時のため)の考慮が求められるようになる」と指摘した。
変化する世界の中で存在感を増してきたのが中国であり、その経済的台頭は各国の製造業に影響を及ぼしている。米政権は「ラストベルト」(さびたベルト)と呼ばれる衰退した米国中西部の工業地帯の労働者らの不満の高まりに危機感を募らせ、自国産業を守る保護主義的政策に傾斜。中国のさらなる台頭を抑えるために、先端半導体の輸出規制を行ったことで米中対立はエスカレートしてきた。しかし、経済関係は分かちがたく、鈴木一人氏は、「米中デカップリングが現実的ではないという認識がコンセンサスになっていると言える」と語った。
中国頼みのサプライチェーンの変化
サプライチェーンが専門のPwCアドバイザリー合同会社 パートナーの鈴木慎介氏は「中国にサプライチェーンを依存してきた日系企業は、中国国内のビジネス環境の変化という課題にも直面している」と指摘する。
2015年発表の「中国製造2025」以降、中国は特定の産業領域で重点的に産業振興を進め、ハイテク分野などで国産化の方針を打ち出してきた。20年には政府調達分野で国産IT機器リストの本格運用を開始。22年には複合機などの国家標準策定に着手し、オフィス機器の国産化を進める。医療機器でも国産比率を高める方針が示され、さらに他の製品分野、民間調達への拡大が予想される。
さらに、1990 年代から2000年代に設立された日系企業と中国現地企業の合弁事業(JV)の期限が迫っていることもあり、日系企業がJVの持ち分を中国側に売却するケースも増えているという。

PwCアドバイザリー合同会社
パートナー
鈴木慎介氏は「日系企業にとって中国市場は引き続き重要であり、中国を外してサプライチェーンの議論はできない。しかし、産業政策の転換により内製化が進み、人件費が上昇する中国の現状を受け、日系企業の中国国内での生産は成り立ちにくくなっている」と述べ、中国事業を縮小して日本に回帰するリショアリング、第三国に移管するオフショアリングが加速する可能性に言及した。
東京大学の鈴木一人氏も、「中国は以前から西側への依存度を減らそうとしてきたことから、内製化志向は今後も続く」と予想する。さらに中国とのサプライチェーンに影を落とすのが経済安全保障政策だ。
経済安全保障は経済合理性とは別に動く。例えば台湾に集中している半導体生産拠点を分散させるため、人件費の高い米国、日本、欧州などに移転させることに経済合理性はない。しかし各国政府は台湾有事の際のリスクを避けるため、現状のままでは経済合理性が成り立たないものの、自国内での半導体生産に対して多額の補助金をつけることで工場を誘致している。
鈴木一人氏は「日本は、米国の対中規制にも足並みをそろえることが求められる。機微な技術を持つ精密機器などの分野で中国離れが進み、円安のインセンティブから日本へのリショアリングが起こる可能性もある」と指摘する。
リスクを評価する体制構築が必要

PwC弁護士法人
パートナー
中国から撤退して第三国に事業をオフショアリングする場合は、その進出先となる第三国のリスクという別の問題が浮上する。国際法務リスクが専門のPwC弁護士法人 パートナーの茂木諭氏は「移管先が東南アジアなどの新興国の場合、見えないリスク、読めないリスクがある」と話し、企業が直面する新たなリスクを課題に挙げた。
世界中で想定外の事態が頻発する中では、政府もリスクを見通せない。鈴木一人氏は、企業は政府に頼らず、自らリスクを評価して、行動を判断する必要があることに触れた上で、新興国のリスクについては「外資誘致で経済発展を図ろうとしている国については、ある程度豊かになるまで外資を規制する可能性は低いだろう」と見る。かつて日本企業の多くが冷戦後の東側諸国への進出をためらったことを例に挙げ、「日本企業は、何が起こるか分からないアンノウンリスクを極端に避けようとする傾向がある。リスクを過大評価するあまり、機会を逃すことがないように」と注意を促した。

PwC税理士法人
パートナー
国際税務の領域では、自国に企業を誘致するために法人税率の引き下げを競ってきた各国は2021年、多国籍企業の最低法人税率を15%にするための国際的な枠組み「グローバルミニマム課税(デジタル経済課税)」に合意した。2020年にはRCEP(東アジア地域包括的経済連携)も署名されるなど、自由貿易推進の流れが広がっている。PwC税理士法人 パートナーの神保真人氏は「デジタル経済課税については、かつては誰もが合意が困難と考えていたが実現に至った。サプライチェーンに大きな影響を与える可能性はあるものの、中長期で見れば競争の公平性を促進するという意味で日本企業にプラスになるのではないか」と評価するが、その一方で、各国が国内問題によって保護主義的政策を強めていく動きにも注意が必要であると語った。
最後にPwCアドバイザリー合同会社の鈴木慎介氏が「リスクと向き合い、評価し、そのリスクを取るかどうかを判断すべき。そしてリスクが発現したときに対応できるシナリオを含めたサプライチェーン戦略をつねにアップデートすることが大事になる」とまとめた。