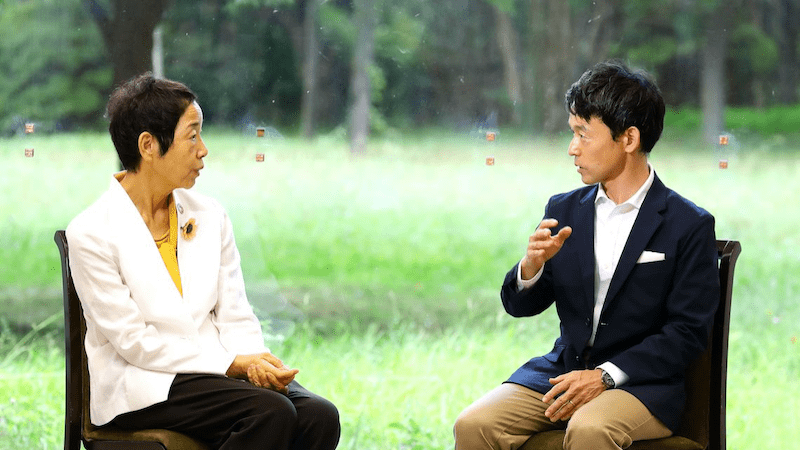パックン×脳医学者が考える「賢い子」の条件 自然体験は子どもの賢さを養う貴重な機会

学んだことを社会で生かせる「リアル賢い人」って?
――まず、お二人が考えられる「賢さ」についてお聞かせください。
瀧靖之(以下、瀧): 賢さの本質を突き詰めるならば、「知的好奇心が旺盛であること」に尽きます。尽きない興味・関心があるからこそ、結果として自主的に学び、覚えようとするものです。また、脳科学的にも、知的好奇心は記憶能力と密接に結び付いていることがわかっています。

パトリック・ハーラン(以下、パックン):知的好奇心と賢さが関連しているのは確かにそうかもしれませんね。僕は芸能界や大学で、すごく賢いなと感じる人とたくさん出会いますが、彼らに共通しているのは、知識が豊富なだけじゃなくて、その知識を現実社会で生かせる「リアル賢い人」だということ。
瀧:「リアル賢い人」という表現、面白いですね(笑)。知識を現実社会で生かせる人は、興味・関心の範囲が物事だけではなく、社会や人間にも及んでいるのだと思います。そのため、必然的にコミュニケーション能力や社会性も高まっていく。つまりパックンが指す「リアル賢い人」は、やはり知的好奇心のレベルが高い人だといえるでしょう。

――いわゆる「コミュ力」も、好奇心と関連しているんですね。子どもの知的好奇心を伸ばすうえで、日本社会に必要なことは何だと思われますか?
瀧:日本は、見た目も考え方もフラットであることを重んじる「均一社会」で、そこから外れることを恐れる傾向にあります。周りの人の顔色をうかがったり、合わせようとするので、自分自身が本当に興味・関心のあることがわかりづらくなる。知的好奇心が育ちにくい環境だといえます。
パックン:日本には「ちゃんとしなさい」という言葉がありますけど、これって英訳しにくいんです。でも日本人同士なら意味が通じますよね。これってすごいことですけど、空気を読みすぎたり、空気を読んでくれる相手に慣れすぎたりする懸念もあります。
瀧:「出る杭は打たれる」ということわざは、「均一な概念からはみ出た行動をすると叩かれる」という忠告ですよね。しかし、世界を見渡せば多様性にあふれており、そのような日本的価値観だけでは通用しません。さらに言えば、皆と同じことばかりしていると、自己肯定感が高まりにくいという問題もあります。

――みんなと同じ行動をしていることにすら、普段はなかなか気づいていないかもしれません。自己肯定感との関係についてもお聞かせください。
瀧:均一さを目指すのではなく、自分の好奇心に従って行動するためには、自己肯定感という土台が必要になります。ちなみに自己肯定感は、「自分は(物事を)成し遂げられる」と思える自己効力感と、「自分はオンリーワンの存在である」と思える自尊感情の2つからなっているといわれます。自己効力感を持ってさまざまな物事に挑戦することで、結果として自尊感情も高まっていくというサイクルです。
パックン:それでいうと僕は、スポーツ、音楽、学業の3本柱で自分の自己肯定感を支えてきました。小学3年生の頃、先生から「ルネサンスマン(多くの話題を知る人)を目指しなさい」と言われたことがあって、多分野で活躍できる人ってかっこいいと思っていたんです。それぞれの分野で優れている人はたくさんいても、僕よりスポーツも音楽も学業もできる人が、漫才まではできないでしょ!? 何より、飽きっぽい性格だから、1つを窮めることはできなかったけど、いろいろできる自分が大好きです。
瀧:私も医者、研究者、ベンチャー企業の経営、趣味のピアノといろいろなことをしていますが、そんな自分が大好きです(笑)。上を見たらきりがありませんが、興味・関心のある分野を大切にして、強みを掛け合わせていけば、唯一無二の自分になれる。さまざまな分野に強みを持つことで、客観的に見てもそんな人は自分しかいないという状態になります。そうなるといやでも自分自身を大事にできますし、自己肯定感が高まることにつながると思います。

「リアル賢い子」を育てるために親ができることとは?
――最近はコロナ禍の影響もありますが、新しい生活様式、クローズドの生活で、どのようにお子さんに接していますか?
パックン:1日の約束として、運動をする、掃除をする、楽器を弾く、そして友達と連絡を取る。こういうことをやらないと、パパと仲良くできないよと言っていました。とくに自粛期間中は、学校に行けないこともあって、近所の友達と、マスクを着けて散歩しに行かせたりしていましたね。
瀧:私もコロナ禍で家から出られない分、息子と一緒に本を読んだり、一緒に昆虫採集や魚釣りに行ったりしました。自然の驚く点は、行くたびに異なる顔を見せてくれるところ。時季や時間帯、天気によって出合う昆虫や魚、植物が変わってきます。ゲームなど人が作った有限のものよりも、無限に広がる自然に興味を持つことで、子どもの「もっと知りたい」という知的好奇心を広げることができると思います。

パックン:子どもの学力調査で上位のフィンランドでは、森に行って木の周囲を測ったり、石の重さを量ったり、自然体験を通して勉強する機会が多いと聞きました。机の上で知識を詰め込むよりも、やはりリアルな体験を通じて学んだほうが、知的好奇心も刺激されるのでしょう。五感で覚えたものは5倍記憶されやすかったりして!?
瀧:おっしゃるとおりで、嗅覚や視覚、聴覚など複合的な刺激は人の記憶に深く刻まれます。これは、書籍や図鑑を通した学びだけでは得られない部分です。ちなみに、私は子どもの頃から蝶が大好きで、空き地でいつも蝶採りをしていました。振り返ってみると、研究者になろうと思ったのは、昆虫採集や魚釣りなど、子どもながらに楽しめる自然体験がきっかけだったと思います。
パックン:僕も幼少期は自然豊かなコロラドで過ごし、いつも外で遊んでいました。木登り、川遊び、キャンプなどいろいろ体験する中で、問題解決能力が高まったと思います。例えば、外遊びをしていたとき、寒さで凍えそうで火をたこうとしたことがありました。でも、着火材が何もなかった。それでどうしたかというと、靴の中敷き(インソール)を燃やして何とか火をつけました。靴の中敷きって燃えるんですよ!

瀧:それはまさに、最近話題のライフスキル「GRIT(やり抜く力)」にもつながりますね。エアコンもなければ電気もあるわけじゃない。自分でやるしかない状態に身を置くことは、子どもたちの生きる力を鍛えることになります。ですから、親ができることとしては、まずは子どもを自然に連れ出すこと。一緒に遊んで、自分自身が楽しむ姿を見せることです。つまり「真に賢い子を育てるために親ができることとは?」という問いに対しての答えは、究極には「親自身が知的好奇心を持つこと」になると思います。
パックン:僕もよく子どもを自然に連れ出していますが、いつも「何でこの葉っぱはこんな形をしているのかな?」とか、自然界のデザインについての疑問をフックに子どもと会話しています。自分が興味あるから、話せる相手がいるとうれしいんです。親が学習を楽しんでいると、子どもも勝手に学ぶことを楽しむようになりますよ。