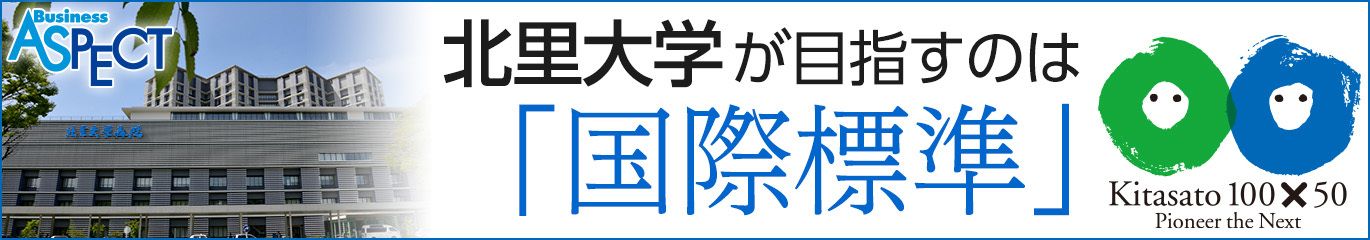医工連携が変える
日本の未来・大学の役割
北里大学

小林 確かに、研究開発体制に医療機器メーカーが参画しているほうが事業化はスムーズに進むかもしれませんね。
その前段の話になりますが、実は北里大学にはスタンフォード大学のような工学部がありません。工学部がないところで医工連携をやると言うと、違和感を持つ人もいるようですが、私は決して不思議ではないと思っています。
前述したように、本学の強みは、医療系学部の人材がそろっていることです。スタッフには医師、看護師、薬剤師のほか、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、診療放射線技師など、医療関係のほとんどの有資格者がいます。さらに、北里大学病院(神奈川県相模原市)、東病院(同)、北里研究所病院(東京都港区)、北里大学メディカルセンター(埼玉県北本市)のそれぞれが特色ある病院であり、さまざまなニーズをくみ上げることができます。
工学部がないことは弱みに見えるかもしれませんが、逆に、さまざまな大学、ものづくり企業、医療機器メーカーとコラボレーションできるという意味ではむしろ強みになるとさえ考えられます。
柏野 そのとおりですね。工学部がないことで、少なくとも学部間のしがらみのような問題が生じることはありませんし、「この技術シーズを使って何か新しい機器ができないか」という技術シーズオリエンテッドな発想に陥りにくいことや、臨床ニーズに対して必要な技術シーズを広い視野で探しやすいことなどは強みと言えると思います。
製品化という観点では、むしろ、医療機器をつくっているメーカーや、そのようなことに興味を持っている企業とダイレクトに組んでいくことが重要です。
医工連携ではよく「病院のベッドサイドのニーズから製品が生まれる」と言います。学長のリーダーシップのもと臨床現場の多くのスタッフが医工連携に参画される(臨床ニーズが提供される)のであれば、医療機器メーカーにとっては非常に魅力的です。このことは、北里大学と医療機器メーカーとが連携し、製品化の可能性が高い医工連携プロジェクトを多数創出できるということです。お話を伺っていると、北里大学は恵まれた環境にあると言えます。
北里発の医療機器を
世界の国際標準に
小林 医工連携が成功するためには知財のあり方についても検討する必要があると思います。これまではたとえば医師が医療のニーズを感じ、アイデアとして医療機器メーカーに伝えたとしても、その企業が特許を取ってしまうということが少なくありませんでした。
もちろん、ニーズだけでは知的財産にならないわけですが、実際に製品化される場合には、ある時点で知財として権利を押さえるということも必要です。