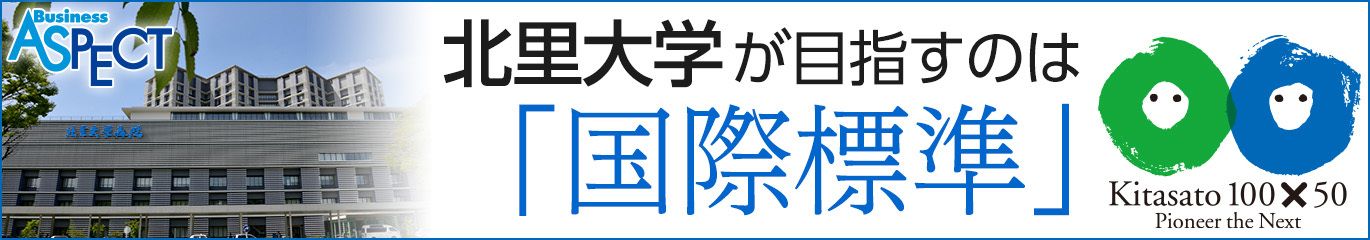医工連携が変える
日本の未来・大学の役割
北里大学
小林 スタンフォード大学が行っているバイオデザインプログラムでは、医学部と工学部、さらにMBAの学生が一つの場所に集まり、協働で医療機器の開発を行っています。医療ニーズを掘り起こすところから、機器の製作、さらにファンドの投資を得てベンチャー企業を立ち上げたり、あるいはベンチャー企業とジョイントしたりしながら、臨床試験まで行い、最終的には大きな会社に自分たちの会社を買ってもらうところまでの一連の流れ(エコシステム)を身に付けられるようになっています。

一般社団法人 日本医工ものづくりコモンズ 理事 総合シンクタンクにて、医療機器関連の調査研究・コンサルティング業務に従事。製販企業とものづくり企業による医工連携のかたち「製販ドリブンモデル」を提唱し、実践に注力している。東京慈恵会医科大学ME研究室訪問研究員、東京大学大学院医学系研究科客員研究員などを歴任。2013年9月より現職(総合シンクタンクとの兼務)
日本ではここまでスムーズな流れをつくることはなかなかできません。特に最終形の製品化のところに到達できないのです。医療ニーズの発掘については、私たちは大きな自信があります。北里大学には四つの病院があり、それぞれの医療ニーズを深く理解している人が多くいます。医療系の学部だけでも医学部、医療衛生学部、看護学部、薬学部があり、スタッフもそろっています。知的財産(知財)についても、研究支援センター、知的資産センターがあり、それぞれがサポートを行っているので、豊富な蓄積があります。ただ、その先が欠けています。グローバルな治験の仕組みや臨床研究の仕組みはあるのに、その間がつながっていません。
むろん、あきらめているわけではありません。今すぐは無理ですが、スタンフォード大学のような形を理想に、将来的にはそのような体制が構築できないかと模索しているところです。
新規の参入障壁が高い
医療機器の製造販売
柏野 北里大学に限らず、医工連携の事業化はなかなかハードルが高いというのが現状ではないでしょうか。
先に結論を言ってしまえば、医療機器はかなり特殊な産業であることが大きな理由です。まず、製品を販売する相手が医師であること。さらに、医療機器そのものが薬機法(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」:旧薬事法)という法規制の対象ということです。

ですから、医療機器の製造販売などを経験したことのない企業は、たとえ技術力があっても、なかなか製品化にたどり着けません。
もともと、医工連携の取り組みがスタートした当初は、医療機器以外のものづくり企業を医療機器産業に参入させて、収益や雇用を生み出そうというのが狙いでした。これらの企業と医療のニーズを結びつければ、イノベーションが生まれるのではないかと考えられてきました。ところが、いざ実際にやってみると、市場や法規制の特殊性があるので、なかなか難しい。構造やコストも折り合わない。
現在では、やはり医療機器メーカーにつくってもらったほうがいいのではないか、最初から組んだほうがいいのではないかという考え方が主流になっています。