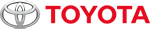トヨタが見せた、「公共交通の未来形」 減っていく「地域の足」をどう維持するか

「これまで車いす仕様車などさまざまな福祉車両を手掛けてきましたが、高齢者の介助に必要な工夫は無限にあり、あらゆる視点からの試行錯誤が必要になります。今回の取り組みを通じて福祉車両の改良を重ね、さらなる技術開発を進めていきたいと考えています」
トヨタでは、いち早く福祉車両の開発を手掛けてきた。生産体制についても福祉車両専用のプラットフォームを設置し、インライン生産も開始している。なぜトヨタが福祉車両開発に力を入れてきたのか。高齢社会を迎えた日本では今、高齢者の在宅比率が増え、身体の不自由な高齢者を介護するために専用のクルマが必要になってきている。トヨタはこうした社会的課題を解決するために福祉車両の開発を本格化したのである。トヨタは現在、標準型の福祉車両で約7割のシェアを持つ一方、トヨタ車全体で見ると福祉車両の割合はまだ1%に過ぎないという。

今回トヨタが横手市に提供した福祉車両「ウェルジョイン」(送迎仕様車)は、乗降しやすいように専用の手すりを設置したほか、3列目シートに乗り込む際の通路確保のために、2列目シートを1つ取り外している。乗降のたびに、2列目シートを前後にスライドさせる必要がないので、有償ボランティアドライバーの負担軽減にもなり、ボランティアドライバー確保にも寄与している。
横手市の社会実験は今、横手市増田町の狙半内地区で進められている。同地区は冬季には積雪が2m近くに達する山間部の豪雪地帯にある。

奥山 良治
この地区では現在、60代を中心とした有償ボランティアドライバー7名が、週3日、1日4往復でミニバスを運行している。狙半内地区の戸数は150戸ほど。一人暮らしの高齢女性も多く、地元の要望は、病院やスーパーがある近隣地への送迎が多い。この社会実験を決断した狙半内自治会・狙半内共助運営体会長の奥山良治氏(67)が言う。
「これを単なる社会実験で終わらせてはいけないと考えています。クルマは人が自由になるためにあるもの。身体が不自由な高齢者にも移動手段は不可欠です。今回の試みによって、いろいろなデータを蓄積し、独自の共助のかたちを具現化することで、ほかの地域でも活用できるようなモデルを構築していきたいと考えています」
住民自らが助け合い地域がつながる社会に
実際、走ってみるとわかるが、豪雪の中の移動は危険と隣り合わせだ。運転手はまず出発時にアルコール検知器でチェックを受けた後、運転しづらい雪道を一定のスピードで走りながら、各高齢者宅の前で乗客をピックアップしていく。移動中も吹雪が続く。細い道が続くところでは対向車との譲り合いも必要だ。過酷な環境の中、徒歩で町の中心部まで行くことはほぼ不可能なことだとわかる。クルマがないと生活はできない。