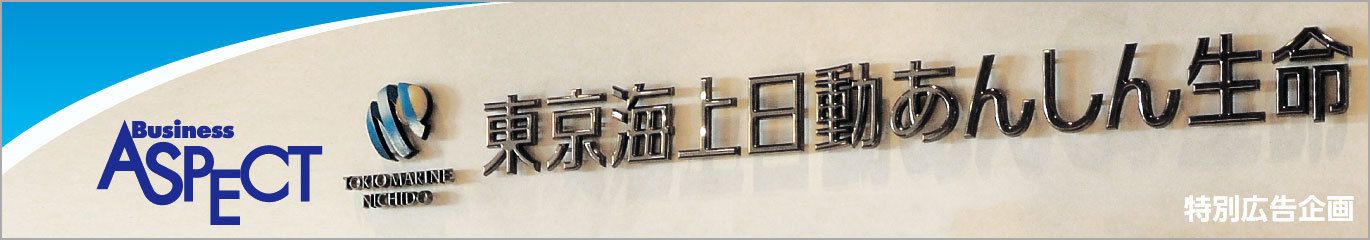「働きながらがん治療をする」社会へ 東京海上日動あんしん生命保険
企業に努力義務を求める改正がん対策基本法
日本人の2人に1人が一生のうちにかかるとされる、がん。国民病とも言えるこの病気の治療水準の引き上げや地域格差解消を目指して2006年に成立したのが、がん対策基本法である。そのちょうど10年後に成立した改正がん対策基本法について、キャンサー・ソリューションズ社長の桜井なおみ氏はこう評価する。
「第8条に、『事業主は、がん患者の雇用の継続等に配慮するよう努める』と明記されました。国はそれまでこういう問題があることを認めていませんでしたし、就労問題は患者個人の問題とみなされる傾向がありました。この改正により、これからは雇用主も対応を考えていかなければいけません。たとえ努力義務でもこの一文が入ったことには大きな意義があります」

桜井氏はかつて自身ががんを経験したことから、がん患者の就労支援を中心にした活動をするためキャンサー・ソリューションズを立ち上げ、がん対策基本法の改正も働きかけてきた。厚生労働省のがん対策推進協議会の委員も務めている。
今回の改正では、国や地方公共団体に、がん教育の推進を求める条文も新たに加えられた。この点も桜井氏は評価する。
「がんに対する理解を促進させるためにも、また自分ががんになったときに困らないようにしておくためにも、がんに対する正しい知識を持つことはとても大切です」
ではがんに対する正しい知識とは何か。それは一言で言うなら、先入観による誤解を解くことだ。たとえば、がんと聞いて「死」を直接的に連想する人は多い。日本人の死因として、がんは長年にわたり第1位なのだからそれも無理からぬところはあるが、国立がん研究センターが今年2月に発表したがんの10年生存率*は58.5%と6割近くに達している。5年生存率で見れば69.4%と実に7割近いのだ。早期発見の技術を含む治療技術の進歩や新薬の発見により、「がん=不治の病」ではなくなってきている。
*「全国がん(成人病)センター協議会の生存率共同調査(2017年2月集計)」における、00~03年(10年生存率)と06~08年(5年生存率)にがんと診断された人のデータ