
ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)は2月20日、ニューヨークで据え置きゲーム機「プレイステーション(プレステ)」の後継機構想を明らかにした。名称は奇をてらうことなく「プレステ4」。過去のブランド資産をそのまま活用する道を選んだ。
発売は今年の年末商戦。ソニーにとってはプレステ3以来、7年ぶりの据え置きゲーム機だ。しかし、これまでとは異なり、そこにソニー独自開発の半導体技術を埋め込んだわけではない。中核半導体にはインテル互換チップで知られる米AMD製のx86半導体を用いる予定で、いわば「ハイスペックのパソコン」に過ぎない。
ソニーはすでに半導体製造事業を縮小している。独自開発するような資金的な余裕もない。外販チップを購入して作るしか道はないことは重々、わかってはいた。しかし、こうして正式に発表になったことで、ソニーは「未来を先取りする会社」ではなくなったことを、あらためて実感した人も多いだろう。
未来を詰め込むハコ
かつてソニーにとって、ゲーム事業は最先端テクノロジーを詰め込むハコだった。2000年発売のプレステ2にはソニーが独自開発した中核半導体「エモーションエンジン」のほか、当時は高価だったDVDドライブが用いられていた。2006年発売のプレステ3にはスパコンもびっくりの処理性能を誇る半導体「CELL(セル)」、ブルーレイディスクドライブが採用された。
当時、SCEを率いる久夛良木健社長の目標は、ソニー発でポスト・インテルのビジネスモデルを生み出すことにあった。プレステ3向けの量産によりコストダウンを果たしたセルがテレビ、レコーダーなど多くのAV家電にも搭載されることを想定していた。
久夛良木氏はプレステのことを「ゲーム機」と呼ぶと、それだけで不快感を示していた。汎用にも耐えるコンピュータという位置づけだった。高い処理能力を持つセルをネットワークでつなぎ合わせれば、大きな処理能力を生み出すことができる。現在のように巨大データセンターに処理能力を集中させるクラウドコンピューティングではなく、分散コンピューティングを想定しており、まさに「ソニーの未来像」を具現化したマシンだった。
久夛良木氏は半導体こそがすべての付加価値の源泉で、ここをソニーがグリップすることが重要だと考えていた。インテルチップを搭載したパソコン「VAIO」を販売しているのは一時的な仮の姿であり、いずれは独自チップを生み出し、「ウィンテル」のビジネス支配を打ち破ろうと考えていた。



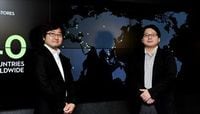



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら