青学原監督「ヘルスリテラシー向上」促す納得理由 自ら身に付けた知識を活用し、力にするには?

長く続く組織には、「強い理念」がある

代表取締役社長
玉井 孝直 Takanao TAMAI
1971年生まれ。精密機械メーカーを経て、2000年ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル カンパニー入社。ファイナンス担当バイスプレジデント 兼 CFO、アジア太平洋地域エチコン事業バイスプレジデント等を歴任。18年よりジョンソン・エンド・ジョンソン代表取締役社長 兼 メディカル カンパニー プレジデント。24年からは医療機器の業界団体である米国医療機器・IVD工業会(AMDD)の会長も務める
玉井 人生100年時代といわれる今、私たちが「自身にとって最もよい人生を送る」ためには、健康や医療に関する情報を正しく判断し、適切な選択や行動をすることが大切です。まさに“人生100年時代を幸せに生き抜く力”であるともいえるでしょう。
人々のヘルスリテラシーが向上することは、個人の健康・人生という枠を超え、限りある医療資源もより適切に使われ、社会全体がサステイナブルになることにもつながり、社会全体に好循環をもたらすと考えています。
そうした取り組みの礎となっているのが「我が信条(Our Credo)」という当社の企業理念です。約80年前に起草されたものですが、世界のジョンソン・エンド・ジョンソン グループ全社員の共通の価値観であり、“経営の羅針盤”であり続けています。
人々の健康・命に貢献したいという強い思いの根底には、つねにこの「我が信条」があります。

陸上競技部監督/地球社会共生学部教授
原 晋 Susumu HARA
1967年生まれ。2004年から青山学院大学陸上競技部監督に就任。改革を進め、同部を何度も箱根駅伝総合優勝に導く。2019年より地球社会共生学部教授。2025年の第101回箱根駅伝では、2年連続8回目の総合優勝を果たした
原 強く、長く続く組織には、やはり「理念」がしっかりあるのですね。そこには自分たちのことだけでなく、社会に対して何ができるのか、といった思いが語られているように思います。
私たちも創部の頃から、「箱根駅伝を通じて、社会に有益な人材を育てる」ということを理念に掲げてきました。重要なのは勝敗だけではなく、4年間を通じて社会に有益な人材を育てていくという思いでずっとやってきたのです。
そのおかげで、多くの皆さんから応援と共感をいただいているのだと思います。ところで、日本におけるヘルスリテラシーの現状はどうなっているのでしょうか。
正しい「ヘルスリテラシー」の知識は、“自分の力”になる
玉井 日本のヘルスリテラシーの現在地を把握するために、当社が実施した「人生100年時代 × デジタル社会の総合的なヘルスリテラシー国際調査」では、日本のヘルスリテラシー(健康情報を入手し、理解、評価し活用するための知識、意欲について)の自己評価は6カ国(日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア、中国、フィンランド)中、最も低いという結果でした。
残念ながら、まだまだヘルスリテラシーが高いとはいえず、より詳細に見ていくと、例えば、病気の症状・治療法に関する情報を判断できない、医療情報が正しいか誤っているかの判断基準がわからないなど情報の判断に自信がない人が多くなっています。
疾患の予兆に対する適切な行動に自信がない、また体調が悪くても様子を見てしまう、といった傾向も見られました。
加えて、医師からの説明への理解を深めたり、質問したり、自分の意見を伝えたりすることに自信がない人や、医療におけるデジタルツールの活用などもまだ進んでいないという結果が出ており、総じて課題が多く見られました。
ただ、日本では「健康寿命」という言葉は浸透しており、「健康に長生きしたい」と考えている人は多く、意欲は高い。私たちがヘルスリテラシー向上のためにできること、するべきことの意義は大きいのではと考えています。
原 リテラシーとは「情報を正しく理解し、活用する力」ですね。情報を正しく理解し、身に付けた知識は自分の力になります。
私も陸上界に復帰したとき、ランニングに関する情報があまりにも古く、正しく反映されていないことに驚きました。そこで、監督に就任した頃から、このランニングリテラシーを高めることに努めてきたのです。
一例ですが、選手のスタミナが切れてしまうということがある。じゃあカロリーを補給すればいいかというと、そうじゃないんですね。メカニズムとして、何が起きていたのか。故障中などで練習量が落ちるため、
そうやって、情報を正しく理解し、活用するために、一つずつ行動してきた結果、今のチームの強さにつながる一因になったと思っています。
玉井 そうですね。正しい情報を得て、行動を起こすことは力になります。当社でもそんな思いで、2023年から「My Health、Myself― 私の健康のために、私ができること。」という、ヘルスリテラシーの向上を推進するプロジェクトを実施してきました。
私たち一人ひとりが健康や医療との向き合い方を知り、行動することで、人生100年時代を誰もが自分らしく生きられるようになると思います。
また、一人ひとりのヘルスリテラシーの向上は、個人の健康やQOL(生活の質)を向上させるだけでなく、医療機関による適切な治療選択肢の提供、医療資源の適切な活用にもつながります。それによって、人々が健康で幸せに、充実した人生を過ごせるサステイナブルな社会につながることを、このプロジェクトでは目指しているのです。
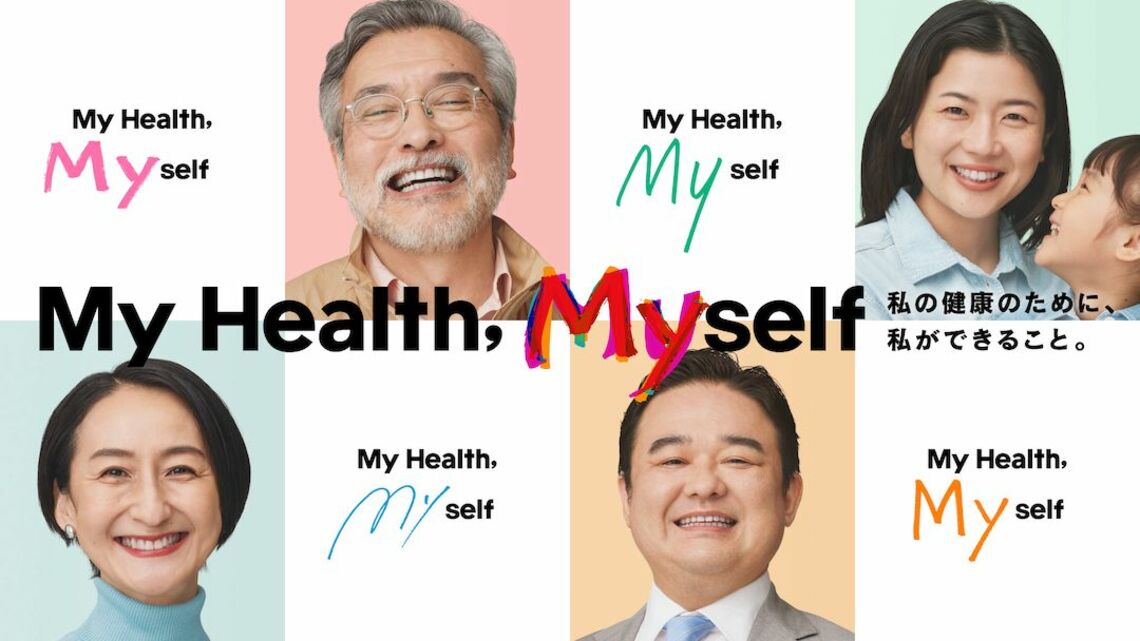
「駅伝選手」も「ビジネスパーソン」も“アスリート”である
原 確かに行動を起こすためにはリテラシーが重要で不可欠です。駅伝にもそれが言えます。
陸上競技とは、個人が己の肉体を使って勝負する競技になります。そのため、選手が成長するには、まず自分自身、そしてランニングについての必要な知識を身に付けて、理解することが欠かせません。
そのうえで行動に移し、得た知識を定着させていくことも重要です。
そのために、私たちのチームでは目標管理ミーティングを欠かさず行っています。自分の課題は何か、自らの目標を短期、中長期で設定し、自分で行動すべき項目を定め、実践していく。そのプロセスはグループでディスカッションしながら進めていくようにしています。それがチームとしての強さやパフォーマンスにもつながっていると思っています。

玉井 とても興味深いですね。アスリートもビジネスパーソンも、つねに最大のパフォーマンスを出し続けることが必要という点で、同様の考え方ができると感じました。
自身の最大限の力を必要なタイミングで発揮したり、可能性を最大化させたりするためには、環境づくりが不可欠です。
それを健康に置き換えてみれば、身体の健康に加え、心の状態や自身のエネルギーをマネージし、「何のために」という目的意識や「強い思い」といったモチベーションを保つことが何より重要ではないかと思います。
当社社員へも「強い思い」を持つことの大切さは繰り返し伝えています。駅伝も同様だと思いますが、ビジネスにおいても、1人の力だけではなく、チームとして最大のパフォーマンスを出すことも求められます。
一人ひとりが心身の環境を整えたうえで、目標達成のために努力し、働くことに誇りを持てるチームをつくり、パフォーマンスを最大化していくことが重要ですね。
徹底的に繰り返し、意識変容・行動につなげていく
原 陸上競技は自分の身一つで戦うものなので、いいトレーニングをしていても、健康管理ができていなければパフォーマンスは落ちてしまいます。
何よりも自己管理していくことは欠かせません。そのためには、チームとしても、選手に同じことを“繰り返し”言い続けることが必要です。この“繰り返し”がポイントなのです。
一例ですが、私たちのチームでは、毎年トレーナーに来てもらって、選手たちに体の構造を説明してもらう機会を設けています。体の構造を理解し、血液の数値から何がわかるのか、その意味合いなども理解してもらっています。どんどん難しい知識を追加するのではなく、毎年繰り返し徹底的に基礎の知識を教えます。
そうすることで、基礎の知識が身に付くのはもちろんのこと、興味を抱いた学生は、自主的に自分で掘り下げようとするのです。
玉井 よくわかります。当社も、社員自ら「My Health, Myself」を実践することが重要だと考え、全社ミーティングなどでも継続的に伝えています。
また、当社には臨床医経験のある社員もいますので、社員同士で医師役、患者役に分かれロールプレイングすることで、ヘルスリテラシーの大切さを学ぶイベントを開催したりしています。
人の意識や行動が変わるには、目的や目標を持つことがまず根本にあり、それを実現するために、適切な行動に必要となる正しい知識を持てるよう、学び続ける姿勢、行動する意思が重要だと思います。
また、組織が最大のパフォーマンスを出していくには、会社の枠を超え、さまざまな視点や専門性を持った多様な組織や人とパートナーシップを組み、エコシステムとして長期にわたって取り組むことも重要です。当社でいうと、民間企業はもちろんのこと、行政、業界、アカデミア・医療従事者の皆様を含めたさまざまな人や組織との協業・共創が欠かせません。
そうすることで、当社の扱うメドテック(医療機器・ソリューション)で、医療・治療を支えるための継続的なイノベーションを起こすことができ、このイノベーションを日本の医療・患者さんに切れ目なく届けられる。そのイノベーションを人々が享受し、より健康に過ごすことができるサステイナブルな社会をつくっていくことができるのです。
駅伝に学ぶ、個々の力を超えた「チームとしての強さ」
原 駅伝競技でも同様のことが言えます。駅伝は選手が単独で走りますが、多くの支えている人たちの集合体で成り立っています。
それが駅伝競技なのです。

興味深いのは、必ずしも、速くて強い選手だけをチームに集めれば勝てるわけではないことです。ポイントになるのが一体感です。以前、一度だけ、大学選抜の監督をやったことがあります。大学選抜というだけあって、速い選手が集まっているわけです。歴代の大学選抜の監督としては、いい成績を収めたのですが、選抜チームは1位になれなかった。答えは一体感なんですね。
やはり一体感があるチームは強い。チームとして一体感があるほうが結果は出やすいのです。
ビジネスにおける協業・共創も、一体感を持って、共に学び、競い合う環境だとより力を発揮できるでしょう。ヘルスリテラシー向上を浸透させていくという点においても、こうした環境づくりや、どう活用するのかという視点が必要かもしれませんね。
玉井 そうですね。ヘルスリテラシーにおいては、単に「情報を探す・読み解く」だけではなく、「正しいか」「自分に合っているか」といった視点で評価し、さらにその先、自分や自分の周りの大切な人のために、どうその情報を使いこなしていくかが重要です。
まさに、自分への視点と、全体への視点が必要なのですね。
そのうえで、情報源が信頼できるかどうかの見極めや、適切なタイミングでの医療機関への受診といった行動も重要です。早期受診により、治療の選択肢も広がり、より安全で効果的な治療を受けられる可能性が高まります。多くの疾患では早期発見・早期治療がカギとなるからです。そのためには、健康診断やがん検診を定期的に受けて、自分の体の状態を把握しておくことも重要ですね。
さらには、受診した医療者とのコミュニケーションの際には、自分自身の価値観も加味して医療者と治療方法を決められるとよいと思います。そのためには、日頃から正しいヘルスリテラシーを身に付けておくことが欠かせませんね。
挑戦した失敗は失敗にあらず。「何もしないこと」が失敗
原 行動するにはまずチャレンジをすること。そして失敗を容認するという2つの視点があると思います。
私は、失敗とは「何か事を起こして誤りをすること」ではなく、「何もせずただ立ち止まっている行為そのもの」だと捉えているのです。
ヘルスリテラシーにおいても、そう言えると思います。
1つずつ、まずはチャレンジしてみること。まず健康についての知識を付けてみる、お医者さんに間違ってもいいから質問をしてみる、健康診断を受けてみる。立ち止まっていても前進はありません。この変化が激しい世の中で、つねにチャレンジする勇気を持つことが重要です。真剣にチャレンジしたときの失敗は失敗ではない。
もし失敗しても成功に変えるよう反省して、次に向けて頑張ること、何よりも真剣に行うことが大事なのです。ヘルスリテラシーも真剣に取り組んでいくことが欠かせないと思います。
玉井 私もそう思います。ヘルスリテラシーは健康や医療に関する問題に対して、自分にとって納得いく解決策に近づくことができる、とても大きな「力」であり、「資産」になります。
当社としても、日本の医療・患者さんにとって必要なメドテックのイノベーションを届け続けるとともに、人の健康・人生、ひいてはサステイナブルな社会づくりに貢献できるよう、多くの皆様と共に、協業・共創を続けていきたいと考えています。
それには私たち自身も、つねに新しい視点を取り入れ、学び続け、進化していくことが大切だと考えています。今日は原監督から多くの視点や示唆をいただきましたので、これらをさらに生かしながら、人、医療、社会にポジティブなインパクトをもたらし、よい循環をつくることに貢献し続けられるよう、これからも皆様と共に取り組みを続けてまいります。





