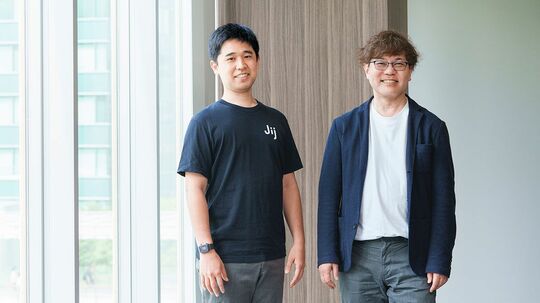量子コンピューターが「ビジネスに影響大」の根拠 識者が語る「投資先として現実的な選択肢に」
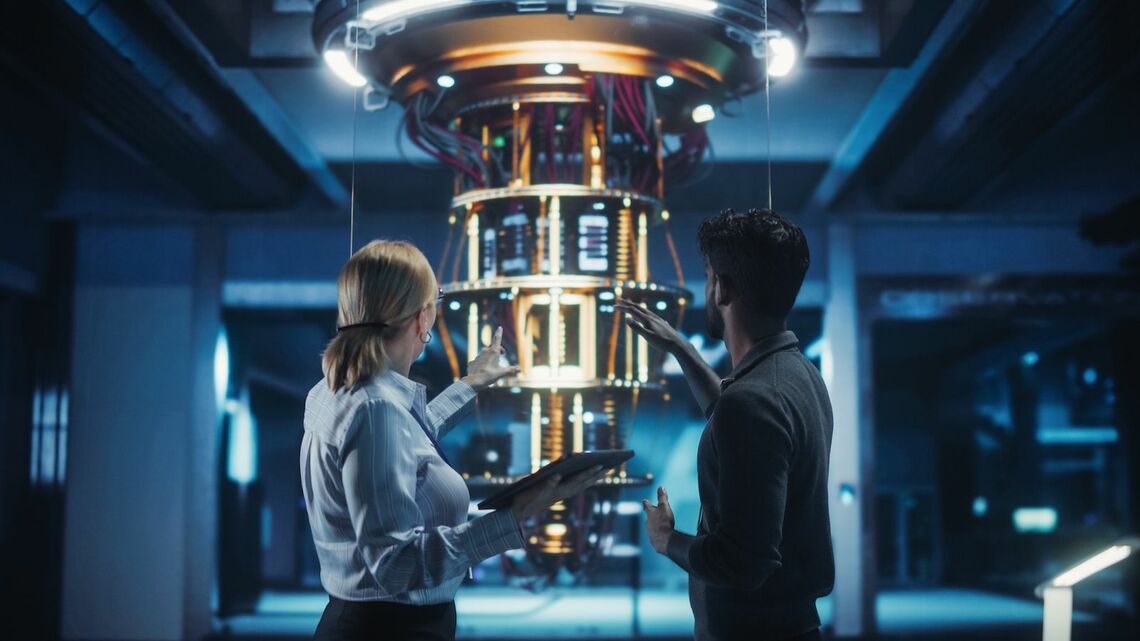
「消費電力の少なさ」から始まった量子コンピューターという発明
――量子コンピューターの革新性について教えてください。
最も革新的なのは「消費電力の少なさ」です。現在、SNSや生成AIの活用、インターネット検索など、あらゆる用途で大量の電力が消費されています。電力の消費量が増えるとコストがかかるうえ、地球温暖化にも影響を与えます。その課題への解決策として、量子コンピューターが期待されています。
なぜ量子コンピューターは電力消費が少ないのか。従来のコンピューターが0または1を表す「ビット」を厳密に区別するのに対し、量子コンピューターは0と1の両方を重ね合わせた状態である「量子ビット」で計算できます。
「0かもしれないし1かもしれない」というあいまいな状態でも、両方の可能性を重ね合わせながら柔軟に計算できる。その動作原理から省電力で動作します。
従来のコンピューターは0か1しか表せないため、大量の計算を繰り返して解にたどり着く必要がありますが、量子コンピューターなら1回の計算で済むので、さらに消費電力が少なくなる分野もあります。
かつて、コンピューターが大型から小型へと進化する中、電力不足が予測されるようになりました。同時に「エネルギー消費ゼロのコンピューターは実現できるか?」という問いが生まれ、実現できるとしたら量子コンピューターが1つの候補だと考えられるようになったんです。
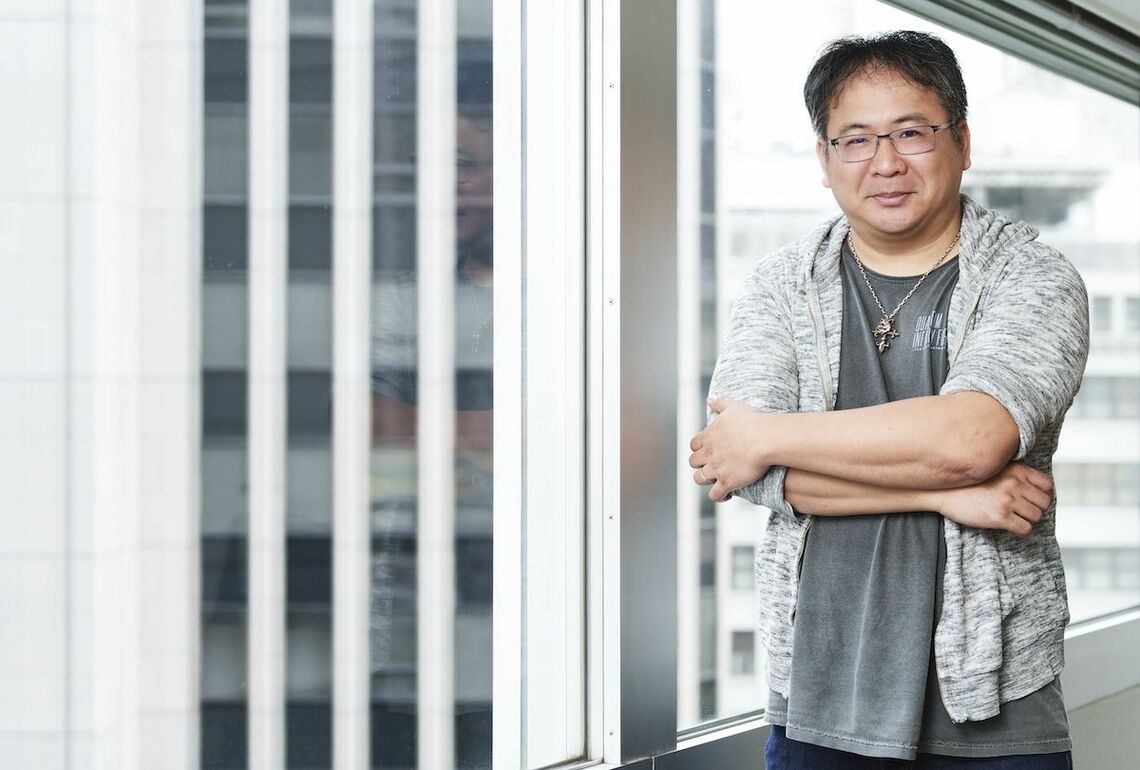
東北大学大学院情報科学研究科情報基礎科学専攻教授
東京科学大学理学院物理学系教授
シグマアイ 代表取締役
――具体的には、どのくらい消費電力が少なくなりますか。
私たちが普段使っているようなコンピューターで数十〜数百ワット、高性能なスーパーコンピューターはその数十万倍の電力を消費します。一方、超伝導タイプの量子コンピューターは数十fW(フェムトワット)の電力しか消費しません。聞き慣れない単位ですが、1000兆分の1ワット、つまりほぼゼロの消費電力で済みます。
しかし現時点では、超伝導状態にするために冷却する必要があり、その消費電力が大きいとされます。今後、高い温度でも超伝導状態を維持できる素材の開発が進めば、この課題もクリアできるでしょう。従来のコンピューターチップは量子コンピューターチップに置き換えられ、将来的には、消費電力を意識せずにコンピューターを使える時代が訪れるかもしれません。
量子コンピューターを活用すると大きなビジネスインパクトを得られる
――量子コンピューターは、ビジネスの現場にどんなメリットをもたらすのでしょうか。
量子ビットを利用した技術の中でも、組合せ最適化計算に特化した「量子アニーリング技術」はさまざまな業種に利用されています。とくに材料化学や製薬業、製造業、物流などを中心に大きなメリットがあるでしょう。
すでに、量子コンピューターを活用して材料や薬の性質を解き明かすシミュレーションを行っている企業や、倉庫内を最適化することで効率化を実現している物流関連の企業もあるようです。

量子コンピューターの強みを生かせば、従来は難しかった高速な計算や意思決定ができるようになり、経営にも好影響が生じると考えられます。
中でも量子コンピューターの効果を大きく享受できるのは、DXが進んでいる企業です。例えばロボットの活用を通じて自動化を進めている倉庫や工場では、人間が介在しないほうがシステマチックに動けるので、最適化に向いています。ロボットが作業しているので、すぐに量子コンピューターの指示どおりに製造を進められます。
業種や業態によらず、企業が早期から量子コンピューターを試すことで、人材育成の観点も含め、長期的にメリットを享受できます。戦略的に「量子コンピューターに触れた経験がある人」を増やすことは、イノベーションの種まきや、社外向けのPRなどにもつながるでしょう。実際、すでに取り組んでいる企業の成功例が呼び水になり、活用の裾野を広げ始めています。
――日本と海外との違いについてはいかがでしょうか。
量子コンピューターのハードウェア開発・製造に関しては、米国が先行しています。一方で、研究分野や一般企業における活用においては、日本もそうとう進んでいます。世界的な研究発表の場でも、日本企業による発表が目立ちます。企業が研究投資をする中で、産業利用の具体的な用途を考えてきたことが有利に働いているのではないでしょうか。
ただし今後は、日本も量子コンピューターの開発に力を入れていく必要があります。現在は他国に頼っている部分が多いため、地政学的リスクや貿易取引のリスクを避けられません。経済安全保障の観点でも、国内企業が量子コンピューターを製造したり、一般企業向けにサービスを提供したりできる状態を整えておくことは非常に重要です。
長期的に世界で発展。投資先として現実的な選択肢に

――企業が量子コンピューターを活用する際の注意点について教えてください。
量子コンピューターはどのような難しい問題も解決できると考えている方もいるかもしれませんが、それは幻想です。素因数分解を速く解けることは間違いありませんが、それが有効な領域とそうではない領域があると理解する必要があります。
例えば、組合せ最適化問題で代表的なのが「巡回セールスマン問題」(複数の都市と各都市間の距離が与えられ、すべての都市を一度ずつ訪れて出発点に戻る最短ルートを求める問題)です。
このように解くのが非常に難しい、いわゆる「NP困難」と呼ばれる難解なものは、量子コンピューターでも解けないとみています。
また、量子コンピューターにはノイズが含まれることがあります。それでも、分野や用途によっては十分な精度を持っていますし、今後も精度が上がっていくでしょう。どのような分野でも期待を持てます。
長期的な目線で考えると、量子コンピューターは、間違いなく世界各国で発展していく分野です。活用方法も今後ますます広がっていくでしょう。今すぐビジネスシーン全体に大きな革命を起こすものではないものの、企業の経営レベルに大きなインパクトをもたらすテクノロジーです。そのことを正しく理解し、ぜひ前向きに考えてもらえればと思います。