持続的成長に向けた日本企業の変革のあり方 Finance Leaders Summit 2025

自社の存在価値を問い直して実現した「両利きの経営」
AGC 代表取締役 社長執行役員 CEOの平井良典氏は、「AGCの企業変革―両利きの経営と企業カルチャーの醸成―」と題した講演で、2015年からスタートした同社の企業変革について語った。
「ディスプレイ用ガラス基板事業の成長によって、10年に過去最高益を達成しました。しかしそれは、11年のデジタル放送への移行に伴う液晶テレビへの買い替え需要によるもので、そこがピークであることは予測されていました」
同社は状況を見越し、新事業の種まきを進めていた。しかし、全社を支えるレベルまでには育っておらず、結果として11年から4年連続の減益となり、ピーク時の3割程度まで落ち込んだ。
加えて、業績悪化によってコスト削減を続けたことにより、成長の姿を描くことができなくなっていたことも問題だった。社内では、「挑戦心」「信頼」「技術へのこだわり」「社会的使命感」を示した創業の精神が根底に流れる、元来のよきカルチャーが失われていったという。
その状況を打破すべく、平井氏は「深化」として既存のコア事業の競争力強化と、「探索」として複数の成長事業の創出に取り組み、事業ポートフォリオを組み替えて「両利きの経営」を実践していった。
最たる変化は、“脱自前主義”に舵を切ったことである。自社だけで物事を進めようとすると膨大な時間がかかるため、外部との連携やM&Aを積極的に行ったほか、縦割りの壁をなくすために社長直轄の組織を結成するなどして推進していった。
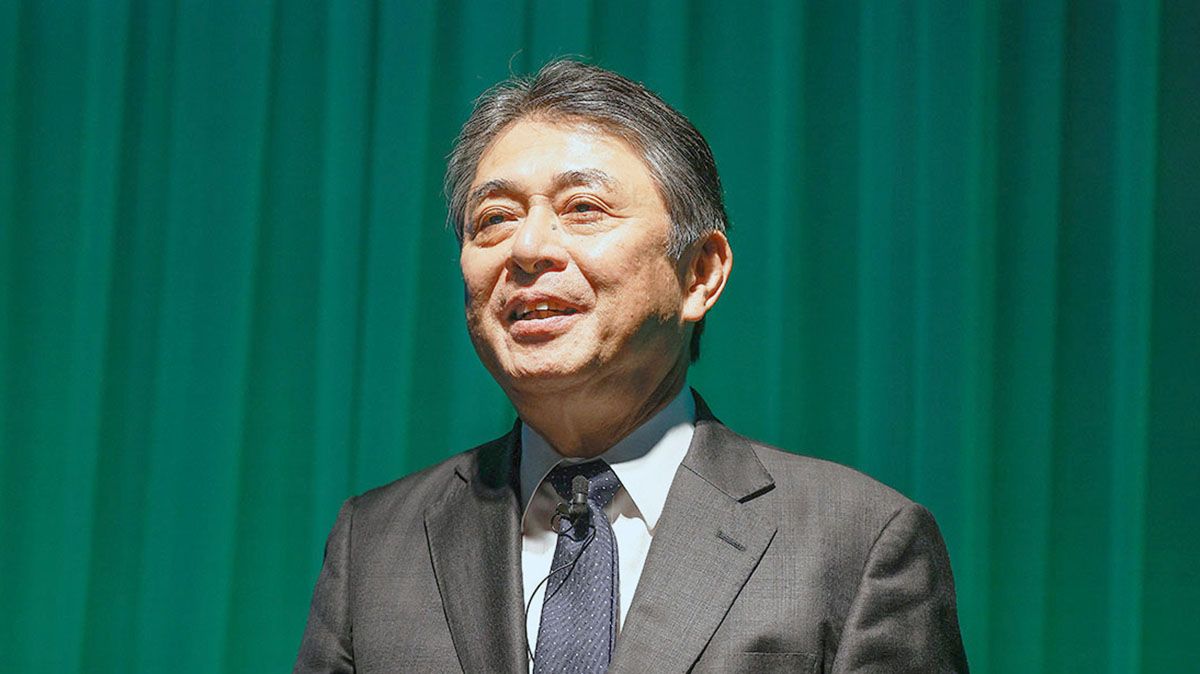
平井 良典 氏
「当初はもちろん反発の声もありました」と平井氏は当時を振り返った。ただ、社内の雰囲気がみるみる変わっていったことを実感したという。
「11年から始めた新事業創出の取り組みは、現在では売り上げ規模約10倍以上、営業利益は全社の約50%を占めるまでに成長しています」
このように両利きの経営を成功させた要因を、平井氏は次のように語る。
「既存の事業部門から新事業創出を担う組織を分離しないと、『なぜ無駄なことをやるのか』と横やりが入りかねません。一方で完全に分離したところ、本業から切り離した出島型になってしまい、思ったような成果を収めることができなかった過去がありました。
そこで、事業部門から分離された組織(“探索”組織)と、既存の事業部門の組織(“深化”組織)を一部結合させて、既存のアセットを活用できるようにしています。この分離と結合のバランスをうまく取るのが、両利きの経営の成功につながる組織設計のポイントです」
同時に、元来同社が持っていた創業の精神を取り戻すカルチャーの醸成と浸透を目的とした企業カルチャーの変革に向けて、社員と対話を重ねることにも力を注いだ。
「当初、直接対話をするのは経営幹部だけだったこともあり、組織全体への浸透はまったく進みませんでした。社員から自分たちと直接対話をしてほしいという声が上がったことをきっかけに、今では若手や中堅層などを含めた各レイヤーとの対話を毎年100回以上重ねています。
結果として実感しているのは、変革はトップダウンとボトムアップが交わるところで起こるということです」
これは、トップダウンを否定するものではない。一方で、従来の「牽引型」や「調整型」のリーダーシップだけでは通用しないとも指摘する。
「日本が産業競争力を失った理由を改めて思い出す必要があります。高度成長期からバブル期のリーダーは、先行する欧米に追いつこうという明確な目標に対して、どう実現するかが問われました。しかし今は、明確な目標設定ができていないのに、高度成長期のリーダー像だけが色濃く残っています。
今日のリーダーには、明確なビジョンや方向性を示し、メンバー一人ひとりの力を引き出しながら育てる力が求められると考えています。そして競争力を高めるには、画一性や無難さを求めるのではなく、多様性や異質性を積極的に受容することが大切です。それによって組織は自発的な活力を持ち、新たなイノベーションを創出できると確信しています」
LIXILの変革を導く対話と化学反応
LIXIL 執行役専務 CFOの藤田真理子氏は、デロイト トーマツ グループ コンサルティング ビジネスリーダーの長川知太郎氏と「企業変革への挑戦と課題」をテーマに対談セッションを実施した。藤田氏は、まず自身のCFO就任を振り返った。

藤田 真理子 氏
「LIXILには優秀な人材がたくさんいる中で、入社してから約2年でCFO就任の打診をされたことは、私自身も非常に驚きました。しかし、ずっと外資系企業で働いてきた“異端”だからこそ、新しい視点での変革を経営から期待されたのだと思います」
少子高齢化が進む日本では、新築の住宅戸数を表す「新設住宅着工戸数」は減少傾向にあり、同社はこれまでと異なるアプローチでのビジネス展開を急ピッチで進めてきた。
新築だけでなくリフォームなどにビジネスの軸をシフトしたことに加え、海外事業を成長のドライバーに位置づけていることも相まって、企業文化やマネジメントスタイルの変化も求められている。
そうしたアプローチを推進する中でのCFOとしての役割を長川氏に尋ねられると、藤田氏はこう答えた。
「当社では、中長期で目指す企業としてのビジョンや方向性を定めた『LIXIL Playbook』を『北極星』として位置づけています。それを実現するうえでCFOに求められているのは、CEOのビジネスパートナーとしての役割です。
CEOが状況を正しく把握し、適切な判断ができるようファイナンスの観点でサポートすること、そして必要と感じたときにはCEOと異なった見解を述べることも、CFOとしての重要な役割であると思います」
同社のような変革を進めていくためには、企業文化や人の変革が必要不可欠だ。藤田氏は従業員のマインドセットも変えていく重要性を説く。
「従業員に失敗を恐れないマインドセットを持ってもらうことが大きなチャレンジです。同じ失敗でも、失敗をした後ですぐに方向転換をできるかどうかが重要です。とはいえ、単に伝えるだけではなく腹落ちしてもらわないと意味がありません。
現在は変化のスピードが格段に速くなっており、こうしたスピード感に適切に対応しつつ、同時に腹落ち感とのバランスを取っていくことに心を砕いています」

長川 知太郎 氏(左)
続いて、長川氏は「企業文化づくりや人づくりにも携わる中で、大切にしている価値観や行動原則は何ですか」と問いかけた。藤田氏は次のように語った。
「自分よりも業界や製品の知識が豊富なメンバーがいるチームに、リーダーとして参画することが多くあります。そうしたとき、必ず2つのことをしています。1つは、『私はすべてをわかっているわけではない』と伝えることです。
解決策の引き出しは多く持っていますが、それがその現場や企業に合うかどうかは、長年携わっている担当者の考えも聞かなければ正確な判断ができないというのが私の考え方です。そのため、選択肢を投げかけたうえで、解決に向けて共に考えることを重視しています。
もう1つは、既存のやり方のすべてを否定しないことです。そのやり方が成立しているのは何かしらの背景があるため、なぜそうしてきたのかを具体的に聞くようにしています。そうすると、聞かれたほうも改めて考えるきっかけとなり、新たな気づきにつながっていきます」
また、これまで複数の外資系企業での経験を通じて、「自分のキャリアの価値は自ら高めていく」という文化が根付いていることを目の当たりにした。キャリアは“ジャーニー”であり、チャレンジを積み重ねながら目的地に向かって進むものであると藤田氏は語った。
「自発的に手を挙げて新しいことに挑戦する姿勢が、個人の成長につながることを実感しています。未経験の分野にチャレンジできる環境があれば、組織内の人材の流動性も高まり、部署等の垣根を越えて、社員同士の相互理解も深まります。今後はこうした仕組みづくりにも力を入れていきたいと考えています」
問いかけや対話を重ねることで“化学反応”が起き、新しい発想が生まれるとともに、相互理解も深まることで、より強い組織へと成長していく。藤田氏は、自身のような“異端”が加わる意義はまさにそこにあると語る。こうした要素がそろうことで、変革に向けて目指すべき「北極星」への道筋が明確になってくるという。
「変革もキャリアも、その“ジャーニー”は決して平坦な道のりではありません。しかし、どれが最適な答えなのかわからない中でも、勇気を持って困難に立ち向かい、意思決定をすることが、リーダーであり数字をつかさどるCFOの役割であると考えています。恐れずに挑戦を続け、企業経営に立ち向かっていきたいと思います」
「トップの本気を伝える」富士通の全社変革
最後に登壇したのは、富士通 代表取締役社長 CEOの時田隆仁氏。「パーパス実現に向けた富士通の全社変革」と題した講演で、変革に向けた経営の舵取りについて語った。
「富士通は、当時グローバルで約13万人いた社員の能力を最大限に生かし切れていない会社だと思っていました。例えばサイロ化の問題が長年指摘されていましたが、一向に解決しませんでした。だから社長に就任した際、真っ先に人事制度の改革に着手しました」
人事制度の変革は、2021年に発表した事業モデル「Uvance」の構想につながっているという。
従来の個々の業種や業務に対峙するビジネスから、社会課題を起点に、さまざまなステークホルダーを一元化されたデータと仕組みをもってクロスインダストリーでつなぐ、一気通貫したデジタルソリューションを提供する事業モデルへと転換するには、社員一人ひとりの行動変容が必要だと考えた。
「キャリアを自ら主体的に築こうとするマインドが社員になければ、このような事業に向き合うことができないという危機感に駆られました。従来型の会社に委ねたキャリア形成ではなく、自分のキャリアにオーナーシップを持たせ自律的な成長を促すためにも、人事制度を全部変えました。
今は全社にジョブ型人事制度とポスティング制度を適用しており、自ら手を挙げない限り昇格はありません」

時田 隆仁 氏
そして社長就任の翌年には、パーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」を定めた。
「社長就任直後から『パーパスドリブン』の重要性を社内に伝え続けてきました。目指す指標を定め、全員で挑戦するための信頼感や共感を築くためです。やはり、全社を挙げてやっている証しは必要だと実感しています」
人事制度を変え、パーパスを策定し、時田氏自らがIRミーティングに出席するなど投資家との対話も重ねた。さまざまな取り組みを進めていく中、コミュニケーションにおいて貫いているのは「トップの本気を伝えること」だと時田氏は語る。
「最も大切なのは経営のリーダーシップです。『TOP FIRSTプログラム』と名付けていますが、まず経営トップが必ず最初に自分事としてアクションを起こします。そして、対話を通じて社員にも自分事化させていくことが、全社変革への大きな一歩だと感じています。
『パーパスドリブン』と同時に必ず言い続けているのが『データドリブン』です。抽象的に富士通が良くなると言われても、本当にそうだろうかと疑念を持つ社員はいるはずです。実際に私自身がそのタイプです。
そういった社員の疑念を解消するためだけではないですが、例えばデータを施策と合わせて総合的に分析し、あらゆる場面でデータを中心とした経営を実現するためにも、社内システムの入れ替えといったことも重要な施策だと捉えています」
データドリブンの環境を整備しているのは、あらゆる戦略を全社で迅速に共有するためでもある。だからこそ、国内外グループ企業を含む全社のシステムや業務プロセスなど、経営資源を一元的にデータ化・可視化する「OneFujitsu プログラム」は、ITプロジェクトではなく経営プロジェクトなのだと強調する。
財務・非財務の指標を示すダッシュボードを活用することで、合理的かつ迅速な意思決定を支援し、数字による裏付けを可能にするとともに、リアルタイム・マネジメントを実現している。
また、富士通ではAIによる経営の高度化にも積極的に取り組んでいる。顧客企業と共同で開発したAIエージェントを活用したサプライチェーンの高度化のケースが共有され、経営の新しい形も示された。
「AIの急速な進化もそうですが、あらゆることが流動的となってきました。コロナ禍を乗り越えたことで、『富士通は変化対応力がついてきた』といろいろなところで発言してきましたが、今は考えが変わりました。
変化を受け入れる側に回るか、変化を生み出す側に回るかで市場における勝負が決まります。富士通は変化を生み出す側となり、『変化創造力がある企業』と呼ばれる存在になりたいと思っています」
目まぐるしい変化の中で、いかに持続的な成長を遂げるか。今こそ、強い推進力をもって変革に挑む姿勢が日本企業には求められている。「Finance Leaders Summit」で語られた三者三様の企業変革への取り組みと、それに対する思いや経営者としての覚悟が、参加各社の変革を加速させる原動力へとつながることを期待したい。
>Finance Leaders Summit 2024「価値創造につながる日本企業の強みと戦略とは」






