価値創造につながる日本企業の強みと戦略とは Finance Leaders Summit 2024

「失われた30年」ではなく「変革の30年」だった
冒頭の基調講演に「日本企業の強みと戦略」と題し登壇したのは、日本の企業戦略や組織論を研究している米カリフォルニア大学サンディエゴ校グローバル政策・戦略大学院教授のウリケ・シェーデ氏だ。シェーデ氏は、一般的にいわれる「日本は30年間停滞していた」という悲観論に対し、異なる見解を示す。
「多くの人が『失われた30年』『停滞の30年』と日本経済の停滞を指摘します。それが本当なら、日本は世界GDPランキングで30位、50位と転落していてもおかしくありません。しかし日本は、2024年現在でも米国、中国、ドイツに次ぐ世界4位の座に就いています。それは、この30年間が『失われた30年』ではなく、『変革の30年』だったからにほかなりません」

ウリケ・シェーデ氏
(『シン・日本の経営 悲観バイアスを排す』著者)
シェーデ氏の指摘によれば、戦後の日本は欧米から技術や生産プロセスを学び、取り入れ、日本流に昇華させてきた。ただ、05年ごろからの約20年間で、日本は「追随者」から「追随される技術リーダー」へと転換し、それがビジネスの再興をもたらしたという。
「戦後の日本企業は、欧米に象徴される『規模の経済』を追求してきました。しかし、これから真の競争力を得て再興するには、技術力やスピードを武器にした独自の戦略が必要です。売上高や雇用で単純に表されるサイズだけではなく、独自の技術や戦略を持って競争に打ち勝つ、戦略的差別化をするべきだと考えます。
具体的には、コモディティー化された製品から脱却し、サプライチェーンの上流、すなわち高い利益率が見込める素材や部品、材料、製造装置などの分野に特化し「方向転換(ピボット)」していくことが挙げられます。実際、既存事業で収益を上げつつ技術革新を続け、付加価値の高い分野で世界的なシェアを獲得している成功例は複数あります」
日本社会や日本企業においては、改革や方向転換に時間がかかることもあるが、シェーデ氏は、「スロー」は選択であると語る。社会の安定と引き換えに日本が支払っている代償であり、停滞ではないと訴える。
そして企業が変革を成功させるためには人々の行動様式を変えていく必要があり、これが最大の課題であるという。そのマネジメントの方法論として、「LEASH Model」を提唱する。
- Leadership……リーダー自らが変革を牽引する
- Employee Involvement……全従業員を巻き込み、変革を自分事化する
- Aligned Rewards……新しい行動を評価し、適切な報奨を与える
- Stories, Signals, Symbols……新たなビジョンを共有し、象徴的な行動を起こす
- HR System Alignment……新しい行動様式を促進する人事制度を構築する
この方法論を実践に移し、LEASH Modelに基づいた変革によって見事に成功を収めた日本企業もある。シェーデ氏は、経営陣が主導して改革に取り組み、社名変更や人事制度改革など大胆な変革を実行した結果、企業価値が向上した事例を紹介した。
シェーデ氏は、日本企業が目指すべき未来として、「新しいバランス」というキーワードを掲げる。
「これからの日本企業は、経済成長だけでなく、社会的な安定性やステークホルダーの幸福も両立させる、新しい経済モデルを世界に示していく必要があります。すでに、たくさんの企業がこの挑戦を始めています。数値化するのが難しい概念ですが、今後さらに重要視されていくでしょう。私は、日本の未来に大きな期待を寄せています」
味の素のグローバル競争を支える無形資産の力
味の素 取締役 代表執行役社長 最高経営責任者の藤江太郎氏は、「グローバル競争における要諦」と題した基調講演で、同社グループが実践する企業変革の全容を語った。藤江氏が冒頭で触れたのは、2019年ごろに味の素グループが直面した、事業成長の停滞だ。
「過去を振り返ると、10年周期で業績の谷が訪れています。その原因は、大きな社会変化への対応不足でした。縦割り組織の弊害で、意思決定が遅く、市場の変化についていけない。成長の停滞を機にこのことに気づき、大きな危機感を抱きました」と、当時を振り返った。

藤江 太郎氏
そこで断行したのが、従来の組織構造や企業文化を根本から見直す、抜本的な改革だった。前CEOの西井孝明氏がパーパス経営への転換を宣言。そして、CDO/CIO/CXOの設置のほか、DX推進委員会を立ち上げるなど、縦型組織のメリットは残しつつ、部門横断的な連携を強化した。
「重要なのは、DXを目的とせず、あくまでツールとして捉える姿勢だと考えました。当社が目指す真のゴールは、社会課題を解決し、人々のウェルビーイングに貢献することです。DX1.0〜DX4.0と4つの段階を設け、本質的な目的を見失わないようにしました」
DX4.0の事例として藤江氏が紹介したのは、ベトナムにおける「栄養改善」に向けた取り組みだ。日本の学校給食システムを応用し、栄養バランスの取れた献立を作成できるソフトウェアの開発やアプリの提供を進めている。
また、自社製品のマヨネーズを使い子どもたちに野菜をおいしく食べてもらう取り組みで、売り上げも伸びた。社会変革しながら利益を上げ、その利益をより大きな社会課題の解決に使っていく。これこそがASV*の一例だと述べた。*Ajinomoto Group Creating Shared Value
「DXに加えて、企業文化の変革、社員一人ひとりが自律的に考え行動、挑戦する『自発型企業文化』が必要だと考えました。具体的には、経営層を含めた社員同士の対話の機会を増やし、年齢や役職を超えたコミュニケーションを促進しています。
また、個人目標を発表する会という施策を導入して、社員が自分の目標を組織全体の目標とリンクさせられるよう、また仲間の取り組みを理解できるように工夫しています。こうして、組織としての一体感や評価制度への公平感を醸成し、社員の能力とモチベーションを引き出してきました」
さらに、財務部門での企業価値の向上のための取り組みにも注力している。具体的には、着実なキャッシュフロー創出と、成長率の向上およびWACC低減だ。
藤江氏は、財務部門の重要性が非常に高いことを強調し、情報の「視える化」を進めること、そしてFP&A(Financial Planning and Analysis)導入を中心とした財務と現場双方の視点を持つメンバーが事業側との相互信頼を築くことが、企業価値を高めることにつながっているという。
現在は、2030年に向けた挑戦的な目標を設定し、それに基づくロードマップを策定し実行力を磨き続けることで、企業価値の向上を図っている。
「経営者が覚悟を決めてリーダーシップを発揮すること、そして社員が働きがいや生きがいを感じながら仕事をすることは、大切な無形資産だと思います。当社の成長は、自発型の企業文化とイノベーションの精神に支えられてきました。これからも挑戦することを恐れず、価値を創造し続けて、持続可能な成長を実現していきます」
経営プロセスの刷新と非財務情報による企業価値の向上
最後に、日本電気 取締役 代表執行役 Corporate EVP 兼 CFOの藤川修氏が登壇。「自社の強みをいかに捉えステークホルダーに伝えるか」というテーマの下、対談セッションが行われた。聞き手は、デロイト トーマツ グループ ボード議長の永山晴子氏が務めた。
藤川氏自身は、NECに入社後、長年にわたり、金融機関向けのシステム開発や新規事業の立ち上げなどに携わってきた。2021年にCFOに任命され、現在に至る。現社長の森田隆之氏に続き、2人目の事業出身のCFOとなる。
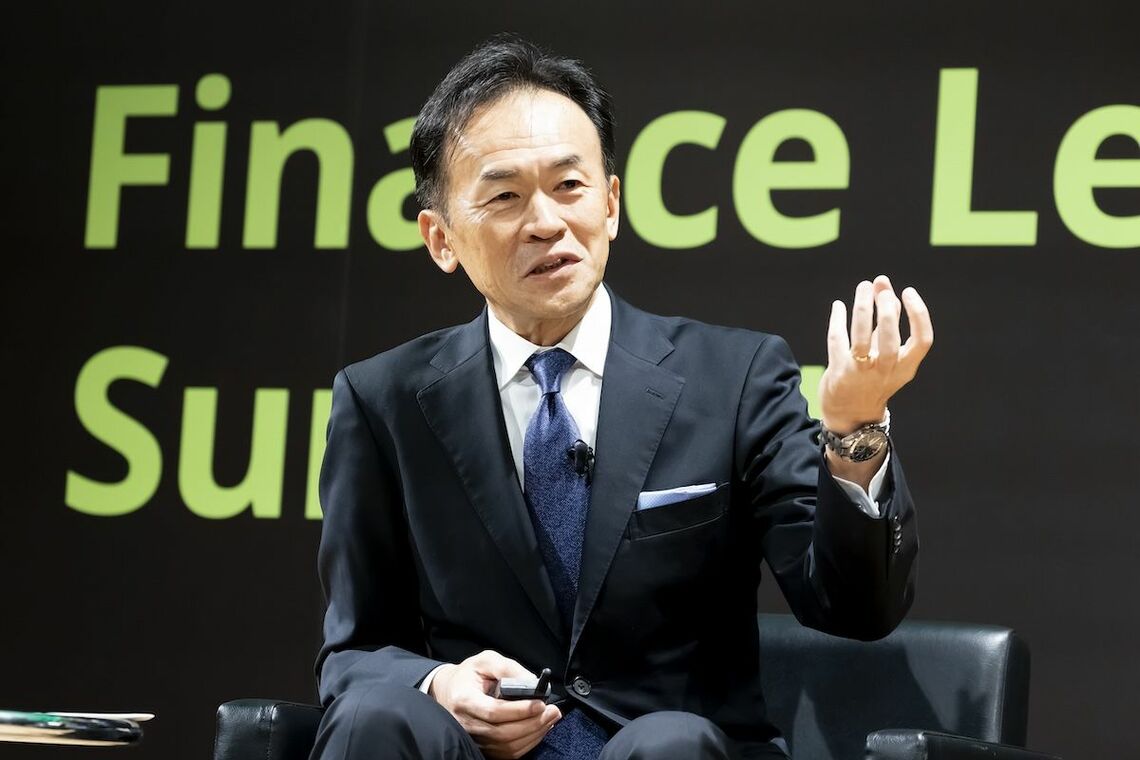
藤川 修氏
「私は現在、経理財務部門の枠を超え、経営企画やサステイナビリティー、IR、コーポレートレベルの投融資、グローバル企画、ブランディング・メッセージング、デザインなど、幅広い業務を管掌しています。とくに企業価値の向上をいちばんの目的として、低収益事業の改善からグローバルを含む成長事業の促進までメリハリをつけて関与しています。
25年度末までの中期経営計画を進めるために、各部署が密接に連携しています。財務戦略においては、成長に向けた投資を優先すべく、短期利益の最適化を目指しつつ、軽視されがちな長期利益の最大化に向けて、とくに中計で定めた成長領域を中心に資本を投入し、持続的な成長を実現しようと考えています」
藤川氏は、注力して取り組んでいる施策として「経営・ファイナンスプロセスの刷新」を挙げた。社内プロセスやルールを統一・標準化し、データを1つのデータプラットフォームに集約した結果、今まで見えなかった重要な情報が見えるようになったという。さらに、FP&A機能の強化への取り組みを紹介。新しいシステムを導入し、データ収集・分析、報告書作成、業績予測などを自動化することで、これらに費やす時間を削減する考えだ。
「業務の自動化により空いた時間は、ビジネスパートナーの立場で事業ラインとの関係構築に充てるようにしています。データを基に現状の課題を分析し、先々の改善に向けた施策を提案できる組織を目指しています。事業を理解し信頼を得て、一緒に事業推進できるように変わっていかないといけません。またこの変化を事業側に受け入れてもらえないと機能しないため、双方の意識を変えて、一緒に動かしていこうとしています」

永山 晴子氏(右)
次に、永山氏はNECが外部のステークホルダーから受ける企業価値向上に向けた期待や、その変化について尋ねた。
「ESG説明会では、とくにS(Social)に関する質問が多く、従業員や企業文化に向けた注目や期待はずっと続いています。G(Governance)に関しては、指名委員会等設置会社に移行し、社外取締役の比率が増えたことに対して投資家から好意的な反応がありました。
中長期的な議論が活発になったことなどが変化として挙げられますが、よりガバナンスが利く仕組みに変わったと投資家から受け取られたのでしょう。非財務情報については、ITベンダーとして、企業価値との関係性をデジタルに説明できるかということをつねに考えています」
最後に、永山氏は藤川氏がCFOとして大切にしていることは何かと問いかけた。藤川氏は「自らの知識や経験を次世代に『恩送り』することを大切にしている」と応えた。
「私は、これまでに自分が受けた恩を次の世代にできるだけ多くつなげようとしています。NECの成長を支えるために、私自身が障壁を取り除き、次の世代がスムーズに成長できるように環境を整えていきたい。それが、CFOとして意識していることです」
日本企業が持続的な成長を遂げるためには、既成概念を超えた革新と変革が求められている。「Finance Leaders Summit」で示された多様な視点と実践事例は、企業が自らの強みを再評価し、新たな価値を創造する道しるべとなるだろう。
このカンファレンスを通じて得られた知見とネットワークを武器に、各企業が独自の道を切り開きながらも、共に築いていく未来に期待したい。






