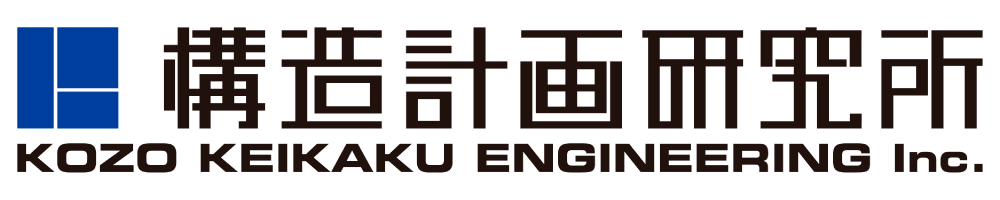工場の耐震補強「残された課題」を解決するカギ 「補強が困難な建物」への新しいアプローチとは

社会的要請が高まる地震対策で残された課題
「この10年間で、企業の地震対策は着実に進展していますが、その進捗は一様ではありません。補強が難しい建物は取り残されやすく、対応が滞っているケースがあるのです」と指摘するのは、製造業の工場などを中心に建物の地震対策を支援してきた構造計画研究所 エンジニアリング営業1部の守武祐子氏だ。
「まず取り組むべきは、従業員の命を守るための建物の耐震化だと考えています。とりわけ、旧耐震基準で建てられた古い建物の対策は最重要課題です。一方で、とくに製造業の工場に対しては『耐震補強が難しい建物がある』という声をよく耳にします。これが現在の大きな課題だと考えています」

構造計画研究所 エンジニアリング営業1部 企業防災チーム
なぜ、耐震補強が難しいのか。その主な理由は、「操業を止められない現場の事情」と「建物そのものの特性」が複雑に絡んでいるという点だ。
一般的な耐震補強の工事を行う際、生産ラインを一時的に移設しなくてはならない場合が多い。しかし、移設には多大な費用と時間がかかるだけでなく、収益の要である生産ラインを止めることは機会損失にもなる。その結果、現実的に移設が不可能になるケースも少なくないという。同部の児玉徹也氏は、工場特有の制約についてこう説明する。
「週末のみ工場の稼働を止め、長期にわたって段階的に補強を進める方法もありますが、多額の費用と長期間の工期を要するため、現実的ではありません。さらに、建物内に生産設備が密集している場合、補強部材を入れるためのスペースすら確保できないことがあります。経営判断において、リスクとコストを天秤にかけた結果、補強の優先順位が下がり、手を入れたくても入れられない状況が生じてしまうのです」

構造計画研究所 エンジニアリング営業1部 企業防災チームリーダー
経営者にとっては難しい判断だが、耐震補強は社会的責任として求められているだけではない。震災時にもし自社だけ操業が止まれば、取引機会の消失という重大なビジネス損失につながりかねない。
「とくに製造業はサプライチェーンの上流企業からの要請が強く、その対応に苦慮されているのではないでしょうか」(児玉氏)
工場の地震対策、その新しいアプローチとは
収益の維持と安全策の強化。そのバランスを図らなければならない経営者にとって、耐震補強は重い判断を伴う施策となる。こうしたジレンマに対して、技術の進化が現実的な選択肢をもたらしていると児玉氏は話す。
「近年のコンピューター性能の飛躍的な向上と地震研究の進展によって、建物の地震対策の分野は大きく進化しています。その結果、複雑な地震応答や構造解析のシミュレーションが高精度に行えるようになりました。地震の揺れが地盤を伝わり、建物に影響を及ぼすまでの一連の挙動を可視化・解析することで、適切な補強方法を、より精緻かつ合理的に検討できるようになってきたのです」
代表的な手法は、地震の揺れを和らげるオイルダンパーを用いた制震補強だ。「建物外周部や柱と柱の間にオイルダンパーを設置し、揺れのエネルギーを吸収することで、建物全体が受ける地震力を低減できるのです。これは、従来の耐震補強のように屋内の鉄骨部材やコンクリート壁を増やし、建物全体を堅く・強くする手法とは異なるアプローチです。建物の外部の工事となるため、設備移設や操業停止を抑えられるメリットがあります」(児玉氏)。
「シミュレーションの精度向上によって、補強すべき箇所を選択することが可能になったことが大きい」と語るのは同部の古川欽也氏だ。従来はすべての柱や壁を均等に強化する方法が一般的だったが、建物全体の挙動をシミュレーションすることで、局所的に補強しても耐震の性能を満たせるアプローチが可能になったという。
「耐震性の指標として広く用いられているのが、建物の強さと粘りを示す『Is値』です。大規模な地震の際、Is値0.6以上は倒壊や崩壊の危険性が低く、Is値0.3未満は危険性が高いとされています。この基準は優れた考え方ですが、鉄筋コンクリート造の建物と構造特性が異なる鉄骨工場などの建物に適用する場合、Is値による指標を用いた補強がベストとならないケースがあります。また当然ですが、1981年以降に設計された新耐震の建物には適用できません」

構造計画研究所 エンジニアリング営業1部 企業防災チーム営業担当部長
Is値だけでは捉えきれないリスクに対し、構造計画研究所では、地震工学や構造解析の専門知識を生かしたシミュレーション技術による耐震性の評価・補強提案を実施している。「設定した地震シナリオに対して建物が壊れるかどうか、という二者択一的な地震対策をするのではなく、どのような規模の地震から、何を守りたいのか。人の命なのか、事業の中断も防ぎたいのかといった目標を明らかにし、シミュレーション技術によってその目標を達成するための検討を重ね、最も費用対効果の高い地震対策のベストソリューションを見いだしていきます」(古川氏)。
経営層の判断材料となった「補強効果の見える化」
構造計画研究所が制震補強設計を担った自動車関連部品メーカーでは、旧耐震基準の生産棟に制震補強を導入。外付けオイルダンパーを採用することで、操業を止めずに施工が可能になり、コストや工期、設備移設の負担を大幅に抑えることができたという。古川氏は、次のように補足する。
「いくら地震対策だからといって、その間工場の操業を止めてもらうわけにはいきません。今回は、外付けオイルダンパーによる制震補強を採用していただくことで、工場の操業を止めることなく対策を実行することができました。単に『工期やコストを縮減できればいい』というものではなく、お客様のBCP(事業継続計画)での地震被害の低減目標も満たさなくてはなりませんが、この方法によってどちらもクリアすることができました」
Is値の指標だけに依存せず、被害の程度を定量的に捉えるアプローチは、企業の意思決定に新しい選択肢を提供しているようだ。
中には、何から手をつければよいかわからない企業も少なくないだろう。「約60棟の施設を保有する資材メーカーでは、どの建物から地震対策を講じるべきか、その判断材料がない状況にありました。そこで私どもに相談があり、地震対策の優先度評価と建物挙動のシミュレーションを実施。3Dアニメーションによる可視化は、経営層の直感的な理解を促し、迅速な社内決裁につながりました。結果として複数拠点で計4棟の耐震補強工事を決断され、工場の稼働を止めることなく、工期どおりに完了しました」(児玉氏)。
構造計画研究所のシミュレーションによる設計検討では、数十パターンを試し、コスト・工期・性能のバランスを検証しながら、現実的な解に収束させていく。だからこそ、工場を止められない企業にとって納得感のある補強案を提示できるのだと児玉氏は語る。
「耐震だけでなく、耐震と制震を組み合わせる選択肢や、場合によっては緊急避難場所となるシェルター設置といった暫定策まで含めて幅広い選択肢を示すことで、地震対策に踏み出せない企業に『できる方法』を提示しています」

さらに、地震発生直後の建物の安全性を判断するため、シミュレーション技術を基盤としたモニタリングシステムも提供している。地震時にセンサーで捉えた数値から、建物の変形や損傷度をクラウド上で評価し、建物への立ち入り可否判断を支援する。建物のダメージや倒壊リスクを判断できる専門家がいない現場でも、迅速な対応を可能にする仕組みとして導入が進んでいるという。
「技術の進化は、これまで『耐震補強が難しかった建物』にも、新たな選択肢を差し出すことを可能にしているのです」と児玉氏は強調する。建物の地震対策、その新しいアプローチへの関心が高まっていくことだろう。