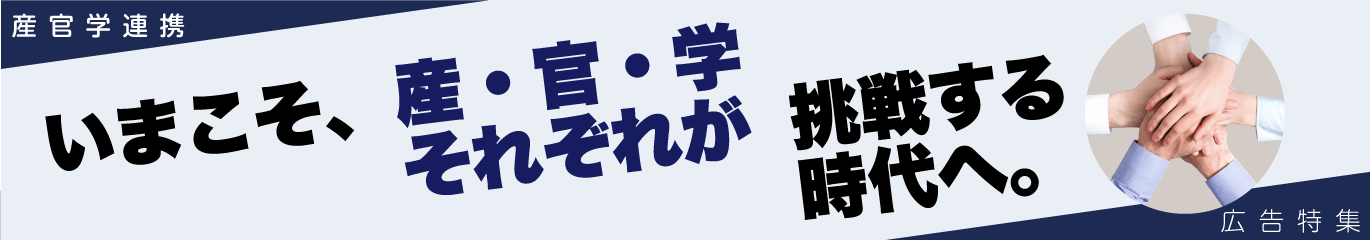「形」にとらわれず、
ポテンシャルのあるビジネスにチャレンジを。
日本で産学官連携の成功モデルを生み出すためには
―― 「産官学連携」という言葉が一般化しつつあるように思います。認知が進むまでには、どのような経緯があったのでしょうか。
原山 産官学連携の取り組みが広まった一つのきっかけは、1990年代後半、大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する技術移転機関(Technology Licensing Organization:TLO)の仕組み(大学等技術移転促進法:1998年施行)が生まれたことです。
実はそれまでにも、大学の研究者が個人的に企業と付き合う例はありました。企業によっては「今さら産官学連携と言われなくても、わが社は昔から大学と共同研究をやっている」と言うところもあるでしょう。
最近になり、産官学連携が加速した背景には、ビジネスにスピードが要求される中で、自社に閉じた枠の中では、新たなビジネスモデルを創出することが難しくなっていることも挙げられます。未来志向とも言うべき、新しい方向に向かうツールとして、大学が一つの候補になっているわけです。
―― 「大学発ベンチャー」の事例を聞くことも増えています。ただ、産官学連携により生まれた成功事例はまだ少ないようです。

原山 優子
1996年 ジュネーブ大学教育学博士課程修了、1997年ジュネーブ大学経済学博士課程修了後、ジュネーブ大学経済学部助教授、経済産業研究所研究員を経て、2002年より東北大学大学院工学研究科教授に就任。 2010年から2年間、経済協力開発機構(OECD)の科学技術産業局次長を務める。2013年3月に東北大学名誉教授、総合科学技術会議(現・総合科学技術・イノベーション会議)常勤議員に就任
原山 確かに、欧米、とくに米国に比べて、日本では産官学連携により生まれたビジネスの件数は少ないとも言われます。
理由として、日本ではどうしても『形』から入りがちという点があります。たとえば企業においては、可能性はあっても不確かなものにはなかなか投資しない傾向があります。大学では、前述したTLOのほか、知財本部や産学連携本部をつくるといったように、まず形を整えることからスタートするケースが多く見られました。また政府や地方自治体も、産業クラスター政策などの枠組みを利用した取り組みを進めてきたのです。
もちろん、形をつくれば産官学連携が進むというものでもありません。企業からは、これまで独自に行ってきた大学との共同研究との整合性が取れず、使い勝手が悪いといった声もありました。しかし現在は、これらの形から始まったルールの課題を改善しながら、徐々に成果を生みつつある段階と言えます。
企業と大学をつなぐ人材の育成が急務に
―― 米国では、研究者がベンチャーキャピタルなどを相手にプレゼンテーションをし、事業化を促進する場を設けている大学もあると聞きました。最近の動向は。
原山 「エレベーターピッチ(エレベーターに乗り合わせたわずかの時間に自分のプロジェクトを売り込むこと)」といった言葉もあるように、米国では、大学の研究者もベンチャーキャピタリストなどの投資家に活発に提案を行っています。ただし、早期の事業化が見込めるというメリットはあるものの、その弊害も指摘されています。
と言うのは、ベンチャーキャピタルはどうしても「投資がどれくらいの期間で回収できるか」を重視しがちだからです。それだと、販路が確保されており、一定の市場が見込めるものでないと選ばれません。未知数だがポテンシャルはあるといった技術は事業化されにくいのです。ただし「エンジェルとして、若い研究者を育てる」といったスタイルの投資家も増えてきているのは、好ましいと感じています。