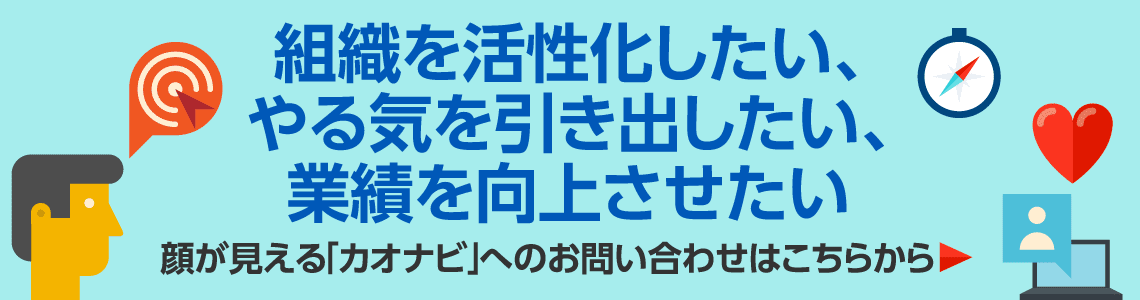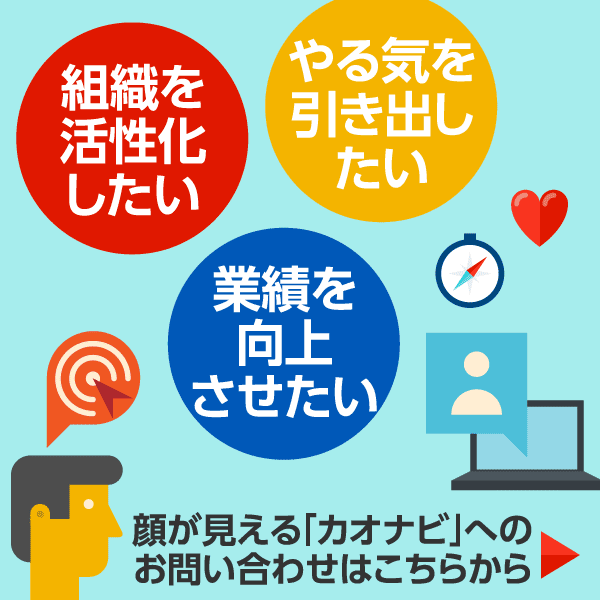なぜ顔を覚えると組織が活性化するのか? 脳科学者が解き明かすビジネスメリット

(なかの・のぶこ)
1998年東京大学工学部応用化学科卒業。同大学院工学系研究科を経て、2004年東京大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程修了、2008年東京大学大学院医学系研究科脳神経専攻博士課程修了。「高次聴覚認知における知覚的範疇化の神経機構 : fMRI・TMSによる複合的検討」で医学博士。2008年から2010年まで、フランス国立研究所ニューロスピン博士研究員。2015年4月から東日本国際大学教授。脳や心理学に関する独自の研究を進行中。
柳橋 例えば、街で偶然会った人が、顔はわかるけれど、名前がなかなか出てこない場合がありますね。逆に言えば、名前が出てくるけれど、顔が思い浮かばないということはほぼありません。ということは、人間というのは、顔をキーとして認識しているのでしょうか。
中野 そうです。さらに言えば、「エピソード記憶」の場合、「感情を伴うこと」がポイントになってきます。記憶をつくる「海馬」のすぐ近くに「扁桃体」という情動を生む神経細胞があります。「この人と会って不快だった」「この人と会ってうれしかった」という扁桃体によってつくられた感情と一緒に「エピソード記憶」は記憶されます。感情をともなうことで記憶を呼び起こしやすくなるという効果があるのです。
その際、キーとなるのが顔、それも表情です。人間は普通のフラットな顔より、笑ったりしたときの表情で顔を覚えています。頬が上がって、目じりがちょっと下がっているような笑顔に人間は安心感と信頼を覚え、その反対に、眉が吊り上ったような顔には距離感を感じると言われています。
顔が見えることで「近接性の効果」が生じ
業績アップにもつながる
柳橋 私たちのサービスを利用するユーザー企業からは、営業部全員やプロジェクトメンバー全員の顔写真が“一覧”で出ているから、人材配置などがイメージしやすくなったという声もあります。
企業では、組織が大きくなると、誰がどこにいて、何が得意なのかがわかりにくくなります。そのため、企業では「人材の可視化」ということが今叫ばれています。実はその可視化の一端として、顔写真を一覧で並べることによって、少なくとも感覚として組織の特徴が見えてくるのではないかということを期待しています。
中野 組織が大きくなるとある弱点が発生します。小さな集団であれば、一人ひとりを知ることで充分人材の可視化ができます。ところが、集団が階層構造になっていく、つまり、いくつかの営業チームが集まって営業本部となるような「集団の集団」という状態になっていくと、一人ひとりのことを知ることが難しくなります。
そのことが、「集団同士の協力行動」に実は大きなマイナスの影響を及ぼします。人間は大きな集団というものを認知しにくい性質を持っているので、ついつい自分のいる部署のことだけを考えてしまうのです。
ビジネスでは、組織の力を発揮するために多くの人が協力することが必要です。企業のトップが精神論的なメッセージやスローガンをよく掲げるのは、実は集団の中の一人であることを認識させ、社内のグループ同士が争わないようにするための“無意識”の工夫でもあるのです。
科学的には、ここで勝たなければいけないというときに、組織内で内輪揉めをしてしまうことを、「メソn人協力」ができていない状態と言います。組織を活性化するためには、この「メソn人協力」を意識的にする必要があるのです。顔が見えることは、「メソn人協力」をしやすくする効果があるように思います。
柳橋 例えば、トップが普段から私たちのツールを使って社員の顔写真を見ていれば、社員に共感をもつようになり、より働きやすい環境になるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
中野 専門的には、それを「近接性の効果」といいます。顔を見ていることによって、好感度が上がる現象です。それは愛着を形成するホルモンである「オキシトシン」が媒介する現象であり、仲間意識が生まれやすくなるのですね。それによって組織の一体感が増せば、業績の向上も期待できます。