特別対談前編・日本が進むべき「今後30年への道」 「すり合わせ型」で成長する日本の製造業の未来

さまざまな危機や事象は課題を説くための「連立方程式」
小宮山 現代は、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代であるとよく言われます。確かに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに続いて、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻に伴う深刻なエネルギー高・資源高が起こるなど、予期せぬ事態に次々と見舞われ、世界情勢は混迷を極めています。
しかし、われわれ人類が2050年という未来を見据えたとき、解決しなければならない本質的な課題は、実は変わっていません。
藤本 未来予想は、いまや大きな連立方程式を解くように複雑化していますから、式や変数が1つ加わるだけで解はどんどん変わります。ただし、小宮山さんがおっしゃるとおり、方程式の骨格、つまり本質的な課題は変わらないと私も思います。
小宮山 私は以前から、「有限の地球」「社会の高齢化」「知識の爆発」の3つが、人類が直面している本質的課題だと考えていました。
地球は有限であるにもかかわらず人類のあらゆる活動が拡大し続け、その活動規模に比して地球が小さくなってしまった。また、食の安定と医療の高度化を背景に人類の長寿化が進み、世界人口全体が高齢化しつつあります。さらに、人類の有する知識が爆発的に増大した結果、領域の細分化が起こり、蓄積された知識が十分に活用されていません。
藤本 最近の日本を見ていると、過去の蓄積を捨て、新しい要素を取り入れることだけが課題解決だと、誤解されているフシがありますよね。DX(デジタルトランスフォーメーション)やIoTなど、新しいワードにすぐ飛びついて、はやりものにしてしまう。メディアの論調もそれをあおっているところがある気がします。

小宮山 2007年に『「課題先進国」日本』(中央公論新社)という本を書いたとき、すでに日本は少子高齢化・人口減少を始め、世界に先駆けて多くの課題に直面していました。それを前向きに捉え、活力ある長寿社会、環境や資源の制約を克服できる社会の実現など、「課題解決先進国」を目指すべきだと提唱してきました。あれから実に15年が経過しましたが、長寿社会に向けた取り組みにしても、あるいは脱炭素や再生可能エネルギーの活用にしても、日本の変革の歩みはあまりに遅い。目先の新しい問題が登場するたびに右往左往しています。
藤本 目先の問題に右往左往しないためにも、つねに本質的な長期課題群を相互依存的な体系として意識しておく必要があります。先ほど申し上げたように、私はそれらを、巨大な「連立方程式」と捉えています。
ウクライナ侵攻以降、世界のエネルギー問題の構図がガラッと変わりました。連立方程式において、1つの式、1つの変数が加わるだけで、方程式の解がすべて変わってしまうのはよくあることです。しかし、本質的な課題設定は変わっていないのですから、新たな要素が1つ加わったらまた解き直せばいい。解き直し続ける意志が大切で、つねに原点回帰しながら進化するわけです。
小宮山 それができない日本は、社会を変革する力が弱まっていると痛感します。変化に対する抵抗力も海外に比べて強い気がしますね。個人的には、年配者が依然として意思決定に深く関わっていて威張りすぎている、というのも大きな理由だと思っていますが(笑)。それだけでなく、日本では企業も政府も目先の問題を解くことだけに注力してしまっている。これも大きな社会変革が起こりにくい要因でしょう。
藤本 はやりものに対して、上が「とにかく導入して、頑張って成果を出せ」と言うだけだと、現場は大抵「部分最適」に走ります。製造業の現場なら、とりあえず目の前にある1台の機械の稼働率アップにIoTなどを使えば怒られない。しかし、付加価値の流れの全体を見る「ものづくり」現場のリーダーは、「全体最適」でプロセス全体の課題解決の道を探るべきでしょう。
小宮山 変化できないというより、課題解決の捉え方や戦略が誤っているということですね。
藤本 はい。例えば、既存のものづくりの強みを否定するような意味合いで「モノからコトへ」と言われることがありますが、本質的には正しくありません。そもそも「モノ」を操作しなければ「コト」は生まれません。正確には「モノからコトを」です。つまり、よいモノ(競争優位製品)からよいコト(顧客本位のソリューション)を生み出すのが重要なのであって、ものづくりを捨ててサービスに走るのではありません。
日本でも先進的なソリューションビジネス企業は、過去に蓄積してきた足元のモノ系のリソース、例えば自社製品の設置台数シェアや顧客信頼関係を出発点として、それを顧客企業とのデータ共有など、コト系のソリューションビジネスにつなげています。ものづくりは古いからはやりのコトづくりへ、という意味での「モノからコトへ」は、強みを活かし弱みを補う戦略論の基本を忘れた言葉遊びに聞こえます。
日本の製造業は衰退どころか付加価値が増えている
小宮山 これから数十年単位で未来を考えるとき、当然ながらデジタル化は外せない要素です。しかし今の日本では、何でもデジタル化に結び付けすぎるきらいがあります。まずは、今後も揺らぐことのない日本の強みをしっかりと見極めることが先決でしょう。
私の専門領域は化学システム工学ですが、日本の化学産業にはその強みが集約されていると常々感じていました。半導体の基板に回路を刻むうえで欠かせないレジスト(感光剤)や素子を保護する封止材などは、いずれも日本メーカー数社で世界シェアの100%近くを占めています。一つひとつの市場規模は決して大きくありませんが、いずれも分子の設計や粒子の配合、塗布工程に至るまで、膨大な技術の蓄積と高度な「すり合わせ」が必要です。要するに、市場規模に比して大変難しい世界なので、容易には参入できません。こうした化学産業の市場を合計すると、自動車産業に次ぐほどになっています。こういう分野が、今後も着実に生き残っていくと思うのです。
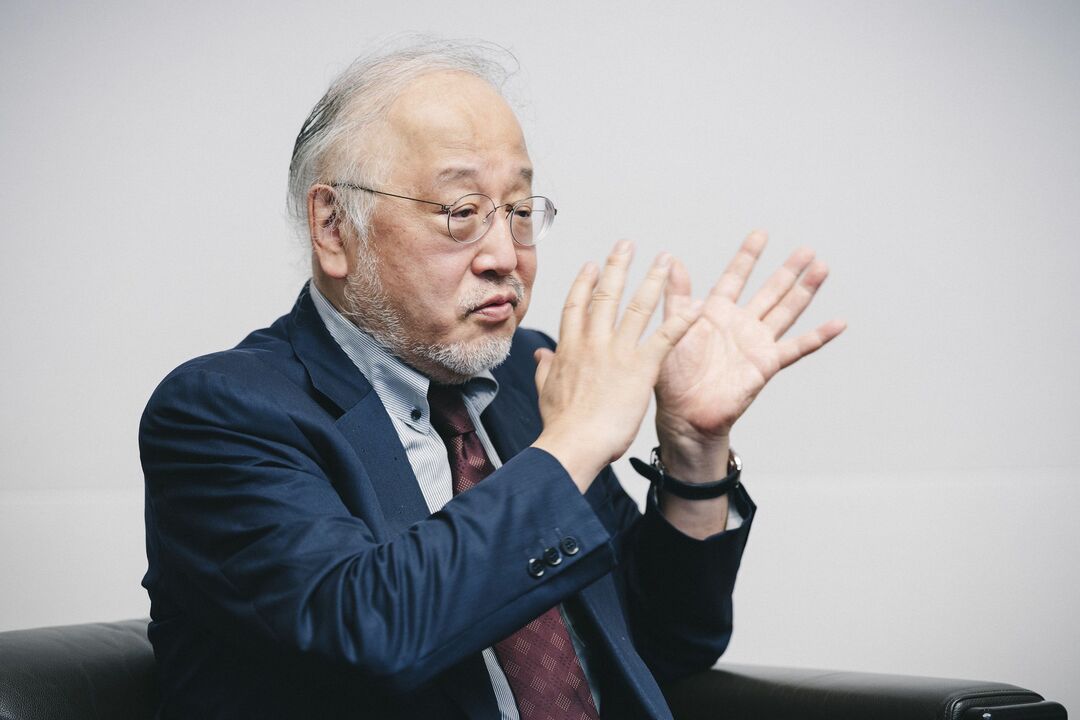
藤本 まったくそのとおりですね。「日本の製造業は衰退した」という論調がよく見られますが、実証的にも理論的にも間違いですね。冷戦終結後のこの30年間、厳しい国際競争下で地道に能力構築を続けたのが国内製造業です。1990年代には日本と中国との間に、約20倍もの賃金差、つまり巨大なハンディキャップがありましたが、現時点においても日本の製造業はGDP(国内総生産)の20%程度を生み出しています。国内製造業がこの比率で残っている国は、G7では日本とドイツだけです。確かに企業数を見ると約半数に減ってしまいましたが、付加価値はむしろ増えている。この30年間で、国内製造業全体の実質付加価値額は、80兆円台から約110兆円前後まで伸びているのです。
小宮山 低成長ではあるけれど、衰退だなんてとんでもないですね。
藤本 それは日本が「設計の比較優位」産業を維持したからで、その多くは、理事長もおっしゃった「すり合わせ」型産業です。
製品にはそれぞれアーキテクチャー(設計思想)があり、機能要素と構造要素が絡み合った調整集約的な「インテグラル(すり合わせ)型」と、機能と構造の関係が一対一でシンプルに対応する調整節約的な「モジュラー(組み合わせ)型」がその2大類型です。そして、戦後日本の製造業が強かったのは主に前者でした。製品機能と製品構造の間の複雑な設計調整を、部門横断的に行う必要がある。高機能型自動車を筆頭に、機能性化学品や高性能な産業機械など、日本の輸出製品の大半がそうです。調整能力の高い日本の産業現場がそれを支えてきました。
要するに、複雑な設計の人工物を、複雑な流れで、調整型の現場でつくる。他国の現場が「面倒くさい、もう日本に任せるよ」と言ってくるような製品を得意技にするのです。
小宮山 日本の現場の調整力を支えている要素としては、独自の信頼関係を築いていることも挙げられます。
最近発表された米国の研究者の論文で、「High-Impact Coalition(社会的に影響力を持つ人たちの連合体)」という組織形態を提言していました。人種問題のような複雑な社会課題の解決において、企業が主導的な役割を果たそうとするとき、企業・政府・NGOなどが垣根を越えて協力し、それぞれの知見を提供し合って課題を解決していく組織形態が望ましいというのです。うまく機能するための条件がいくつか示されているのですが、興味深いと思ったのは、契約や金銭的なインセンティブではなく、「信頼」を重視している点でした。メンバー間の信頼感が醸成されるスピードに応じて、プロセスを進めていくことが重要だと。これは、長年われわれがものづくりの現場で大切にしてきたことと近しい考え方だと思いませんか。
藤本 まったく同感です。戦後日本の産業現場では、高度成長期の慢性的な人手不足もあって、長期雇用・長期取引が定着し、そこでは、作業者間・取引企業間の信頼関係や、多能工のチームワークの発達は必然でした。それが日本の産業競争力を支えてきたのは間違いありません。その価値が今になって海外の研究者の間で改めて注目されているのは、確かに興味深いですね。(後編に続く)
※この対談は再構成のうえ、『フロネシス23号 2050年、社会課題の論点』(東洋経済新報社刊)にも収録されています。





