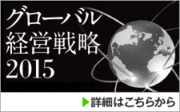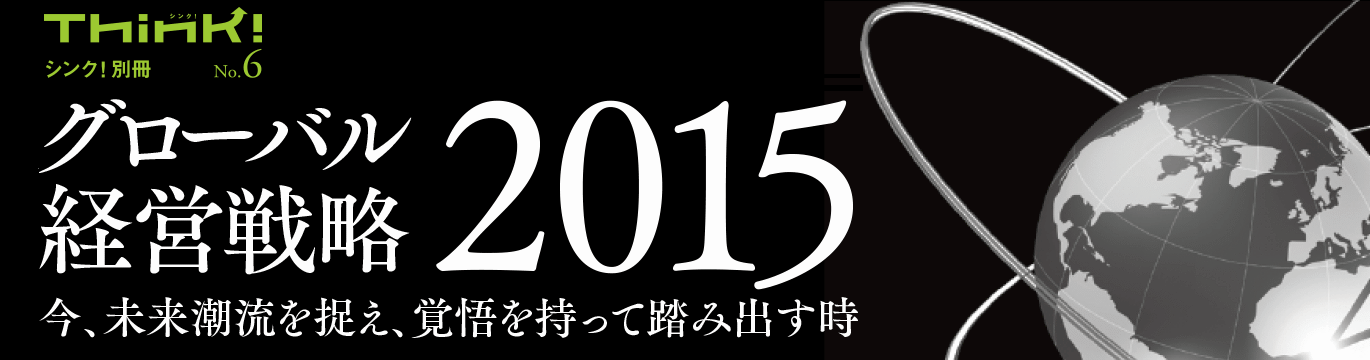メタトレンドとグローバル経営戦略 松尾 淳(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)
日本企業の歩みと未来に向けた新たなる一歩

医薬・医療機器等を中心としたライフサイエンス業界に対して、M&A 戦略立案・シナジーの定量化、ポストM&Aにおける実行支援、サプライチェーンを中心としたプロセス改革、IT 戦略立案、マーケティング戦略立案、海外事業戦略の策定・実行支援などのプロジェクトを数多く手掛けている。Consumer & Industrial Products Division共同リーダー。(photo: Hideji Umetani)
日本企業のこれまでの歩みは決して平坦なものではなかった。日本国は大戦後の廃墟から、戦争特需などによって復興を果たし、1955年から1973年までの高度成長期には年平均10%以上の成長を遂げ、経済先進国へと飛躍した。それを牽引した日本企業は、製造業を中心に力をつけ、その後のオイルショックや通貨切り上げなどを経験しながらも、絶え間ない改善や研究開発を続け、1980年前後には「Japan as No.1」との称賛を世界から受けた。もちろん、この背景にはメインバンクを中心とした安定的な金融システムが日本企業の成長を支え続けたことを忘れてはいけない。しかし、1985年のプラザ合意後からの円高不況、それを乗り越えるための過剰流動性からバブル崩壊への一連の流れでつまずくと、様相は一変。「失われた20年」と呼ばれる長い低迷期へと突入する。かつて世界のお手本であった日本企業は、称賛されたがゆえの驕りも多少あったのか、それまでのあり方、やり方をなかなか変えることができず、兆しが見え始めていたグローバリゼーションへの対応が後手に回った。その間に、大きな環境変化に気づき、それにいち早く対処した欧米系のグローバル企業のみならず、存在感を増してきた新興国を出自とする新たな企業群にも押され、その自信は崩れ去り、立ちすくむ状況が続いてきた。
実際には、自動車産業のように世界で戦えている産業もあれば、素材産業のように目立たないものの技術力を活かして一定のプレゼンスを示しているところもある。つい最近までを振り返ると、このような歩みだったのではないだろうか。
だが今、日本企業にもようやく変化の兆しが見え始めた。具体的な効果が見えない「アベノミクス」ではあるが、意識を改めるきっかけとなり、グローバル化への対応を進め、攻勢に向けた素地を整え始めている。
では、そのような日本企業が未来を明るいものにするためには何が必要か。その答えの1つが、未来の潮流、すなわち「メタトレンド」を読み、能動的に変化を生み出していくことだと考える。移り変わる環境に臨機応変に対応する柔軟性も重要であるが、変化が激しいグローバル環境下だからこそ、これから先の大きなうねりを見据え、経営の軸を定めなければならない。そして、他社に先んじて「次の一歩」を踏み出し、自らが新たな流れをつくり出すことができれば、グローバル競争下において圧倒的なポジションを確立する可能性が高まるだろう。
メタトレンドから理解する事業環境への影響要因
メタトレンドを読み解き、長期的な企業の方向性を決め、経営戦略を策定することは何も特別なことではない。むしろ、持続的に成長しているグローバル企業では「当たり前」といえる。
このメタトレンドをどのように捉えるかは一様でなく、正解があるわけでもない。しかし、何か手掛かりがないことには整理のしようもない。そこで、事業環境に影響を与えうるトレンドを分析するためのデロイトのフレームワークを解説したい。
メタトレンドは、「経済」「グローバル化と地政学」「社会と人口動態」「自然と資源」「規制と政策」「技術とイノベーション」の6つに大分され、これらのカテゴリーに全62のトレンドが含まれる(図表1)。いずれも幅広い業界に影響を及ぼすトレンドであり、新たなビジネス・アイディアの源泉となるものである。
メタトレンド1:経済
マクロ経済の観点からは、政府や中央銀行の度重なる介入にもかかわらず、リーマンショックに端を発する世界的に不安定な金融情勢に収束の兆しが見られないことによる「金融不安」が挙げられている。また、BRICs諸国は引き続き成長を牽引するものの、近い将来、成長スピードが減速する可能性もあることから、それに続く2番手の新興国の台頭による「経済力」の変化がトレンドとして注目されている。新興国に対する外国直接投資の増加により、かつては一極集中型だった経済力が世界に分散しつつある。この傾向は今後も続くと予想され、新興国の経済成長には目を見張るものがあるが、参入にあたっては事業リスクを十分に検討すべきだろう(図表2)。