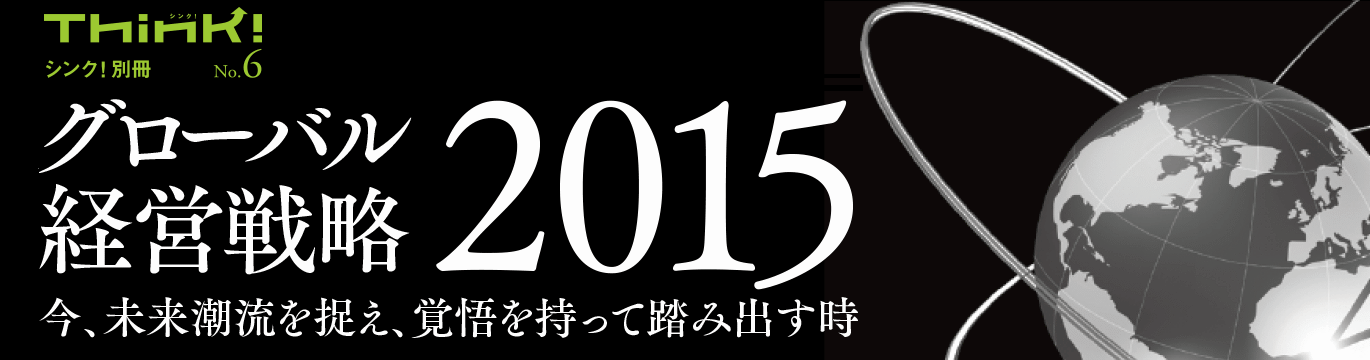[巻頭対談]
日本の産業の実力と競争力復活のカギ
伊藤 洋一(経済評論家)
×近藤 聡(デロイト トーマツ コンサルティング 代表取締役社長
パートナー)
全体がワークしていれば、個々の危機は問題ではない
近藤 危機意識という点は、トップだけの問題ではないようです。若手ビジネスパーソンと直接会って話していると、彼らも不安は持っているけれど、危機意識とか、社会に対する問題意識とかはあまり持っていないように感じます。
伊藤 それは彼らが守られているからでしょう。一人っ子か、せいぜい2人兄弟だから、親の財産ももらえる。
近藤 もう少し危機が深刻化すれば、彼らの考え方も変わるでしょうね。
伊藤 実際、すでに危機は至る所で起こり始めています。パナソニックでもリストラが行われ、シャープも倒産の危機にさらされた。でも、個々の企業の危機は起こっても構わないと思います。私が「ソニーが潰れて何が悪いの」と言ったら「世界中の放送局が困る」と言った人がいます。放送用のカメラは世界中でソニー製が使われているからというのがその理由ですが、別にキヤノンでもいいじゃないですか。個別の企業で危機が現実になっても、社会がトータルでワークしていればいいのです。
近藤 パナソニックやシャープを辞めた技術者がアイリスオーヤマに入社して、開発しているという話もありますね。
伊藤 そういう動きには、大賛成です。リストラに遭った社員は新天地で死に物狂いで働くでしょうし、アイリスオーヤマがこれから大躍進するかもしれません。
近藤 こうした人材を、きちんと日本企業で吸収できる仕組みが必要ですね。
伊藤 そう。でないと、皆、韓国や中国に流出してしまう。ウイークエンドアルバイターといって、週末になるとソウルで働く人が増えた結果、日本の技術が流出したわけです。遅かれ早かれ流出したかもしれませんが、技術を持った人を国内にとどめておけないのはもったいない。でも今ベンチャー企業が少しずつ出てきているみたいですから、そういうところで吸収していけるといいと思います。
国の役割と限界
近藤 日本社会全体がワークする、そういう仕組みをつくるためには、やはり国の役割が大きいと思うのですが、いかがでしょうか。
伊藤 その点について私は否定的です。私は、国の産業政策というのは必ず間違えると考えています。それまで紡織機械をつくっていたトヨタが自動車をつくりたいと言ったとき、官庁の役人は何と言ったと思いますか。「お前のところはやめろ」と言ったのです。だいたい、役人というのは2~ 3年ごとに変わるわけですから、産業を見る目なんてありません。
それでも、昔の役人には、まだ力がありました。なぜなら彼らは外貨のない時代に海外に行って、海外の産業から学んでいたからです。でも、今は誰でもインターネットで、米国の産業がどうなっているかなんて、いくらでも見られるわけじゃないですか。だから私は官庁の知り合いに「君たちの役割は終わった」と言ってるんです。
ただ、本当の目利きが「この会社を応援したい」と言ったときに、お金を出せるようなシステムは必要でしょうね。
近藤 国の役割でいうと、安倍首相の経済政策でも「三本目の矢」が出てきません。産業を興したり、競争力を高めたりしていくために、楽天の三木谷浩史さんたちが審議会などで話し合って、ネットでの医薬品販売を解禁する話なども出てきてはいるのですが、なかなか進んでいないように思います。とはいえ、これまで数々あった成長戦略の多くが道半ばで終わってしまったため成果に結びつかなかったという面もあるので、安倍政権の「実行しきる力」には期待しています。
また、企業側も、政策立案や制度設計といった国にしか担えない部分をうまく活用する意識で行動していかないといけない場面も出てくるのではと考えています。
「目利き」の創出が日本復活のカギを握る
近藤 ここまで、モノづくり、経営、国の役割など、いろいろと伊藤さんのお話を聞いていると、もう打ち手がなくなっているような感覚になるのですが(笑)。
伊藤 そんなことないですよ。山ほどできることがあるのに、手がつけられていないだけです。たとえばパナソニックは自動車や住宅に重心をシフトして、うまく方向転換したと思いますが、業界を超えて車と家とスマホをループさせることができたら、ものすごい可能性を秘めていると思います。デジタル革命は、まだ始まったばかりです。
近藤 ほかにも可能性のある領域として挙げるとしたら、どんな産業がありますか。
伊藤 サービス産業に注目しています。2013年に日本に来た外国人は1036万人で、今年は計算すると、だいたい1250万人くらいになるようです。いずれ2000万人も夢ではないでしょう。
日本は国土に緑があふれていて、温泉があって、食べ物が安全で、セキュリティがよくて、歴史があって、景観も素晴らしい。フランスに負けない観光地になる可能性があると思います。今年5月の旅行収支が1970年以来初めてプラスになりましたが、1970年といえば私が社会人になる前のことで、1ドル360円でしたから、外国に行ける人も少なかった頃です。それはプラスになるでしょう。でも、今のような1ドル100円前後で、誰でも外貨をいくらでも買える時代に旅行収支が黒字になるというのは、実はすごいことです。
ですからサービス産業に期待しているのですが、生産性が低いといわれるこの産業でどういう改革ができるかが1つのポイントだと思っています。
近藤 海外から来る外国人の数は増えていますが、日本の人口に目を向けると、少子高齢化という大きな問題がありますね。
伊藤 その点は、「日本は世界で最初に人口が減少する、実験場だ」と捉えることもできます。日本でこれから起こることは、世界のほとんどの国でもいずれ起こるのです。それを見越してGEは、日野市に巨大な医療研究センターをつくりました。昔は福島で原発を建てていた企業が、今は同じ日本で老人向けのCTC(CT Colonography:大腸がんの診断法)などを研究・開発しているのです。なぜなら、世界に先駆けて高齢化が進む日本で売れる製品は、やがてほかの国でも必ず売れるからです。
近藤 高齢化をリスクやネガティブな要因とせず、ビジネスチャンスとして捉えるのですね。
伊藤 商売とは、そういうことだと思います。日本の企業で見ても、ユニ・チャームなどは元気ですよね。だからソニーがオリンパスに資本参加したときには、やっといい投資先を見つけたなと思いました。これから世界的に高齢化が進み、医療機器は、国の予算が潤沢に出る成長産業となるのですから。
近藤 まだまだ日本には、やれることが山ほどある、と。
伊藤 ただ、それに加えて、もっと社会全体で産業や企業を見る目を養う必要があると思います。評価される企業が生き延びることが重要です。いずれそうなると思いますが、今の日本の株式市場はいい加減なんですよ。目利きができてない。
たとえばロボット産業も日本では有望だといわれています。でも、福島第一原発のなかに入れたのは、フランスと米国のロボットで、日本のロボットは入れなかった。皆さん、日本のロボットといえば「ソニーだ」「ホンダだ」と言うけれど、アイボもアシモも踊っているだけでは駄目なんです。
一方でこの前、東京大学のロボットベンチャーがGoogleに買われました。私は以前、その会社を取材したことがあるのですが、すごい技術を持っていました。なのに、Googleに買われて初めて、日本で「あの会社ってそんなにすごかったんだ」という認識が広がったのですから、これは大変悔しい出来事です。
近藤 日本の大学ベンチャーが外国企業に買われたり、あるいは日本人研究者が米国に活躍の場を求めるということは、技術や頭脳の流出という点で大きな問題です。企業だけでなく政府や大学も巻き込んで、先を見越した戦略を考えていく必要があるでしょう。そのためには、日本としてのモノの見方や情報の取り方というある種のインテリジェンスを、国として、あるいは個人として磨いていくことがこれからの時代では重要です。
伊藤さんは、街を歩いて経済の最先端に触れた上で、それを統計で確認し、さまざまな発信活動で実際に使っていらっしゃる。日本人が未来に向けて持つべきビヘイビアを実践されているように思います。もっと目利きができるようになる必要がありますね。
伊藤 日本にも有望な種はあるのだから、政府、投資家、そして経営者が見る目を養い、それに気づかなければいけない。そうでなければ、日本の産業力は復活しないでしょう。
(photo: Hideji Umetani)