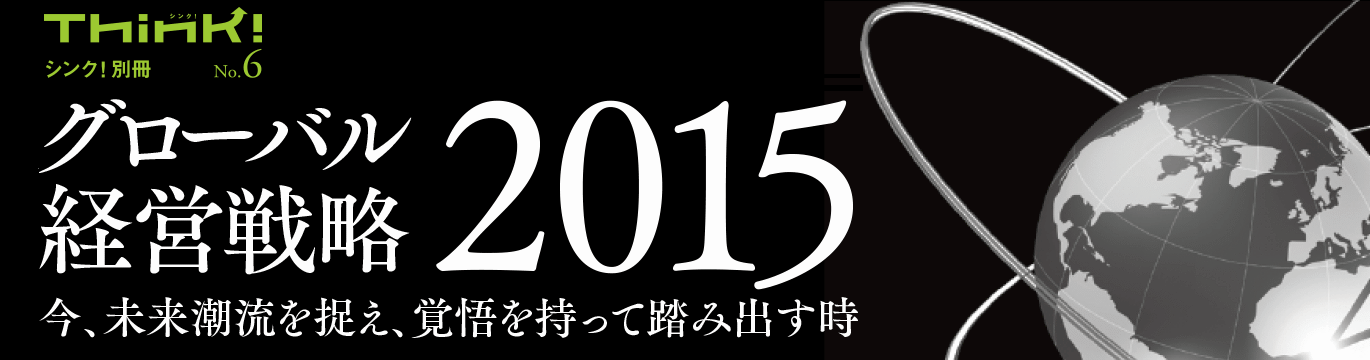[巻頭対談]
日本の産業の実力と競争力復活のカギ
伊藤 洋一(経済評論家)
×近藤 聡(デロイト トーマツ コンサルティング 代表取締役社長
パートナー)

日本企業が抱える問題点と、産業力を復活させるカギについて考える。
日本の産業力の強みと弱み
近藤 聡(以下、近藤) 伊藤さんは、三菱航空機のジェット機「MRJ」に乗ってリポートをされたり、電気自動車を真っ先に買われたり、ご自身で日本の製造業の最前線を体感なさっていますね。その実体験から、素材を含めて技術はあるものの論調としてはネガティブな現在の日本の産業について、どのように感じていらっしゃいますか。
伊藤 洋一(以下、伊藤) 日本の「モノをつくる技術」は、以前と比べて何ひとつ衰えていないと思います。たとえば部品産業を見ても、日本の優位性は今もかなりあります。ボーイングもアップルもサムスンもそうですが、世界経済は日本の部品への依存度をますます高めています。
一方で、世界の基幹技術はアナログからデジタルに変わってしまいました。そしてデジタルでは日本の産業 は弱い。部品産業はアナログだからまだ日本は強いのですが、デジタルで負けている分、トータルで見ると日本の産業力は低下していると思います。
近藤 変化していく環境にうまく対応できていないということだと思いますが、そもそも論として「日本がモノづくりに強かった」という点についてはどうお考えでしょうか。
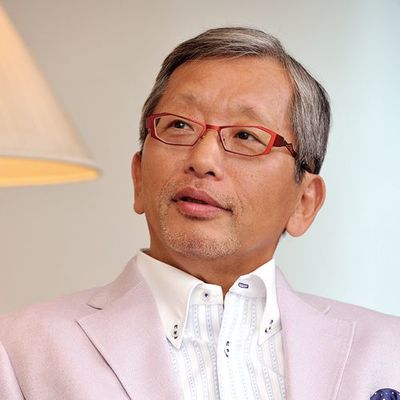
1950 年長野県生まれ。三井住友トラスト基礎研究所研究主幹。金融市場からマクロ経済、特にデジタル経済を専門とする。『ITとカースト』(日本経済新聞出版社)、『カウンターから日本が見える』(新潮新書)、『上品で美しい国家』(共著、ビジネス社)、『日本力』(講談社)など著書多数。
伊藤 そこは本当に強かったと思います。日本にはその素地もありました。まず江戸時代に300年平和が続いて、資本形成がうまくいった。そして、たとえば皇室で使うものをつくるような、高い技術が求められる職業が成立しました。
さらに、日本はモノをつくっても壊されない社会だったことも大きいですね。お隣の韓国は過去に何度も侵略され、何をつくっても壊されてきた歴史があります。中国もそういう意味では、前の民族がつくったモノを全部根絶やしにして、新しいモノをつくってきた。それに比べると日本は、ユーラシア大陸の右端に位置しているおかげで侵略を受けませんでした。
そういう素地があるから、明治維新以降の西洋技術のキャッチアップも非常に早かったのです。資本があって技術があって、モノをつくる人がいて、つくる人に対する尊敬があって、それを大事にする文化や美意識がある。その点で、モノづくりに強い、産業国家となる条件が整っていたと思います。
近藤 ということはやはり、アナログの時代にはうまくいっていた。けれども、デジタル革命にはついていけなかったというのが日本産業の現状ということですね。ではなぜ日本は、産業のデジタル化でつまずいてしまったのでしょうか。
伊藤 経営者がデジタルの本質を理解していなかったからでしょう。日本企業は製品と製品をつなげてループにする力が弱い。ループとは、部門を超えてデジタル技術で連携をとり、製品やサービスをワンランク上のものに昇華することです。今、アップル以外の製品を買っても面白くないのは、このループがないからです。たとえば今の日本の車載カーナビを見ても、目的地を入力するのにスマホで電話番号を調べて、もう1 回ナビに電話番号を入力しないといけない。こんなバカらしいことはないですよ。
近藤 日本の電機企業からiPhoneやiTunesが出てこなかったのは、そのループがうまくつくれなかったというわけですね。
伊藤 そうです。つまり、会社のなかで意思統一ができていないからです。日本の企業は、やっぱりセクショナリズムに支配されています。相変わらずテレビの部門に役員を置いて、スマホの部門に役員を置いて、社長が1人ひとり呼んで「お前のところは売り上げが伸びてない」とやっている。一方で、なぜアップルから出てきたかといえば、スティーブ・ジョブズという1人の人間の頭のなかに構想があり、すべての製品がつながっていたからです。本来、デジタルというのは製品の枠を超えた「壁崩し」の技術です。それなのに組織の壁を残したことによって、製品がワクワクするものにならなかったというのがいちばん大きい原因だと思いますよ。それはデジタルの「壁崩し」の特徴を、経営者がまったく理解していないからです。
なぜ日本企業のトップは
会社を変えることができないのか
近藤 日本の産業がデジタル化の波に乗り遅れた原因は、経営のトップが事の本質を理解できていなかったからということですね。
伊藤 ある企業の技術者と話したことがありますが、彼らは気づいていたようです。しかし、現場で1人や2人がわかっているだけでは駄目です。やはりトップが理解していないと。

自動車、テレコミュニケーション・メディア業界を中心に、企業戦略、オペレーション改革、海外展開戦略の策定・実行支援など、クロスボーダーを含むプロジェクトを数多く手掛けている。GlobalConsulting Executive Councilの主要メンバー。デロイト コンサルティング アジアパシフィック地域代表。
近藤 トップに問題がある、というのは同感です。取締役が何人集まっても、会社を変えることはできません。その役割は、トップでなければできないことです。しかしそれが機能していないケースが多いようです。
多くの大企業において創業者が経営していた時代は、トップが機能していました。現在でも、ソフトバンクや日本電産、ファーストリテイリングなどはそうだと思います。自分自身にアイディアやモチベーションがあるし、下に対して物も言える。でも代替わりしていくうちに、多くの日本企業の経営者がサラリーマン社長になってきました。彼らは総じて、創業者ほどの経営意欲がなく、取り組み方も甘い。これでは会社を変えていくことはできません。
伊藤 私もサラリーマンをしていたことがあるのでわかるのですが、右に頭を下げ、左におべっかを使って神み輿こしに乗らないと、社長にはなれない。でもそうして社長になった人が、ドラスチックに会社を変えることは難易度が高い、というか不可能に近いとさえ思います。
近藤 トップがもっと危機意識を持たないと、いずれ大変なことになりますね。
伊藤 そのとおりです。その点、日立製作所はうまく会社を変化させつつあります。歴史が古い会社ではありますが、いち早く訪れた危機に対してトップが本気で何とか乗り越えようとしたからです。
近藤 伊藤さんから見て、「ここはうまくやっているな」という会社はほかにもありますか。
伊藤 トヨタ自動車はがんばっていると思います。創業家から出たトップである豊田章男さんの車に対する熱意はいいですね。それにG-BOOKなどで、デジタルを車のなかに取り込もうという意思がある。日本のメーカーでスマホとカーナビをくっつけたのはトヨタです。ただ、まだ一般には普及していないのですが。
トヨタは今、世界一の生産台数を誇るわけですから、もっとリーダーシップをとって、どのメーカーのスマホからでもカーナビが動かせるようにデファクトスタンダードをつくればいい。
ただ、こうした期待できる企業がある一方で、日本の製造業には、いまだにメールを秘書に打たせている役員なんかがいっぱいいるわけです。こういう人たちが全員消えない限り、日本の製造業が生まれ変わることはできません。しかも日本企業で社長になるためには皆の支持を受けないといけないから、現役の社長に頭を下げて、現役の社長から「俺が会長になったら、これとこれをやれ」「はい、わかりました」と同じ路線を踏襲するわけですから、なかなか社長も会社を変えていくことができない。
近藤 その点はトップの任期の問題も大きいですね。以前、日本企業で社長に就任する年齢を調べたことがあるのですが、平均で59歳でした。仮に59歳で社長になって、65歳が定年だとしても、6年間しかない。就任1年目と最後の1年は引き継ぎに費やされるでしょうから、正味4年しかありません。このサイクルを断ち切らない限りは難しいでしょう。10年くらい取り組める若い人間がトップにならないと、会社を変えることはできない。そうした経営者を増やすためにも、やはりどこかで断絶をつくって、強引に社長を若返らせるしかないと私は考えています。30代、40代がCEOになるような米国型の仕組みも、やはり必要だと思います。
伊藤 それを実現させるのはハードルが高いと思いますが、成功すれば、神輿に担がれていないで、自分の頭で考えて、肌感覚で仕事をして、会社を変えていく経営者が出てくるでしょうね。