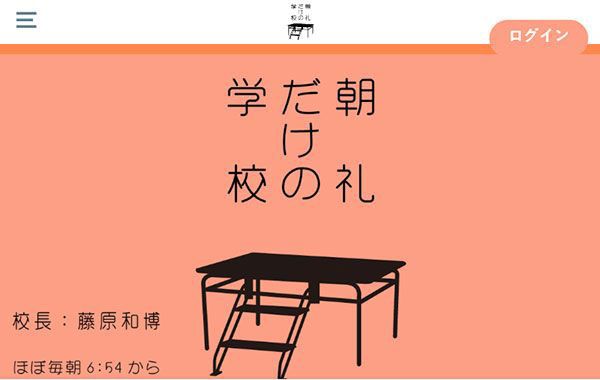コロナ後は「情報編集力」の時代へ オンラインならではの学びが社員を伸ばす

中高生と大人が一緒になって学び刺激し合う場
――藤原さんは東京都杉並区立和田中学校や奈良市立一条高等学校で、教育改革を実践してきました。2021年1月には、オンラインの「朝礼だけの学校」を立ち上げました。その狙いはどこにありますか。
藤原 「朝礼だけの学校」は、人生100年時代の「処“生”術」(藤原氏の造語。自分が主体となって、人生を処するための方法)を学ぶ寺子屋のような存在です。中高生と大人が一緒になって学びますが、参加者全員が生徒であり、先生でもあります。僕がほぼ毎日15分前後の朝礼を行っているほか、テーマに沿って対話や交流ができる複数の教室を用意していますので、学びを通じて刺激を受けることもできます。
「朝礼だけの学校」を始めた理由は、「情報編集力」を身に付けられる場を提供したいと考えたからです。日本の学校教育は「正解至上主義」で、正解を速く正確に言い当てる「情報処理力」を鍛えてきました。これまではそれでもよかったのです。ただし、現在のように社会環境が多様化、複雑化してくると、正解が1つとは限らなくなります。そこでは、自分の知識、技術や経験を組み合わせて仮説を出し、介在する他者も納得させるような「納得解」を導き出す力が必須になります。これが「情報編集力」です。
ビジネスパーソンが生き残るには「希少性」を高めることが必要
――新型コロナウイルスの感染拡大の影響により「ニューノーマル」という言葉を聞く機会も増えています。ビジネスパーソンにとっても企業にとっても、意識改革が求められそうです。
藤原 テレカン(テレビ会議)が当たり前になることで、その会議が本当に必要なのかが問われるようになりましたし、皮肉にも、「部長や課長がテレカンで大したことしか言わない」といったこともバレてしまうようになりました。そういった点からも、コロナ前の「情報処理力」の時代から、コロナ後の「情報編集力」の時代に大きくシフトしたといえます。
さらに今後、AI(人工知能)が発達することによって、人間がしていた仕事の多くがAIを搭載したロボットに取って代わられるようになります。つまり「処理」するだけの仕事はなくなってしまうのです。こうした変化の時代にビジネスパーソンが生き残るには自分自身の価値を上げることが大事です。言い換えれば「希少性」を高めることです。
僕はよく「100万人に1人の存在を目指すべき」と話しています。「そんなの無理だ」と思うかもしれませんが、身に付けたキャリアを「掛け合わせ」、進化させていくことでそれが可能になります。具体的には「キャリアの大三角形をつくる」ことです。
営業でも経理でも、1つの仕事をマスターするのに1万時間かかるといわれます。それだけ取り組めば、100人に1人くらいの希少性は得られるでしょう。20代で1つの足場を固め、30代で2つ目の足場をつくります。40~50代では、別の領域へ3歩目を踏み出すのです。そうすれば、100分の1×100分の1×100分の1で、キャリアの大三角形が完成し、100万分の1の希少性を確保できます。ちなみに、さらに50~60代では自分の美意識、志、哲学などにより、平面だったキャリアの総量に「高さ」が生まれ、描いた三角形が3次元化します。