すごい「テレワーク」カンファレンス シリーズ働き方改革セミナーレポート

主催:東洋経済新報社
協賛:Dropbox Japan Slack Japan ZVC Japan



オープニング
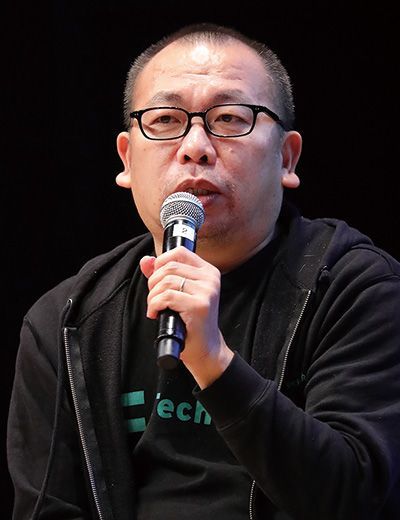
編集統括
吉田 博英氏
TechCrunch Japanの吉田博英氏は、参加者を対象に行ったアンケート調査に触れ、テレワークを導入している企業が25%弱あったと紹介。「労働時間を増やしも減らしもせずに、労働の質を向上できる」と指摘し、テレワーク導入の意義を強調した。
基調講演
いつでも、どこでも、誰でも、誰とでも働ける世の中の実現に向けて

デザイン工学部
企画構想学科 教授
松村 茂氏
テレワーク月間実行委員長も務める東北芸術工科大学の松村茂氏は、テレワークが「ICTを活用した、場所、時間にとらわれない柔軟な働き方」と定義されていたが、最近は「ICTを活用し、場所、時間を有効に活用できる柔軟な働き方」に変わってきたと指摘。2019年の「テレワーク・デイズ」には延べ60万人以上が参加したことを挙げ「やればできるということを証明した」と語った。テレワークは災害対策としても有効であること。総務省による「ふるさとテレワーク」の取り組みを示して、テレワークが地方の活性化にも有効で、「もう実験の段階は終わった」とした。「これからは、ワーカーファーストで、誰と一緒に仕事をしたいか、仕事環境を自らつくりだす時代に移ってきている。テレワークは誰とつながりたいか、オフィスを飛び出し多様な人材と『つながること』を目的とした『つながるテレワーク』になる。それはオープンイノベーションや副業拡大にも発展する」と強調。そうしたテレワークを認める企業が支持される時代になっていると結んだ。
デモンストレーション
「すごいテレワーク」は何がすごいのか?

シニアセールスエンジニア
安田 真人氏

シニアテクノロジー
ストラテジスト
溝口 宗太郎氏
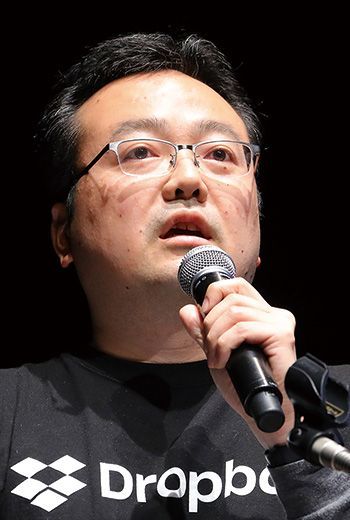
ビジネス
ディベロップメントリード
佐野 健氏
オンライン共同作業場である“スマート ワークスペース”を提唱するDropbox、ビジネスチャットのSlack、ビデオコミュニケーションのプラットフォームであるZoomがそれぞれデモンストレーションを展開し、3つのツールを連携させて使うことでメリットも大きくなると紹介した。
ディスカッション

カントリーゼネラルマネージャー
佐賀 文宣氏

カントリー・マネジャー
佐々木 聖治氏
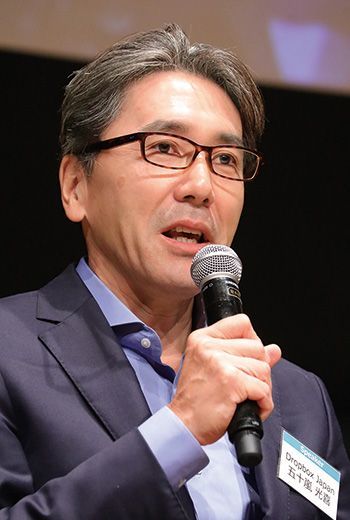
代表取締役社長
五十嵐 光喜氏
次いでパネルディスカッションに移りDropbox Japanの五十嵐光喜氏は、「いつでもどこでも仕事ができるのが当社のグローバルなスタンダード。自分たちがそれを実践し、全社員が毎日、少しずつテレワークしている。このカンファレンスの準備でも、3社が直接会うことはほとんどなかった。
Dropboxはお客様の大切な情報を預かるので、セキュリティーには細心の注意を払い、データを暗号化しているうえに、情報本体とメタデータを分離して管理している。また個人でもご利用いただいているため、使いやすさが生命線。人に教えてもらわなくても使える製品に仕上げるのが根幹だ」と語った。
また、Slack Japanの佐々木聖治氏は「17年に日本市場に参入したときからリモートワークを推奨してきた。自分も移動時間にはテレワークしている。Slackのユーザーは初期段階ではエンジニアやIT系が多かったが、最近は業種や職種に関係なく広く使われている。Slack、Dropbox、Zoomを連携させて使うとスピード感があり、業務の効率化にもつながる利点がある。使ってみてわかるよさもあるので、体感してみることが大事だ」と述べた。
ZVC Japanの佐賀文宣氏は「社員が高いパフォーマンスを発揮できるような働き方にするのがテレワーク。期間を限定したり、特別なときだけにしたりするのではなく、普段から取り入れるべきワークスタイルだ。自分はフェース・トゥ・フェースのコミュニケーションも好きだが、当社は面接もZoomで行っている。セキュリティーに関して、暗号化は当然として、なりすましで会議に入ってくるのを防ぐなどさまざまな対策を講じている。1人でテレワークをしていると孤独になってしまうこともあるので、ほかの人と頻繁に会話することが必要だ」と指摘した。
クロージング講演
経営改善につながるテレワーク
~なのに、やりたくない人だらけ!~

代表取締役
総務省委嘱
テレワークマネージャー/
総務省委嘱
地域情報化アドバイザー/
岡山県 特命参与(情報発信担当)
森本 登志男氏
テレワークを導入していない企業にその理由を聞くと、「適した仕事がないから」という答えが圧倒的に多い。しかし、会議や出張、外回りの仕事にはテレワークが適している。それらの仕事がない会社などあるのか、と話したキャリアシフトの森本登志男氏は、次に佐賀県庁の例を挙げた。全庁でタブレット端末などを導入し、テレワークができる体制を整えた1年4カ月後に、大雪で交通機関がストップしたとき、約1割の職員が在宅勤務を実施した。災害時、自治体は通常時以上に仕事量が増えるが、テレワークで災害時を乗り切ったというわけである。またある中小建設会社は、現場と自宅をサテライトオフィスとみなし、自宅から直行直帰ができるようにした。そのため移動に使う車のガソリン代などが大幅に減少。その浮いたコストを使い会社は社員の資格取得を奨励したところ、資格者を必要とする仕事の受注量が増え、利益率が向上し、売り上げは大幅増、さらに新卒採用の応募者も激増した。
こうした例を紹介した後で森本氏は、企業にはテレワークで助かる人が必ずいるとし、「いざというときにはテレワークができるというだけで気持ちがどれだけ違うか」と強調。そのことに早く気づき、早くテレワークを導入したほうがいいと語った。





