さらば、働かない「働き方改革」 シリーズ働き方改革セミナーレポート
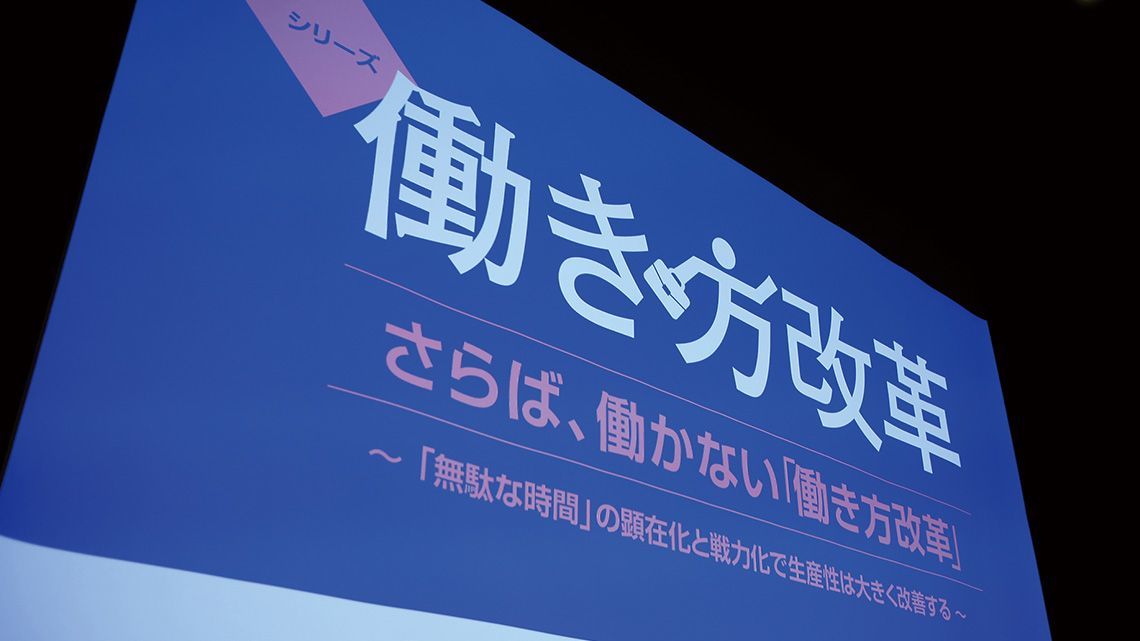
主催:東洋経済新報社
協力:Dropbox Japan
オープニング
生産性を高める働き方改革
2000人の調査結果から見えてきた、「生産性」と「情報共有」の深い関係

代表取締役社長
五十嵐 光喜氏
企業のコラボレーションプラットフォームを提供するドロップボックスの五十嵐光喜氏は、労働時間を短縮すれば、売上高減少が懸念されることから、アウトプット(売上高)÷インプット(労働量)で計算される「生産性」の向上が必要になると指摘した。働き方改革関連法の施行から1カ月となる5月に同社などが2000人を対象に実施した調査では、長時間労働に対する取り組みで成果を出しているという回答が5割超の割合なのに対し、生産性向上の成果は4割に満たないという結果を提示。生産性向上に成果を出しているところは、勤務形態・時間の多様化以外に、ITシステム導入による作業効率化をはじめ幅広い取り組みをしている傾向があると分析。「本来の仕事以外の無駄な作業時間の効率化がカギになる」と結論した。
基調講演(問題提起)
残業学:残業はなぜ生まれるのか?どのようにして減らせばいいのか?

経営学部
教授
中原 淳氏
長時間労働についてパーソル総合研究所との共同研究を行った立教大学の中原淳氏は、残業発生の3つのメカニズムから説明した。1つ目が「感染」。みんな、本心では早く帰りたいのに、周囲から「トンデモナイ」と思われないか不安で口に出せず、誰も望まない同調圧力が生まれ、帰りにくさが感染。上司の朝令暮改やマイクロマネジメントによる仕事量増加でさらに感染が拡大する、とした。2つ目が「遺伝」。上司が無意識に自分が若い頃の働き方を押し付け、世代や組織をまたいで残業が受け継がれる。そして3つ目が「マヒ」。残業が月60時間を超えると、ランナーズハイならぬ「ザンギョーズハイ」というべきマヒ状態になり、社員の主観的幸福感は微増する。ただし、健康・休職リスクが増大し、社員の能力開発も阻害する。
残業削減の方策は、「時間を意識せずに働いてしまう」社員に、出退勤管理の徹底やPCシャットダウンなど、時間の境界を強制的につくる「外科手術」。上司に対するフィードバック強化でマネジメントスキルを向上させる「体力増進」。残業を生む職場の体質を組織開発の手法で改善する「漢方治療」の3つを提示。
組織開発は、長時間労働の背景にある、役割分担の非効率、特定の人に属人的業務が集中する、といった組織の真の問題を「可視化」。関係者が真剣に問題を議論する「ガチ対話」を通じて、今後どうするかを決める「未来づくり」――の3ステップで行う。「データは、まず長所から提示し、それを持続可能にするために何をすべきか、というロジックにするのがコツ」で、犯人捜しではなく、建設的対話を促すことがポイント。「残業は個人の時短、仕事術で是正できるという個人責任論が根強いが、職場、上司の問題が大きい。組織ぐるみの解決が必要」と訴えた。





