反抗期の心も解きほぐす「学校の先生」の実力 「人は変われる」その手助けをやり抜く覚悟
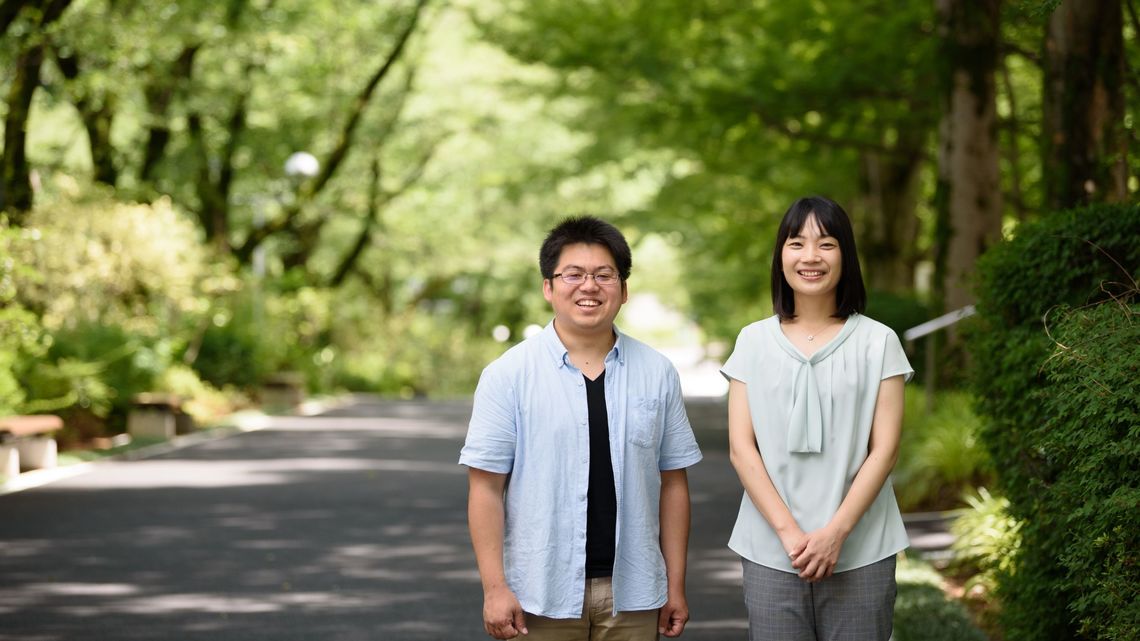
――嶺井さんは小学校で、大川さんは中学校で教員をされています。まずは教員を志した経緯を教えてください。

2005年卒業生。現在は武蔵村山市の小学校に理科専科として勤務。19年春より1年間、より高い専門性を求めて創価大学教職大学院で学んでいる
嶺井勇哉(以下、嶺井) 小さい頃から理数系が得意で、「将来は算数の先生になりたい」と考えていました。はっきり意識したのは中学生の頃。実は当時、校内暴力に巻き込まれて大ケガを負った経験があるのですが、このときに先生が熱心にケアをしてくれたことが心の拠り所になりました。ただ勉強を教えるだけでなく、「子どもを守れる存在になりたい」と思うようになり、教員を目指す理由が一段と深まりました。
そして高校生のとき、オープンキャンパスをきっかけに、創価大学への受験を決めました。手書きで「ようこそ」と書かれたカードをもらったり、私の質問に対して職員の方が丁寧に説明してくださったりして、一人ひとりを大事にする大学だと強く感じたからです。

2011年卒業生。学生時代は「中国研究会」で活躍。現在は東京都内の中学校で、英語教員として教鞭をとる
大川久美(以下、大川) 私はもともと、教員というより子どもの心に関わる仕事がしたいと考えていました。私自身も中学生の頃、非常に心が不安定な時期がありました。そのとき親身になって指導してくれたのが、部活の顧問の先生です。ただ優しいだけじゃなく耳の痛い話もしてくれて、こんなふうに人の心に入っていける大人になりたいなと。
教員か、カウンセラーか。進路は片方に絞らずに、教育学部で心理学の勉強もできる創価大学に進学しました。創価大学は「真の人間教育」を掲げていることも魅力。いつか教壇に立つ日までに人間として成長したいという思いを、しっかりかなえられる大学だと思いました。
教育は「未熟な子どもに大人が教える」ことじゃない
――大学ではどのようなことを経験されましたか。
嶺井 教員としての技能はもちろん、「教育とは何か」「子どもとは何か」といった本質的な部分を学べたのがよかったです。それまで「教育=未熟な子どもに教えること」と勘違いしていましたが、大学で学ぶうちに、子どもを1人の人間として捉え、その可能性をいかに伸ばすかが何より重要だという見方に変わりました。

大川 私は心理学の勉強をしたくて、精神科医である阿部惠一郎先生のゼミに入りました。印象的だったのは、少年院を訪れ、ゼミOBの法務教官に話を聞いたときのこと。進路に迷っていることを阿部先生に相談したら、「あなたは子どもの悩みを飲み込んでしまうから、カウンセラーには向かない。少年院の前の段階、学校の現場で子どもたちを助けてあげてほしい」とアドバイスをもらいました。
おかげで、自信を持って教員の道を選ぶことができました。阿部先生に限らず、大学の教授に悩みを相談すれば、解決するためのヒントをたくさん与えてもらえる環境だったと今振り返って思います。









