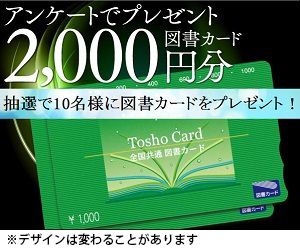広告は、嫌われるかの分岐点に立っている 「バズらせる」が目的化すると炎上の危険も

手法が目的化してしまうとマーケティングは失敗する
―現在のデジタルマーケティングの最新トレンドとは?

取締役CMO
徳力 基彦
徳力 日本ではマスメディアが依然として大きな力を持つ一方、若者のテレビ・新聞離れが加速しています。そうした中、彼らに対してどうマーケティングをすればいいのか。大手クライアントも本格的にデジタルマーケティングに乗り出し、新しい手法にチャンレジするという流れが生まれています。しかし、そのチャレンジの方法が悪いと、動画が炎上したり、広告自体が批判されたりする。一見、デジタル広告で成果が上がっているように見えても、一方で広告を嫌う人が増えるという事態になっていたりします。
―具体的にはどのようなことなのでしょうか。
徳力 デジタルマーケティングにおいて、メリットとデメリットは表裏の関係にあります。企業側からすれば、個人の詳細なデータを取れることで広告をパーソナライズできるうえ、個人がメディア化したことで広告自体が話題となって口コミで拡がり、広告を効率化することができます。一方、これを裏返せば、ユーザー自体もデータを簡単に入手できることで広告を信じにくくなり、パーソナライズされることに気味悪さを感じる。さらに個人が広告を批判することで、ときには炎上も起きてしまう。つまり広告自体が企業の評判のリスクにつながるケースが増えているのです。今後、ネットやSNSのユーザーの間で、広告がどのような位置付けになるのか。今は、その分岐点にあると言えます。
―分岐点で対応を間違えば信頼を失ってしまうということですか。
徳力 今後の対応次第では、デジタルマーケティングの価値自体を低下させるリスクをはらんでいます。北風と太陽の逸話の北風のように、ユーザーが見てくれないからと広告を無理矢理表示すると、さらに広告の印象は悪くなる。本来なら太陽のように、企業がメディアのコンテンツをサポートする立場で、企業側への関心や感謝を醸成するべき。このまま北風ばかり吹くと、悪貨が良貨を駆逐するような事態になりかねません。
―そうした中で、デジタルとマスメディアは、どんな関係にあるのでしょうか。
徳力 従来のマーケティングはアナログとデジタルが別ものとして扱われてきました。企業側でもマスメディアとデジタルの担当は別部署で仕事も別々でした。しかし、マーケティングはそもそもそんなものではない。お客様の側に立ってみれば、デジタルかアナログかはあまり関係ありません。むしろ、今は従来の知見とデジタルが可能にしたことを組み合わせてマーケティングを進化させていく時代と捉えるべきなのです。