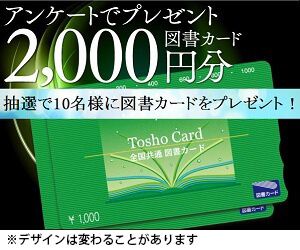新たな産業集積モデルの構築を
確実に進む物流施設の地方立地
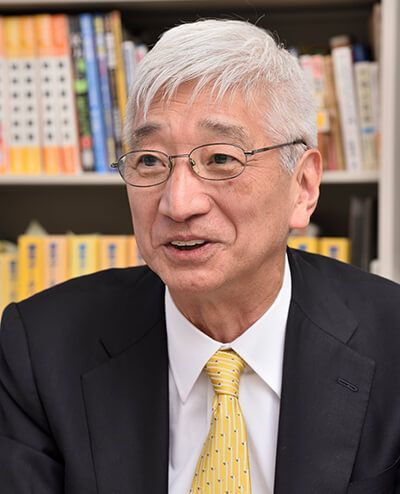
柏木 孝之(かしわぎ たかゆき)
ここ数年の工場立地動向調査を見ると、地方に新規立地している施設の多くが物流施設である。多いときは7〜8割が物流施設で占められていることもある。
圏央道沿いでは国内の大手有名企業・外資などが大規模なロジスティックセンターを次々とつくっている。ただ、当該地域が活性化するには、ロジスティックセンターに情報センター的機能のような施設や機能がプラスされていると波及効果が高い。
今は高学歴の女性が郊外に住む例が増えている。情報センターができれば、そうした女性が働く場になりえる。データ収集・整理だと、仕事は深夜の時間帯になることが多い。そこで多くの女性が働くとなると、安全性をどう担保するかということが課題になる。産業環境条件として、夜間も照明で明るくするなどの方策が必要になるだろう。夜間が明るくなると、夜の人通りが増え、飲食店などもできるようになる。人の流れも変わってくる。そう考えると、ロジスティックセンターの増加は地域経済にとってプラスになる。
かつては、量産段階に入った製品の製造が地方に分散するというのが、日本型の産業集積モデルであった。けれどもバブル崩壊以降、韓国、台湾や中国の量産メーカーが急速に台頭し、そうしたモデルは説得力がなくなってしまった。そこで私は海外各国を見て回ったが、米国テキサス州の都市、オースティンで、新たに日本型産業集積モデルに応用できるものに出会った。