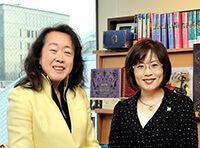自文化に誇りを持ち、異文化に垣根をなくす 東洋大学
第8回は、酒造りの本質にこだわった純米大吟醸酒「獺祭(だっさい)」を海外展開する旭酒造社長の桜井博志氏と、近現代日本文学を研究する東洋大学文学部の石田仁志教授が対談。世界から高い評価を受ける「獺祭」の魅力と、自文化と異文化への理解を深める「国際文化コミュニケーション学科※」の2017年開設を構想する東洋大学の取り組みを踏まえ、日本文化を海外へ発信する上で必要となる人財像を探った。

桜井博志
1948年に創業した家業、旭酒造に1976年入社。だが、酒造りの方向性や経営をめぐって先代の父と対立して退社し、石材卸業の櫻井商事を設立。1984年に父の急逝を受け家業に戻り、純米大吟醸「獺祭」の開発を軸に経営再建をはかる
石田 「獺祭」はとても美味しいお酒で、私は大ファンです。桜井さんの著書も拝読しましたが、「獺祭」は洗米を手作業で行うといった伝統を守る一方で、杜氏に頼らず、コンピュータを使ってデータによる管理を行うなど、革新的な手法を導入されているそうですね。
桜井 革新的に見えるかもしれませんが、それは自分が「美味い」と思うものを追求した結果であり、私自身は「美味しい酒を造る」という当たり前の、古典的な本質に回帰しているつもりです。戦後の経済発展に伴って農村は姿を変え、日本の伝統的な杜氏制度を維持するのが困難になっています。それならば、杜氏には頼らず、どうすれば質の良い酒が造れるのかを自分たちで徹底的に追求しようと考えました。

石田仁志
東京都立大学人文科学研究科国文学専攻修了。文学修士。専門は日本文学。近代文学を中心に、川端康成とともに新感覚派として活躍した横光利一を研究。横光の『上海』研究を一つの足掛かりとして、戦間期の東アジアにおける日本語文学の展開について幅広く考察している
石田 確かに、日本酒や歌舞伎、能・狂言、あるいは現代の精密機械などに象徴されるように、日本文化の優れた点は「質」にあると思います。細部にまで気を配り、優れたものを探求するという「こだわり」が、日本文化の「質」を支えているのではないでしょうか。桜井さんは、「獺祭」をニューヨークやパリをはじめ海外展開されていますが、日本酒の魅力をどのように伝えていますか。
桜井 欧米人にとって日本酒は、理解しがたい「矛盾のかたまり」だといいます。日本酒の製造工程では、米のデンプンを麹で糖化させ、できた糖を酵母でアルコール発酵させます。その時、酵母にとって最適な温度(25度程度)よりずっと低温で発酵させるのですが、なぜわざわざ低温にするのか。また、糖化と発酵の過程を一つのタンクで行うのも、2つの過程を別々のタンクで行った方が合理的なのではないか。欧米式の合理的観点から見た日本酒は、多くの矛盾、疑問となる点を抱えています。しかしながら、欧米人への歩み寄りのきっかけとして使えるツールが「美味い」という万国共通の揺るぎのない感情です。そこをきっかけに、手間暇かけて優れたものを追求した結晶である日本酒、さらには「獺祭」の魅力を理解してもらおうと、日々情報発信を行っています。
石田 「獺祭」が世界で評価されている理由については、どのようにお考えでしょうか。
桜井 我々としては、まず「美味しい」ということ、そして、海外に売っていこうという強い意思があること、さらには、その国の人達に理解してもらえる言葉で説明すること、の3つにこだわりを持っています。それらを踏まえて海外へ情報発信してきた結果、例えばフランスでは、有名シェフが「『獺祭』を初めて飲んだ時に、合いそうな料理がいくつも頭に浮かんだ」と話してくれるなど、「獺祭」の魅力への理解が広がりつつあることを実感すると同時に、日本の文化である日本酒が海外でも通用する自信にもつながりました。