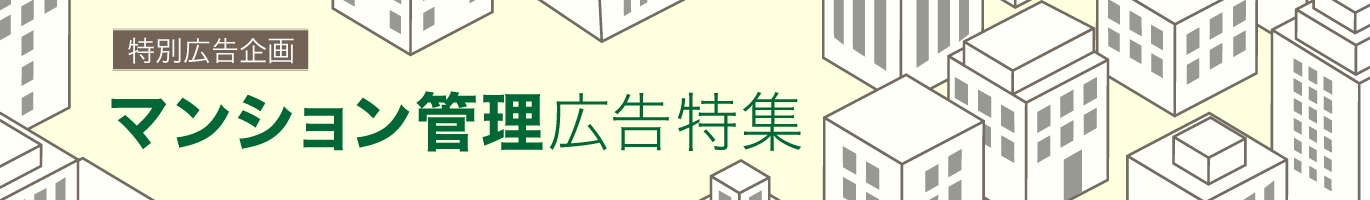ストック型社会において
「団地」の新たな価値を生む
日本総合住生活
団地はフローからストックへ
高齢化も大きな課題に
日本住宅公団(当時)が設立されたのは1955年のこと。その6年後に、日本総合住生活の前身である「団地サービス」が同公団の出資により設立された。その目的について、日本総合住生活の廣兼周一社長は次のように語る。
「当社はもともと、団地にお住まいの皆さまの生活を支える店舗や施設のテナント管理業務や、屋外環境の整備業務、修繕・補修業務からスタートしました。当社自身が日用品の販売などを行ったこともあります。以後、賃貸住宅・分譲住宅の管理、住宅リニューアルなどへと事業の幅が広がってきました」
戦後の復興期から高度成長期の住宅不足を解消するために、住宅公団による団地が数多く建てられた。ダイニングキッチンや水洗トイレなどを備えた団地仕様は当時、あこがれの的だった。しかし、その団地が今、大きな変化を迎えようとしている。
「住宅不足の時代からストックの時代になっています。UR都市機構も新築住宅の建設は積極的に行っていません。ストックの活用が大きなテーマです。さらに住民の高齢化などの問題は喫緊の課題になっています」と、廣兼社長は指摘する。
独自の技術開発研究所で
品質向上を推進
課題に直面する団地だが、一方で、その魅力が再注目される動きもある。

廣兼 周一
「数十年前に建てられた団地の多くは、ゆったりとした敷地で緑も豊かです。敷地内に大きな公園があるところも少なくありません。こうしたことから、若い子育て世代や、シニア・シルバー層のご夫婦などで『団地に住みたい』と考える人が増えています」と廣兼社長は紹介する。
結婚して自分が生まれ育った団地に戻ってくる人も多いという。UR都市機構では、これらの新しい住民のニーズに応えるために、古い団地のリニューアルなども進めている。
「当社もストック住宅のリニューアルニーズに応える設備機器や工法を開発しています。たとえば『エプロンインシステムバス』もその一つです」
古い住宅の浴室の給湯にはバランス釜と呼ばれる風呂釜が設置されていることがある。浴槽が狭くなるという欠点があったが、同社ではこの釜を薄型にし、前面のパネルの中に組み込む浴槽を開発した。清潔感のある広々とした浴室に変えられると好評だという。
「当社では『スクエアJS』と呼ぶ自社施設を持ち、技術開発研究やストック技術の提案・実験・教育などを行っています」
「エプロンインシステムバス」も、「スクエアJS」内にある技術開発研究所から生まれたものだ。
このほか、施設内にあるストック技術実験館では、1960年代のUR賃貸住宅をモデルに、実際の住棟を再現し、最新技術を検証・評価している。