「愛社精神」という、日本独自の不毛な発想 半沢直樹の苦悩は欧米人には理解できない

第1回『不正会計への道は「善意」で舗装されている』
東芝は組織ぐるみで長年不正会計を行ってきたが、ひとりくらい、「こんなことはよそう」と反対する人がいなかったのだろうかという疑問がわく。実際問題として、そういう声はなかなか上がらないのが日本の組織だ。その背景には、自分の人生や生活と会社を重ね合わせ、過剰な共同体意識や愛社精神を持ってしまう、日本人的な性(さが)がある。
日本の会社は世界の組織のなかでも最も同一的で同質的な集団である。そして、このような集団では、入社してすぐ背番号がつけられ、一生それを背負っていくことになる。そうした集団で長く過ごしていると、その集団内の規範が社会的規範を凌駕するのだ。おそらく、東芝の経営陣の間でも、不正は悪いことだと認識しつつ、「これは会社を存続させるために必要なことなんだ」という空気が醸成されていたと思われる。
『沈まぬ太陽』『半沢直樹』で描かれた日本独自の苦悩
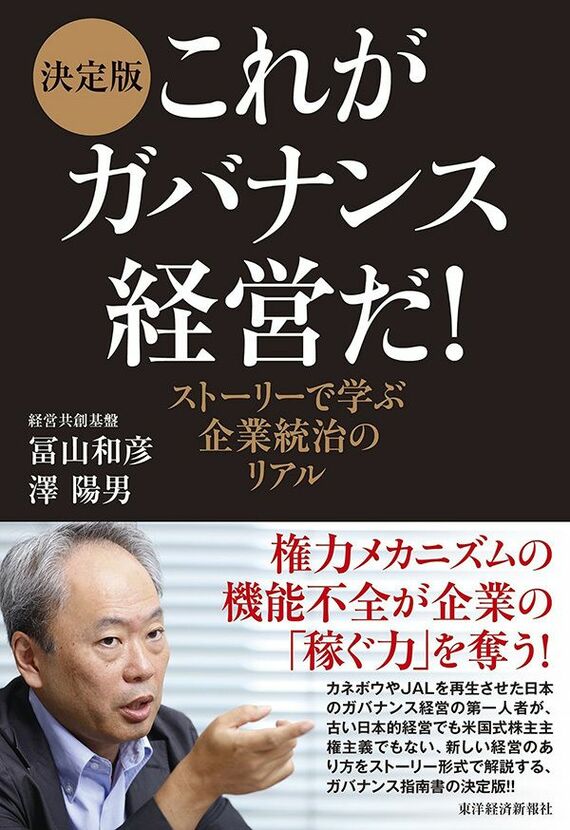
そういう共同体では、裏切り者が密告したりすることは基本的に少ない。もしあったとしても、その代償は所詮、ムラの中での「左遷ごっこ」にすぎないことが多い。
作家・山崎豊子氏の『沈まぬ太陽』では、日本航空がモデルと思われる航空会社を舞台に権力闘争の激しさが描かれている。映画化もされ、多くの日本人サラリーマンの共感を得た小説だが、冷静になって考えてみると、ずいぶんドラマチックに書かれているものの、結局は終身雇用の枠の中でやっている「左遷ごっこ」「出世ごっこ」にすぎない。
仮に権力争いに負けて失脚したところで、殺されるわけではない。会社をクビにすらならない。せいぜいナイロビに飛ばされるだけ。しかも、飛ばされたところで当時の日本航空のご立派な年金はもらえるのだ。引退したプロ野球選手や選挙に負けた政治家のように、いきなり食うに困るようなシビアな世界に追いやられるわけでもない。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら