史上高値圏の金投資は“今から”でも間に合うか 株高でも金が騰がる訳と、個人が投資する方法
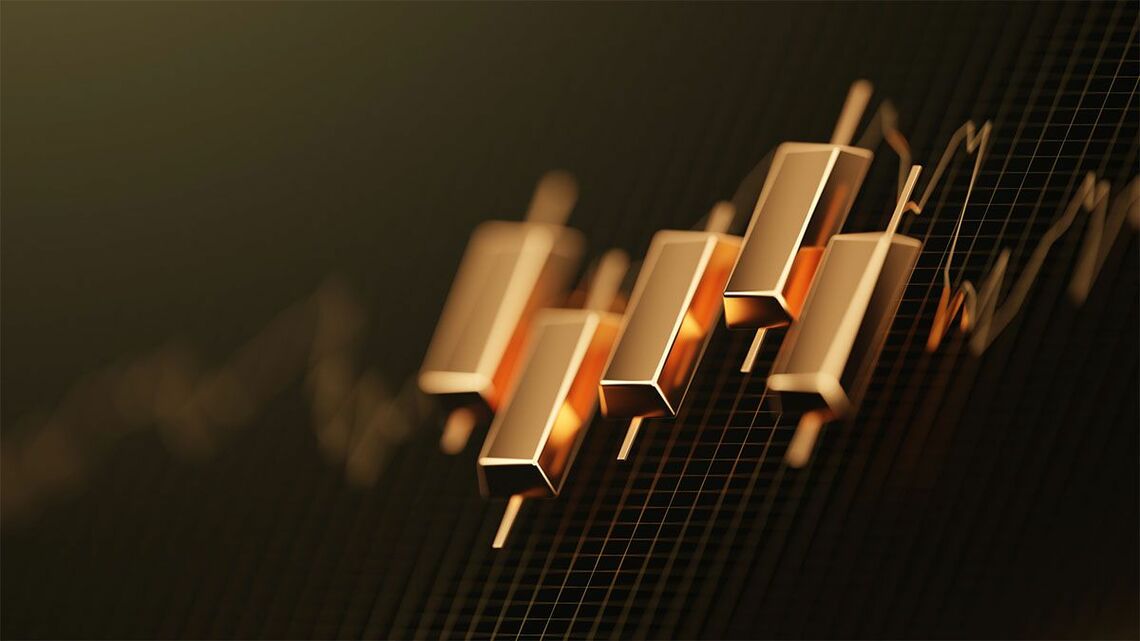
中央銀行が押し上げる新しい需給
――金価格が史上最高値圏にあります。今の動きをどう見ていますか。
2025年に入ってから、金は予想以上の上昇を見せています。ドル安、地政学リスク、アメリカの短期金利低下、インフレ期待――これらが同時に重なった結果です。
春から夏にかけては小幅なレンジ相場でしたが、8月後半から9月にかけて一気に動き、1カ月で約400ドル上がる場面もありました。投資家の間では「下がれば買う」という姿勢が定着しつつあり、金の強さが際立っています。
――株高が続く中で金も上昇しています。この「併走現象」をどう分析しますか。
本来なら株が上がる局面では金は売られる傾向にありますが、今回はその逆です。背景にはFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げサイクル再開への観測があります。実質金利が下がる局面では、利息を生まない金が相対的に有利になります。
インフレが完全に沈静化していないうえ、地政学リスクも続いているため、投資家はリスクオンでも今後のさらなるショックに備えるために金を保有しているのです。金はポートフォリオの優れた分散投資手段だからです。
――安全資産としての金が再び注目されているわけですね。
そうです。金は発行体の信用に依存しない、純粋な実物資産です。株や債券が企業や政府の信用を前提とするのに対し、金はその制約を受けません。だからこそ、金融危機や戦争といった不確実な局面では、最後に残る「保険のような資産」として見直されるのです。

ヴァイス プレジデント ゴールド・ストラテジスト
アーロン・チャン氏
――中央銀行の買いも相場を押し上げています。
はい。08年には年間235トンを売却していた世界の中央銀行が、22年には年間1080トンの純購入、23年には年間1050トンの純購入、24年には年間1089トンの純購入と、3年連続で1000トン超えの純購入に転じています。
とくにロシアのウクライナ侵攻以降、ドル資産への依存を減らす動きが顕著です。
金の世界組織のワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)の調査でも、76%の中央銀行が「今後5年間で金の保有比率は増加する」と予想しています。今や金は、国家レベルでも“備えの通貨”になりつつあります。
――短期的なリスクはどう見ていますか。
中央銀行の買いが一時的に減ると調整もありえますが、WGCの調査を見る限り構造的な買いの流れは続くでしょう。供給も年1%程度の伸びにとどまり、過去15年間で大きな鉱脈は発見されていません。希少性という根本要因が、金を長期的に支えています。
――実需の動向はどうでしょう。
価格高騰の影響で、宝飾需要は減少しています。25年上半期と24年上半期を比較すると、インドで21%減、中国では28%減と報告されています。一方で、延べ棒や金貨など投資目的の需要は堅調で、同時期の比較で、インドで7%増、中国では26%増えました。アジア全体の金ETF(上場投資信託)への資金流入も拡大しており、これに裏付けされた金の保有量も24年末216トンだったものが25年9月末時点で334トンに増加しています。文化的背景に加え、経済成長の裏付けがあるアジアでは、長期的な底堅さが際立ちます。
金投資の選択肢、ETFなら低コスト
――日本の個人投資家の動きはいかがですか。
2019年以降、円建ての金価格が上がり続けたことで注目が高まっています。新NISA(少額投資非課税制度)の導入を機に、少額から始める層が増えました。金は「初めての分散投資先」としても位置づけしやすい資産です。
――ETF市場にも資金が流入しています。
9月末時点で640億米ドルの純購入となっています。欧米を中心に、株高のヘッジや分散投資の一環としての金需要が戻ってきました。金は、政府の債務負担が増大し、地政学的緊張が高まり、国家通貨の安定性に対する信頼が揺らぐ中で、強力な価値の保存手段として位置づけられています。金は世界共通の価値尺度であり、通貨と同じ機能を持つ――そうした理解が広がっています。
――現物ではなく、ETFや投信で金投資を始める最大のメリットは何でしょう。
長期で持つ資産だからこそ、コストを徹底的に下げられる点が大きいです。現物は購入・売却の手数料に加えて、保管や保険の費用、盗難リスクまで考える必要があります。一方でETFは市場でその都度、公正な価格で即時売買でき、保管は信託側が担います。結果として総コストを抑えやすいのがETFの強みです。
――貴社のゴールドETFについて教えてください。
当社は「SPDRゴールド・シェア(GLD)」と「SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(GLDM)」の2本を提供しています。
25年9月末時点でGLDの資産残高は1245.3億米ドル(約18.4兆円)で世界最大かつ最も取引されている金ETF※です。スプレッド(売買価格の差)が非常に狭く、流動性が高い点が特徴です。
GLDMは低コストで、長期保有を重視する個人投資家に向いています。
今年8月にはGLDMを投資先とする公募投信(ファンド)も発売しました。為替ヘッジあり・なしの2タイプで、楽天証券で取り扱っており、同社内では最安水準、全体でもトップクラスの低コスト帯です。現物を直接持たなくても、世界の金市場にアクセスできる手段として、幅広い層に使っていただけると思います。
日中の機動を重視するならETF、積み立て運用の仕組みを使うなら公募投信という使い分けもできるでしょう。
※ブルームバーグ・ファイナンスL.P., 2025年9月30日時点
――「ここまで上がると、今からでは遅いのでは」という声もあります。
19~20年も同じことが言われましたが、その後さらに上がりました。法定通貨はインフレや通貨供給量の増加により価値が目減りします。長期的に見れば、今の水準でも保有を始める意味は十分にあります。
大切なのはタイミングではなく、時間を味方につけることです。積み立てや安い時に多く買って高い時に少なく買う「ドルコスト平均法」などを活用し、継続的に保有していくことが投資ポートフォリオのリスク調整後のリターンを高める効果が期待できます。
金は株や債券と相関が低く、全体の安定性を高める資産として、ポートフォリオの株式比率が60%以上の場合は、金の割合を10%以上に増やすことを検討するのもよいでしょう。
――最後に、個人投資家へのメッセージをお願いします。
金は株式投資のように日々の値幅を狙う商品ではありません。年金のように長期で積み上げる資産です。ETFや公募投信を活用して少しずつ保有を増やす。そうした「長期的な価値の保存手段」として考えていただければと思います。
⇒ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントのゴールドシリーズの詳細はこちら

コモディティ及びコモディティ指数連動商品は、市況全般の変化、金利変動や、天候、疫病、禁輸あるいは 政治及び規制といったその他要因のほか、コモディティ現物における裁定業者や投機家の取引行動により影響を受けます。ETFや投資信託を頻繁に売買した場合、売買手数料や他のコストが大幅に増加し、その結果、低いフィーやコストによる節約効果が相殺されることがあります。分散投資は、利益を確保したり、損失回避を保証するものではありません。コモディティ投資には大きなリスクを伴うため、すべての投資家に相応しいとは言えません。
<SPDR®ゴールド・シェア(「GLD®」)およびSPDR®ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(「GLDM®」)に関する重要情報>
SPDRゴールド・トラストはGLDに係る、そしてワールド・ゴールド・トラストはGLDMに係る(目論見書などの)届出書面をそれぞれ証券取引委員会(「SEC」)に届け出ています。各ファンドとも1940年投資会社法(「1940年法」)の下で登録された投資会社ではありません。そのため、各ファンドの投資主には1940年法の下で登録された投資会社の株式保有に伴う保護がありません。GLDおよびGLDMは1936年商品取引法(「CEA」)の規制対象ではありません。そのため、GLDおよびGLDMの投資主にはCEAが提供する保護がありません。各ファンドの受益権は株式のように売買され、投資リスクがあり、時価が変動します。GLD受益権およびGLDM受益権の価値は、各ファンドが保有する金の価値(経費控除後)にそれぞれ直接関係しており、金価格の変動が受益権への投資に大幅に不利な影響を与える可能性があります。時価で売買される受益権の売却に際して受け取る価格は、受益権が表象する金の価値よりも多い場合も少ない場合もあります。いずれのファンドもインカムを生じず、各ファンドは継続的に発生する経費を賄うべく金を定期的に売却するため、各ファンドの受益権が表象する金の量は時間の経過とともに相応分減少します。MiniShares®はWGC USAアセット・マネジメント・カンパニーLLCの登録商標であり、WGC USAアセット・マネジメント・カンパニーLLCの許可を得て使用しています。
<ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)に関する重要事項>
投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建て資産には為替変動リスクもあります)を投資対象としているため、お客さまの資産が当初の投資元本を割り込み、損失が生じることがあります。基準価額の変動要因には、金の価格変動リスク/為替変動リスク/流動性リスク/信用リスクがありますが、リスクはこれらに限定されるものではありません。投資信託は1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2.購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。
<手数料・費用>
(売買手数料)取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
(SPDR®ゴールド・シェア[GLD、1326]、SPDR®ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト[GLDM]の信託にかかる費用)管理会社・受託銀行に支払う報酬、マーケティング・エージェントに支払う報酬、監査費用等があり、それぞれ年率0.40%、0.10%(GLDおよび1326、GLDM、2025年9月末時点)です。その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。当ETFの運営費用は将来にわたり変更される可能性があります。※取得のお申込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面またはその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取り扱い金融商品取引業者(証券会社)までお問い合わせ下さい。
(ステート・ストリート・ゴールド・オープン(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)の運用にかかる実質的な信託報酬)年率0.2925%程度*マザーファンド受益証券を通じて投資する投資対象上場投資信託証券の管理費用等年率0.10%を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。ただし、この値は目安であり、投資対象上場投資信託証券の実際の組入れ状況等により変動します。
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第345号
加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会、日本証券業協会







