エグゼクティブが注目する不動産投資の正体 「1棟まるごとオーナー」ならではの可能性とは
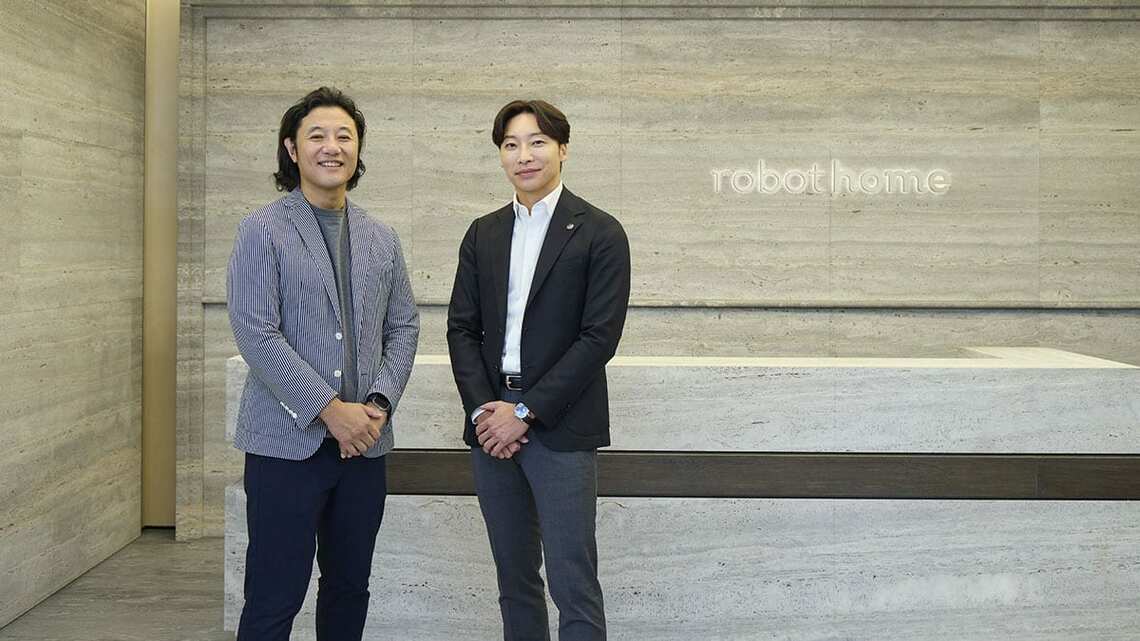
不動産投資市場が注目されている背景とは
入山 現在投資に強い興味を持っています。というのも、若い頃は、どうしてもフローベースで考えるので、投資に対する意識が低かったんですね。ところが、年齢を重ねるうちにストックベースで物事を考えるようになります。それでいろいろと検討しているのですが、やはり不動産投資の重要性に改めて気づいたんです。
理由はシンプルで、まずは、利回りへの期待値が高いということです。そして、東京や大阪など都市圏が持つポテンシャルです。

早稲田大学大学院経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授
古木 おっしゃるとおり、この3~4年で明らかにデフレを脱却し、私どもが管理する賃貸物件の賃料も上昇に転じています。また首都圏の1都3県では、空室率はたいへん低い水準で推移しています。
入山 1都3県への人口流入は減っていませんから、納得できる話です。今後もこの傾向が続くと考えると、まだまだ期待できそうです。
一方で、不動産投資は手間がかかるというイメージもあります。インカムゲインを期待できる一方で、いろいろな心配事が出てきますよね。そしてそもそも、心配事の対応に割く時間がないのが現状ではないでしょうか。

robot home 代表取締役CEO
古木 まさにそれが、エグゼクティブ層に共通するお悩みです。物件の情報収集をはじめ、空室が出た場合の募集といった管理業務や確定申告などの煩雑な事務作業をする時間がありません。
そこで私たちrobot homeでは、オーナーの負担を減らすようテクノロジーを積極的に活用しています。不動産業界でもデジタル化が大きな課題となっていますが、私たちは不動産投資に必要なさまざまな情報を自社開発のアプリで完結させ、収支報告書のPDFを税理士に渡せばスムーズな確定申告ができるようにしています。
さらに、レスポンスのスピードにこだわっています。担当者が不在であってもお問い合わせにすぐに答えられるよう社内のプラットフォームを整備して情報共有を行っているため、アプリ上のチャットから問い合わせをいただいたらすぐにお答えできるようにしています。
「経営」の側面もある不動産投資とは
入山 不動産は大きな金額を投資することになりますので、信頼できるパートナー選びも重要なポイントです。その点、スピーディーなレスポンスはありがたいですね。具体的に、robot homeではどのような物件を取り扱っているのですか。
古木 大都市および政令指定都市を中心に、最寄り駅から徒歩5~10分程度の場所で木造のIoTデザイナーズアパートを提供しています。「1棟まるごとオーナー」という選択肢をご用意し、賃貸経営を一気通貫でサポートしているのが特徴です。
入山 なぜ、「1棟まるごとオーナー」なのでしょう。
古木 1つは、安定性を重視していることです。1部屋だけの場合、退去されたら収入はゼロですが、10部屋あれば1部屋退去しても入居率は90%です。収益の変動を緩やかにできるので、リスクの分散が可能です。
もう1つは、コントローラブルであるということです。区分所有とは異なり、建物全体の所有権を持っているので、オーナーの意思のみでリフォームなどを行うことができます。またほかの投資手法と異なり退去が出たときの賃料や、売却するときの金額なども主体的に設定できます。その意味では、経営に近いといえるかもしれません。
入山 投資には不確実性が伴うわけですが、経営学的にいえば不確実性には「外生的な不確実性」と「内生的な不確実性」の2種類があります。前者は、地政学的なリスクや金融政策の変更など自分でコントロールできないもの。しかし後者は、ある程度自分でコントロールできるわけです。
その視点に立つと、売買を中心に行う投資は、市場の動きという「外生的な不確実性」に依存しがちです。しかし、「1棟まるごとオーナー」だと賃料設定や修繕計画などの収益に直結する判断に関与できるので、「内生的な不確実性」をコントロールしやすいということですね。
IoT住宅が持つ価値
古木 私たちrobot homeでは、エグゼクティブ層向けに、土地の仕入れから開発、管理まで、賃貸経営に関わる専門領域をカバーし、ワンストップでサービスを提供する「1棟まるごとオーナー」のご案内をしています。お客様の中には投資による資産拡大により、人生の選択肢が広がったという方もいます。
入山 まさにそのとおりですね。人生のオーナーシップは自分自身が持つ、ということも大切ではないでしょうか。ところで、空室率は低い水準との話がありましたが、稼働状況はいかがですか。
古木 現在、全国に約2万7000室展開しており、入居率は98.0%です(2025年6月末時点)。とりわけ関東の入居率が高く、約1万室あるうち、空室は20部屋ですから約99.8%の入居率となります。
こうした高い入居率は、きめ細かい入居者対応とIoT導入によるところが大きいと考えています。robot homeは「世界を代表するテクノロジー企業となり、不動産投資を通じて持続可能な社会を実現する。」をビジョンに掲げており、とくにIoTによるDX化には注力しています。
例えば入居者アプリはオートロックやエアコンのコントロールもできますから、オートロックの遠隔開錠により、増加する再配達の課題解決にも役立つでしょう。また、建物の外部にはクラウドカメラを取り付け、不法投棄などのチェックをしています。20代の入居者が多いのは、こうした機能が評価されているからだと分析しています。

入山 これからの賃貸アパートについて、個人的には「エモい」展開があると面白そうだなと思いました。現在、店主の世界観を表現する飲食店に注目しているのですが、そうしたコンセプト型のアパートなんてありですか。音楽好きの人が集まり、気兼ねなく練習することができるとか。
古木 ありだと思います。コンセプトに共感する人たちが集まるアパートであれば、入居者同士がコミュニケーションできるツールを開発して入居者アプリに搭載することもできます。「1棟まるごとオーナー」なので、時代とともに変わるライフスタイルや価値観に合わせて外壁や装飾、共用部の設備を変えることも柔軟にできます。
入山 僕もそうでしたが、投資教育を受けないままに、定年を迎えてしまっている人は多いと思います。経済的に自立していくための選択肢として、投資への理解は深めておきたいですね。
古木 AIの普及によって余暇が増えるという見方もあります。その余暇を充実させ、ウェルビーイングを高めるためにも、資産形成はさらに必要となっていくと思います。その手段の1つとして、不動産投資の中でも「1棟まるごとオーナー」に注目しているエグゼクティブ層が増えているということは、ぜひ多くの方にお伝えしたいと思います。robot homeは、その中でもワンストップの賃貸経営と、特徴あるIoT住宅でオーナーをサポートしていきますので、ぜひご期待ください。
本ウェブサイトに掲載された情報は、その正確性について細心の注意を払っておりますが、万が一、情報に誤りがあった場合や、第三者によるデータの改ざんにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いかねます。また投資にあたっての意思決定、最終判断はご自身の責任でお願いいたします。
株式会社robot home
宅建業免許番号 国土交通大臣(4)第7533号
賃貸住宅管理業登録番号 国土交通大臣(1)第006902号




