未来の産業界を担う人材育成「変革への挑戦」 大学と、教育ビジネスが果たすべき役割とは
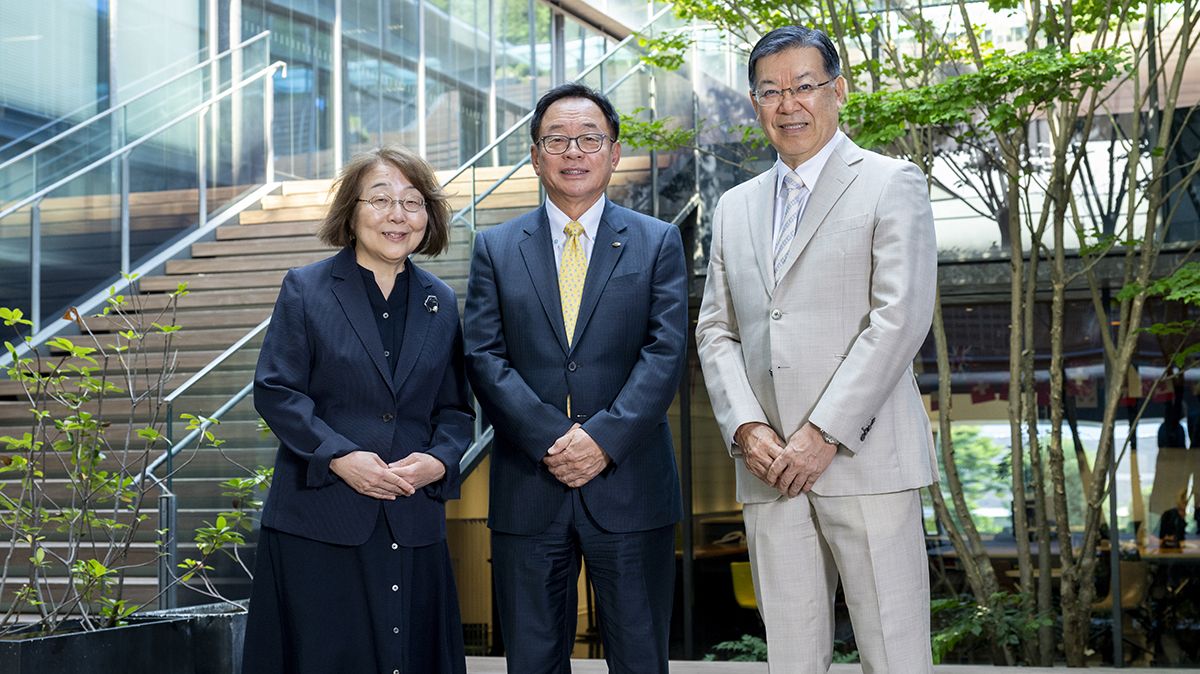
テクノロジーは、教育をどう変えたか
―大学・教育ビジネスを取り巻く環境をどう見ていますか?

学校法人京都産業大学 理事長
山田 啓二 氏
2002年京都府知事就任。4期16年の任期の間、2011年から18年まで全国知事会長を務める。18年知事退任後、京都産業大学法学部教授に就任、24年6月より現職を兼務。
山田 大学を取り巻く社会環境は、急激に変化しています。予想を上回る急速な少子高齢化により大学入学者数は減り続け、いずれ既存の大学の半数は、経営が成り立たなくなるともいわれています。社会構造の変化を踏まえ、高度成長時代の受け入れる大学から選ばれる大学へ、ターゲットの拡大や教育の質の向上、地域への貢献などあらゆる分野で大学のあり方が問われています。
もう1つの大きな変化は、デジタル化です。DXやAIの進展は、人々の働き方や生き方を根本から変えようとしており、教育のあり方も例外ではありません。私たちは前例のない変化の激流の中にいることを自覚すべきです。
花房 当社は、幼児から高齢者まで、幅広い年齢層に教育を展開していますが、子どもの減少は、教育費の減少に直結しますから、危機感は大きいです。絶対数の減少に対し、占有率を上げたり、語学教育にとどまらない多様な教育を提供し、生徒数を確保していく必要があると考えています。
―そうした中でどのような教育課題があるとお考えですか?

ECC 代表取締役社長
花房 雅博 氏
1977年経営学部卒業。米国留学より帰国後、84年講師としてECCに入社。ジュニア事業や法人渉外事業などを担当し、94年取締役に就任。2009年から副社長。21年より現職。
花房 当社は英語を中心とした語学教育を提供してきました。しかし、今や語学を教えるだけでは十分ではありません。当社では、自分で考える力やコミュニケーション力を育む教育に注力しています。単語や文法を教えるだけでなく、文章の内容にまで迫り、成り立ちや文化的背景も理解させることを重視しています。
AIが進化し、今は自分で話せなくても、自動翻訳機能で外国語を理解することはできます。ところが海外旅行に行った人から、「自動翻訳のおかげで会話には困らなかったが、やはり自分で話さなければダメだと実感した」という声を多く聞きます。どれだけデジタル技術が発展しても、人と人とのコミュニケーションは不可欠です。それを育む教育は決して廃れないと信じています。
山田 非常に興味深いお話です。多様な人と触れ合うことなしに、コミュニケーション能力を育むことはできません。オンライン教育も可能になればなるほど、オフラインの大切さが逆に認識されると思います。
本学が全10学部を1拠点に集結させ、「ワンキャンパス」を実現する意義の1つも、そこにあります。幅広い分野やさまざまな人と交わり、複合的に学ぶことで、コミュニケーション能力とともに、オンライン社会にも適応できるプラスアルファの力を身に付けられると考えています。
花房 大学の教育課題についてはどのようにお考えですか。
山田 人口減少社会にあっては、DXやAIを活用しながら1人の人間が複数の役割を担うマルチタスク型人材が求められます。そのため大学も、狭い専門性にとどまらず、幅広い知識と教養を育む教育体系を整備していく必要があると考えています。
ワンキャンパスの利点を生かし、学際的な教育を提供できるよう、本学も変わっていかなければなりません。固定化したカリキュラムを打破し、より柔軟に履修できる体制をつくることもその1つです。学生のニーズに合わせ、複数の学部の専攻分野を履修する「ダブルメジャー」を可能にしていくことも考えています。

―教育課題を解決するため、組織として注力することは?
山田 学部や学問分野の壁を越えて、学内のネットワークを緊密にしていく必要があると考えています。理事長職を担いながら、現在も法学部の教授として教壇に立っていることが、私の強みです。
学生と接する中でリアルなニーズをくみ取り、学生の立場に立って経営や施策を考えようと努めています。創設初期のOBが社会の中枢で活躍している時期にあり、本学は教職員・OBの一体感が強く、それを可能にするポテンシャルがあると、確信しています。
花房 卒業生の1人として、非常に頼もしい言葉を伺いました。母校が新しいことに挑戦する姿を見るのは、うれしいものです。当社は現在、全国に1万を超える教室があります。しかし人口減少が進む中で、生徒が来てくれるのを待っているだけでは、先細ることは目に見えています。そこで「待ちの姿勢」から転じ、「攻めの姿勢」へと打って出ました。
高校・大学、さらに企業、自治体などとの連携もその1つです。大学の語学教育を支援するほか、企業向けに海外赴任前の語学研修を実施するなど、多様な教育プログラムを提供しています。
山田 重要なのは、より多くの教育リソースを学生に提供すること。外部の教育リソースを活用することも一策だと、私は前向きに捉えています。例えば京都では、「大学コンソーシアム京都」を設立し、大学連携にも早くから取り組んでいます。
本学も、京都の文化や伝統産業、最先端の企業に触れながら文化と観光を学んだり、アントレプレナーシップを養うなど、ほかにはない教育の充実を図っています。少ないパイを奪い合うのではなく、共有することで、多様な教育リソースを増やしていける環境が京都で学ぶ魅力につながると考えています。
激変する社会で、真に求められる人材とは
―リカレント教育や生涯教育といった学びの需要に対しては、どのように捉えていますか?
山田 社会が複雑化する中で、働きながらも、今ある力をさらに底上げしていく必要性を感じる人は増えています。社会人の学び直しは、社会との連携の中で初めて価値が出てくる。産学や地域の枠にとどまらず、取り組んでいかなければならないと考えています。
花房 同感です。私も、より高いレベルの力を身に付けたいというニーズは増えていると感じます。当社は、総合教育・生涯学習機関として、幅広い年齢層に多様な学びの機会を提供しています。最近では、AIの実践講座など、専門性の高い講座の需要も高まっています。
―これから産業界に求められる人材とは? そのためにどのような教育を実践していくのか、聞かせてください。
花房 デジタル時代こそ、対面でコミュニケーションを取れる人材を増やしていかなければなりません。当社の小学生対象の英語教室でも、ディベートを取り入れています。また教材や教育法を研究するECCの総合教育研究所では、政治・経済のトピックを取り入れた学習法の開発にも取り組んでいます。
そして何より重視しているのが、コミュニケーションの基盤となる「人間力」の育成です。これからも知識と高い人格を備えた人材を育てる企業であり続けたいと思っています。

山田 総合大学として、高度な大学教育を提供し、「建学の精神」に掲げる「将来の社会を担って立つ人材」を送り出すことが、本学の使命です。本学は、「就職の京産大」と言われるほど、高い就職率を維持してきました。単に多くの人材を輩出するだけでなく、産業界から高い満足・評価をいただいています。
創立以来60年、現実の社会に役立つ人材を育ててきたことは、われわれの誇りです。ここで立ち止まらず、未来に向け、より高いステージへ飛躍していかなければなりません。建学の精神を大切に、これからの時代を生き抜いていける人材を育成する新しい京都産業大学をつくるべく、決意を新たにしています。
Interview/60年の歩みが示す「実績と革新」
―2025年、創立60周年を迎えられました。どのように振り返られますか?
「将来の社会を担って立つ人材の育成」を建学の精神に掲げ、1965年に創立して以来、産業界に役立つ人材を輩出し続けてきました。60年経ち、その成果が目に見える形で表れてきたと思っています。卒業生の中には、経営者になった人や起業して成功した人をはじめ、産業界の多様な分野で一目置かれる存在になっている人が数多くいます。
―2026年度に新たに「アントレプレナーシップ学環」を開設されます。開設の理由をお聞かせください。

京都産業大学 学長
在間 敬子 氏
1984年大阪大学理学部卒業後、民間企業の研究職等を経て、京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)、博士(工学)。2007年から京都産業大学経営学部准教授、11年から教授。教育支援研究開発センター長、経営学部長、副学長を歴任後、24年10月より現職。
社会課題から新たなビジネスを見いだし形にしていく力は、起業する人だけでなく、あらゆる組織で求められています。起業家精神とは、現状をよりよくしようと主体的に考え、周囲を巻き込みながら課題解決に導くマインドセットと行動様式そのもの。今回新設を予定するアントレプレナーシップ学環は「学環」とすることで、学部を横断した科目構成とし、多様な課題に関心を持つ学生に門戸を開きます。
特長の1つが、「セルフ・カルチベーション(自己開拓)」型の演習です。実際に起業や事業化に挑戦し、「失敗しながら」成長していける、実践的な学びを提供します。現実のビジネス現場や起業家に接しながら、起業家精神やイノベーティブな考え方を養い、次代のビジネスを創出していける力を育成したいと考えています。
―同じく26年度、文化学部を再編・強化します。
文化学部に、既存の「京都文化学科」に加え、新たに「文化構想学科」「文化観光学科」を設置し、3学科体制に生まれ変わります。従来から強みだった、京都の文化や伝統産業などに接する学びをさらに強化します。

中でも面白いのが「文化構想学科」です。古典からサブカルチャーまで幅広い文化の領域を網羅するとともに、先進のデジタル技術も学びます。過去の知恵と未来の技術を掛け合わせることで、文化に新たな命を吹き込む。デジタルと人文学を融合し、新しい文化を創造・発信していける人材の育成を目指します。
―60周年を機に大学改革を進められています。とくに教育・研究面の強化ポイントを聞かせてください。
DXの活用とAIエンジニアリング教育推進のほか、産業と結びつく応用分野の拡充や、国内外の地域や企業、教育・研究機関との連携強化を進めます。海外の大学と提携し、新たな教育プログラムをつくることも想定しています。また生涯教育の推進も重要なテーマです。幅広い世代の人が、大学と社会を行き来しながら学べる新しい教育の仕組みを整えたいと考えています。
もう1つが、研究力の強化です。クライオ電子顕微鏡など先進の機器を導入し、生命科学や宇宙物理学・天文学などで先駆的な研究を進めるほか、産学連携も積極的に行います。
重視するのは、多様な人が集まる「場づくり」。本学をハブとして異分野が融合することで、専門分野の壁を越えた、新しい価値を創出していきたいと考えています。これらの取り組みを通して、より多くの新たな産業を生み出す人材を輩出することを目指します。




