東京海上グループ「ブランディングに投資」の狙い 「財務」の視点から見た、ブランド価値とは?

ブランド力を高めることは大切だと考えていても、具体的なブランディング活動をどこまでやるべきなのか、頭を悩ませているマネジャーは少なくないだろう。
LinkedInセールスマネジャーの田代千晴氏は現状を次のように解説する。
「LinkedInのシンクタンクが行った分析(※)によると、ブランディング活動が、『成長』『利益』『リスク管理』の3つの観点から財務的価値に貢献していることがわかっています。また、投資家に対する調査では、約80%の投資アナリストが、ブランドの強さを企業評価で重視していると回答しています。 ところが、米国ではBtoBが経済の約48%を占めているものの、ブランディングやマーケティングにかけられた費用でみるとBtoC向けが75%を占め、BtoB事業向けは約15%にすぎず、大きなギャップがあります。十分な投資を行っていないため、ブランド力を高められていない企業が少なくないのです」
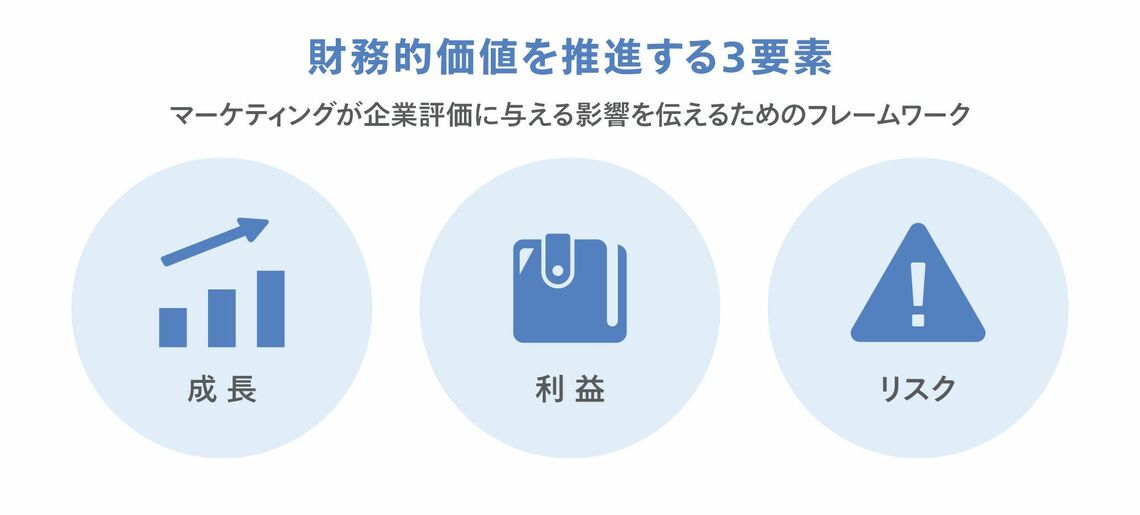
こうした現状においてブランディング活動に積極的なのが東京海上グループだ。常務執行役員でHead of Global Communications、グループ副CFOの石黒大蔵氏は「ブランド投資は長期目線で考えるべき」と指摘する。
「企業価値について、3~5年先であれば財務諸表を分析し、一定予想することはできます。しかし、その先の10年、30年後となると見通すのは困難で、非財務な価値をヒントに探っていくしかない。木に例えれば、地上に見えている部分が財務的価値で、地中の根の部分が将来財務とも言える非財務価値。根を深く広く張らせることができれば、強い幹ができ、未来に花を咲かせることができます。非財務価値にはさまざまなものがありますが、ブランドもその1つです」
企業価値を高める起点は「人」にある
ブランド投資がどうやって花を咲かせるに至るのか。起点になるのは「人」だという。
「働くとき、その価値を金銭的な視点のみで捉えると仕事はつまらないものになります。当社でいえば、目の前の契約を“保険料”として見るのではなく、『これで、お客様の“いざ”という時をお支えすることができる、安心を提供できたのだ』と考える。
そうした、目の前の仕事を尊いと思う、使命感に燃えた社員達をどんどん増やしていきたい。 そして、社員達の想い・熱意が、保険代理店・ブローカー等のパートナーとのさらなる協業につながり、お客様や地域社会にクオリティの高い価値(商品・サービス)を提供していく、課題解決に貢献する。
お役に立った結果として、当社は適正なマージンをいただき、当社自身、利益成長を実現。株主にも還元する。そして、このビジネスモデルを未来(の世代)に向けて継承、進化させていく。

石黒 大蔵氏
このように、すべてのステークホルダーに価値を提供する。これこそが、当社ならではの価値創造であり、この価値創造に、みんなが熱狂する会社・グループ・世界を創りたい。 その旗印、認知がブランドとも言えるし、そのためにも、東京海上グループとして、社内外、一貫したメッセージの発信が大切。足元、『Inspiring confidence. Accelerating progress(次の一歩の力になる)』といった旗印を、グループ・グローバルに掲げ、展開しています」(石黒氏)
「パーパスドリブン」で、仲間を集める
東京海上グループは2000年代以降、海外企業のM&Aを積極的に進めてきた。ここでもレピュテーションや旗印は欠かせない。
「当社にとって、M&Aは目的ではなく、グローバルなリスク分散、利益成長の取り込みといった目的を達成するための手段にほかなりません。実際に当社は、収益性も成長性もあり、それを裏付ける優れたビジネスモデルを有し、何よりも当社とカルチャーが合う、いわゆる“いい会社”を買収してきたわけですが、彼ら彼女らは、買収後も、市場を上回る成長を実現し続けています。
そして、“いい会社”は、何か困難を抱えているわけではないので、一緒になることは決して簡単ではない。その中で、最後はやはり、目指す世界観が同じ、一緒になることでその実現に向けた角度と確度が高まるということが大きなポイントだと思います。その意味では、やはり旗印は大事だと思います」(石黒氏)
M&A後も企業ブランディングは重要だ。東京海上グループは、グループの土台となるブランドの上に、それぞれの会社が現地市場に向けて自社のブランドを使ってマーケティングする戦略を取っている。
グループとして一体感を醸成したり、各社のシナジーを生み出したりするためには、社内外に向けてグローバルとローカルの両方の視点で発信して理解を深めてもらう必要がある。グローバルコミュニケーション部 室長のジェームス・デイ氏は次のように語る。

ジェームス・デイ氏
「米国でM&Aを始めて20年ほど経つので、各社経営層の横の連携はできています。ただ、現場はまだ、同じ仲間の会社がどのような強みを持っているのか全てを把握しきれていない部分もあり、隣の会社の優れた事例などを共有し、知恵が全体に広がっていくことがさらなる成長領域になります」
LinkedInであえて豆知識を発信
これらの情報を届けるために東京海上グループが選んだソーシャルメディアが、BtoBに強いLinkedInである。現在、同社は大きく3つのコンテンツを発信。1つ目は決算や人事などのニュースリリース、2つ目は採用につながる東京海上グルーブの従業員体験情報。そして3つ目が各社のケイパビリティや閲覧者の共感を誘う思想や考え方の発信だ。とくに重視しているのは3つ目の情報で、ときには豆知識情報なども発信しているという。
「津波のときは各自がバラバラに避難する『津波てんでんこ』が生存確率を高めるといった情報は、保険グループとしてぜひみなさんに知っておいてもらいたい情報です。あとは、当社の新本社ビル(建築中)にかかる地鎮祭のコンテンツを上げたら、海外の仲間から反応がよかったですね。実は3つ目のコンテンツは、決算や人事情報に比べると『いいね』の数は少ないのですが、最後までしっかり目を通してもらえる確率が高いです」(デイ氏)
前出の田代氏は、ブランディング活動におけるLinkedInの強みを次のように語る。

田代 千晴氏
「企業にとって重要なステークホルダーである社員と結び付きを持てることが、LinkedInの最大の特徴です。社員に向けた社内コミュニケーションで結び付きが強まれば、社員が情報を拡散して、現在の顧客や将来の顧客候補、取引先などさまざまなステークホルダーへのブランディングも促進されます。LinkedInは、そうした活動について、効果的なターゲット設定・実施、効果測定まで一貫して提供しています」
フォロワー200人から20万人以上に。
広がる東京海上の輪
LinkedInを活用した東京海上グループでは実際にどのような効果があったのか。同社が企業ページをつくったのは2022年。当初はフォロワーが200人程度しかいなかった。しかし、反応を見て文章より動画を増やすなど、試行錯誤していくうちにフォロワー数が増加。現在は約20万人以上まで拡大している。
また、LinkedInページから同社のWebサイトを訪れるフォロワーも多く、エンゲージメント強化に貢献していることもうかがえる。こうした効果が、どう企業価値につながるのか。石黒氏は最後に力強く語ってくれた。

「企業価値については、昨今さまざまな考え方が出てきていますが、当社としては、先ほど申し上げたパーパスの実現、価値の提供に情熱を燃やした社員を起点とする価値創造を、しっかりと『実行』していくことに尽きますし、その結果として、企業価値を持続的に高めていくことができます。
株式市場に対しては、『世界トップクラスのEPSグロースの実現』と『Global Peers水準へのROE引上げ』を標榜していますが、同様に実現し、株式価値も引き上げていけると確信しています」
リンクトイン・ジャパンへの問い合わせ
japan-lms@linkedin.com




