AI時代のCX経営-組織と顧客の未来を描く- 経営と現場を結ぶ「CXフォーラム2025」

協 賛 NTTマーケティングアクトProCX/セールスフォース・ジャパン/トランスコスモス/オプト/RightTouch/テクマトリックス/パーソルコミュニケーションサービス
後 援 公益社団法人消費者関連専門家会議/公益社団法人日本マーケティング協会/一般社団法人日本コンタクトセンター協会/一般社団法人D2Cエキスパート協会/日本ダイレクトマーケティング学会
特別講演
AIで失敗しないためのカスタマーサービス戦略
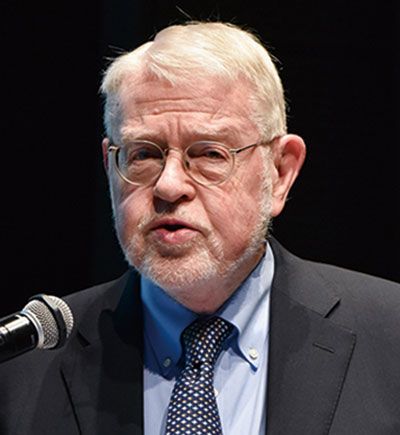
(Customer Care Measurement & Consulting)
Vice Chairman
John A.Goodman 氏
顧客からの問い合わせに対するAIによる自動対応は、迅速な応答ができ、コストも削減できる一方で、問題を解決できないときの顧客の不満・離反リスクが大きいことが課題だ。
そこでグッドマン氏は、オンボーディング(製品利用開始期)のトラブル予防へのAI活用を推奨する。トラブルを事前回避できれば、苦情を申告しない人も含めて顧客の不満・離反を減らせるので、苦情対応よりCX向上の投資対効果は高い。AIで顧客の進捗を管理し、動画や顧客向けアプリなど複数チャネルでアプローチすれば、より高い効果が見込める。それでも問題が起これば、AIで必要なときに必要な情報をジャスト・イン・タイムで提供し、自動対応による問題解決につまずいたら、速やかに有人対応に移行することが重要だ。柔軟な対応ができる権限を与えられたスタッフが、顧客の期待以上のサービスを、AIが把握する適切なタイミングで提供すれば、満足を超える感動体験(ディライト)を創出できる。「リスクを回避しつつAI活用を進めてほしい」と語った。
基調講演Ⅰ
変化の激しい時代に企業価値を上げ続けるための経営者が意識すべきPR・ブランディング

代表
小西 みさを 氏
「ブランドに対する信頼は、企業と社会の共創による長期的な事業成長を後押しする」と、アマゾンジャパンの草創期から広報を担当し、事業戦略と一体となったPR・ブランディングを推進してきた小西みさを氏は語る。
ブランディングは、まず社内に、パーパス(存在意義)、ビジョン(目指す姿)、ミッション(果たすべき使命)、バリュー(行動指針)を浸透させるインターナルブランディングが重要だ。そのために、採用時のブランドに合った人材の見極め、入社時研修での刷り込み、トップメッセージや社内表彰制度を通じたカルチャーの醸成を進める。その後は、広告・パブリシティー(マスメディアへの広報)・ソーシャルメディア・自社メディアを通じて、パーパスに基づく取り組みを対外的に発信し、ブランド価値を向上させる。「ブランドの価値を確立することで、短期的な業績の上下に左右されない、長期的な評価に基づく企業価値が築ける」とした。
ベストプラクティスⅠ
「一歩先ゆく」プロアクティブな企業風土へ組織変革
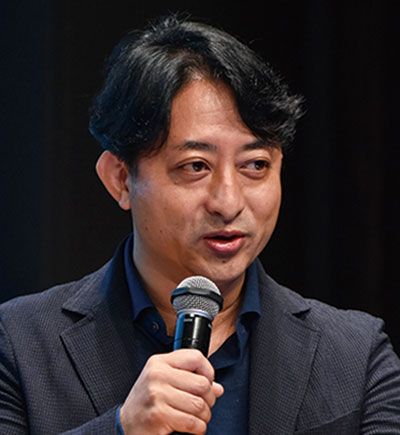
代表取締役社長
石井 智宏 氏
CXに関するテクノロジーやコンサルティングを提供するモビルスの石井智宏氏は、自社のミッション「すべてのビジネスに、一歩先行くCXを。」を実践するプロジェクトについて紹介した。
約1年前にスタート。まずワークショップで作成した痛点の仮説を基に、顧客アンケートでMOT(深刻な痛点)を洗い出した。さらに「社員が主体的に取り組むボトムアップ型で、会社の公式の取り組みとして社内に認知されるプロジェクト体制」を、5カ月かけて設計。士気向上のため、メンバーの評価にプロジェクト参画分を加点して、ボーナスなどで報いる工夫もした。また、VOC(顧客の声)データを継続的に分析・スコア化して課題を把握できる「データがフローするテクノロジーインフラ」も整備した。現在は、第1回プロジェクトチームが、約3カ月の期限で優先順位の高い課題から改善を進めている。「将来は顧客情報との連携で、顧客を先回りする痛点解決の仕組みを目指す」と語った。
ベストプラクティスⅡ
全社変革!BIGLOBEが挑むCX向上のリアル
~経営層から現場までを巻き込んだCX推進~

営業統括本部
チーフ・エグゼクティブ・プロフェッショナル CX
土生 香奈子 氏
インターネットプロバイダーのビッグローブは、2023年の社長交代を機にCXプロジェクトを開始。リーダーの土生香奈子氏は、申し込みや接続設定時に顧客が抱える問題について調査したが、その過程で、一連の業務の流れを知る社員がいないほどの細分化により、顧客に対する社員の意識が低下していることがCX低迷の一因と気づいた。
そこで、社員のCXマインドを醸成する研修を開催。CXを「自分事」として捉えてもらうため、改善すべき点を各自の業務と関連づけてもらい、グループディスカッションを取り入れるなどの工夫をしたところ、受講率98%、約1500件の痛点が寄せられる成功を収めた。さらに、顧客の声を分析して痛点を可視化、減らす取り組みも推進。「コモディティー化した通信業界はCXが重要。痛点削減は、問い合わせ件数、コスト、離反顧客を減らし、収益増につながる。CX向上による経営への貢献も可視化したい」と語った。
基調講演Ⅱ
痺れる戦略

特任教授
楠木 建 氏
ロングセラー経営書『ストーリーとしての競争戦略』の著者、楠木建氏は「競合他社とのさまざまな違いを長期利益獲得に向けてつなげていくのが戦略ストーリー」と語る。企業戦略の多くは、箇条書きになっていることが多く、つながりも単なる取引関係や、シナジーのための複数要素の結合にとどまる。「さまざまな要素がどのようにつながって、儲かるという結果になるのか。ストーリーは時間軸のある順列になる」。
また、儲け続けるには、戦略を他社に模倣されるのを防ぐ障壁が必要だが、より有効なのは「業界の常識に反し、他社が模倣を忌避するような戦略だ」とする。そうした戦略は、一見すると非合理だが、ストーリー全体では合理性があるとして「核心は非合理の中の理にある」と強調した。
スペシャル鼎談
AI時代のCX戦略と組織論を考える
続くスペシャル鼎談は、楠木氏、小西氏、畑中氏が、CX戦略や組織論について語り合った。アマゾンジャパン出身の小西氏は、同社の顧客第一主義のパーパスを実践する仕組みとして、プレスリリース様式にまとめる企画書について紹介。「顧客層や顧客へのメリットに焦点を絞り、市場規模などには言及しない。そうしてニーズを突き詰め、アマゾン・ウェブ・サービスなどを事業化してきた」とした。
「戦略ストーリーにおけるITツールの役割」や「期待した反応を得られなかった場合の対応」を畑中氏から問われ、楠木氏は「ツールは、現実がストーリーのとおりになっているのかを確認するために使うべき。ストーリーがつながらないとわかれば、早期に失敗と判断できる。結果が出るまでずるずる引き延ばさず、小さく、早く、はっきりと失敗することが大切だろう」と語った。
パネルディスカッション
CXを取り巻く環境と推進のカギ
~新しいサービスの❝カタチ❞を探る~
CXソリューション部 CXデザイングループ エグゼクティブ・プロデューサー
井上 賀友 氏
理事 CX事業統括 アナリティクス本部 本部長
トランスコスモス・アナリティクス
代表取締役社長
北出 大蔵 氏
執行役員 CMO
井上 雅博 氏
CXにおけるAI活用や、コンタクトセンターのオペレーターらによる有人対応の今後のあり方を議論した。最初にファシリテーターのラーニングイット井上雅博氏が、商品・サービスの利用で問題があったとき、顧客は自己解決を図る「セルフサービス」のための接点を利用する割合が高いとする調査結果を示し、「今やセルフサービス手段の提供は当たり前になっている」と提起した。
NTTマーケティングアクトProCXの井上賀友氏は、有人対応に比べ、提供時間などの制約がないセルフサービスはできるだけ進めるべきとしたうえで、カスタマージャーニーを可視化して「問題が解決できない顧客を救済する有人対応の導線を検討すべき」だと語る。
トランスコスモスの北出大蔵氏は、約半数の消費者は、事実と異なる回答を生成するなどのAIの問題を知ったうえで、自己解決手段を求めているというデータを紹介。「AI単体ではなく、カスタマージャーニーを含めた全体でCXを評価することが大事」とした。
セッション
事業戦略に基づくCX設計の要諦

CXソリューション部
CXデザイングループ
エグゼクティブ・プロデューサー
井上 賀友 氏
「予算などの制約もある中で、必ずしも最高のCXを目指す必要はなく、ブランドへの期待を満たすための"最適"なカスタマージャーニーと顧客満足を設計することが重要」と、コンタクトセンター運営受託を含むCX最適化を支援するNTTマーケティングアクトProCXの井上賀友氏は語る。
まず、問い合わせが生じないような商品作りを目指し、問題が生じても自己解決しやすいサポートを提供。解決できない場合に備えたラストリゾート(最終手段)としてカスタマーセンターを置くカスタマージャーニーを設計する。次に、CX指標と、収益に関する業績指標、解決率などの業務指標との相関性を把握。CX指標向上による業績への貢献、CX指標向上に有効な業務改善を可視化する。CX最適化に向けては、生成AI、VOC分析を活用して「組織の境目などで分断されない、シームレスな顧客体験『CXフロースルー』実現を支援したい」とアピールした。
セッション
CX改善の「守・破・離」
~コミュニケーション体験スコアのティア表上位優良企業から学ぶ~

理事 CX事業統括
アナリティクス本部 本部長
トランスコスモス・アナリティクス
代表取締役社長
北出 大蔵 氏
アウトソーシングサービスを提供するトランスコスモスでCXを調査してきた北出大蔵氏は「まず目的を明確にして適切なCX指標を定義すべき」と訴える。顧客とのコミュニケーション体験を改善したい場合、商品力などほかの要因の影響も受ける顧客満足度では、分析が難しくなるため、コミュニケーションに特化した同社独自のコミュニケーション体験評価指標の利用検討も提案する。
CX評価は、サポート窓口への問い合わせ前に試みる自己解決の成否も重要なため、その分析は、顧客接点だけでなく、カスタマージャーニーを広く見渡して、決定的に重要な「真実の瞬間」を捉え、競合と比較して自社のCXの強みと弱みを把握することが重要だ。CX改善は、CXスコア上位企業からAIやVOC活用の先進施策を含めて学んで、弱みを克服し、強みを磨く。「他社を参考に自社の手法を確立するCXの取り組みは、武道・芸道の『守・破・離』に通じる」と語った。
セッション
高LTV・高ロイヤルティを
醸成するデータドリブンなCX

CXコンサルティング部
部長
清水 啓介 氏
顧客データの活用により、CXを改善しながらLTV(顧客生涯価値)を向上させる、LTVM(LTVマーケティング)のコンサルティングを提供するオプトの清水啓介氏は「CX活動は成果が見えづらく、頓挫しがち。CXとともにLTVを向上し、収益も伸ばせる持続的な事業成長を支援する」と語る。
LTVMでは、経済ロイヤルティ(購入額)、心理ロイヤルティ(ブランドへの忠誠)がともに高い関係を築き、継続して選ばれ続ける関係を育む。まず、LTVとの相関が強い次回利用意向などの心理ロイヤルティ指標を設定。その指標への影響が大きい顧客接点、体験因子を特定する。さらに、経済・心理ロイヤルティの高さなどに応じてセグメント分類。顧客の関心度に合ったカスタマージャーニーの設計、CX改善を行う。そのためのツールとして、オプトは、分析機能等を備えたAI搭載の顧客データプラットフォームなども提供している。
セッション
AIによる顧客理解の最前線
~顧客接点のパーソナライズを加速するAI戦略~

代表取締役
野村 修平 氏
顧客体験の価値が高まる一方で、カスタマーサポートの現場ではリソース不足が深刻化している。「オペレーターに問い合わせる前の段階で、いかに自己解決できる顧客体験を設計できるかが重要。生成AIはそれを加速する"銀の弾丸"になりうる」と、カスタマーサポートプラットフォームを提供するRightTouchの野村修平氏は語る。
まずAIが活用される土台として、社内に点在する企業ナレッジのデータ整備が不可欠。そのうえで、AIに任せられる業務と人が担うべき業務を明確に分担し、体制を構築。顧客との接点の中でも、期待値のコントロールがしやすいWebサイト領域を「実証の最初の場」と捉え、生成AIを活用したチャットや音声での自動応対を展開。これにより、FAQによる自己解決や、適切なチャネル・オペレーターへの誘導を実現している。「弊社はカスタマーサポートデータとAIを使って人の価値を最大限に引き出す仕組みをすでに構築している。人と共創できるAI活用を推進すべきだ」と訴えた。
セッション
CX新時代
~コンタクトセンターにおける生成AI活用の新たなステージ~

CRMソリューション
営業第3部 部長
松木 健太郎 氏
ITサービス企業、テクマトリックスが実施した今年のコンタクトセンター意識調査では、生産性向上の課題感と生成AIへの関心の高さが顕著だった。松木健太郎氏は、オペレーターにつながる前に顧客が通話を終了する「放棄呼率」上昇のデータを示し「日本のコールセンターは、つながりにくくなっている。CX新時代の課題解決には、生成AI、デジタルチャネルがカギ」と語る。
最新CXソリューション「Fast Series」は、デジタルコミュニケーション機能を拡充。ナレッジシステムで適切に管理されたナレッジを使い、生成AIの回答精度を高め、オペレーターをサポートする。通話内容はAIで自動的にテキスト化、要約され、CRM(顧客情報管理)システムに登録。ナレッジ候補のQ&Aも自動抽出してFAQを充実させる。「弊社のAIの特徴はCRM・ナレッジシステムとの緊密な連携。オペレーターの手間を大幅に削減できる」とした。









