日本企業のポテンシャルを解放するデジタル戦略 SAPジャパン鈴木氏×BCG佐々木氏が対談
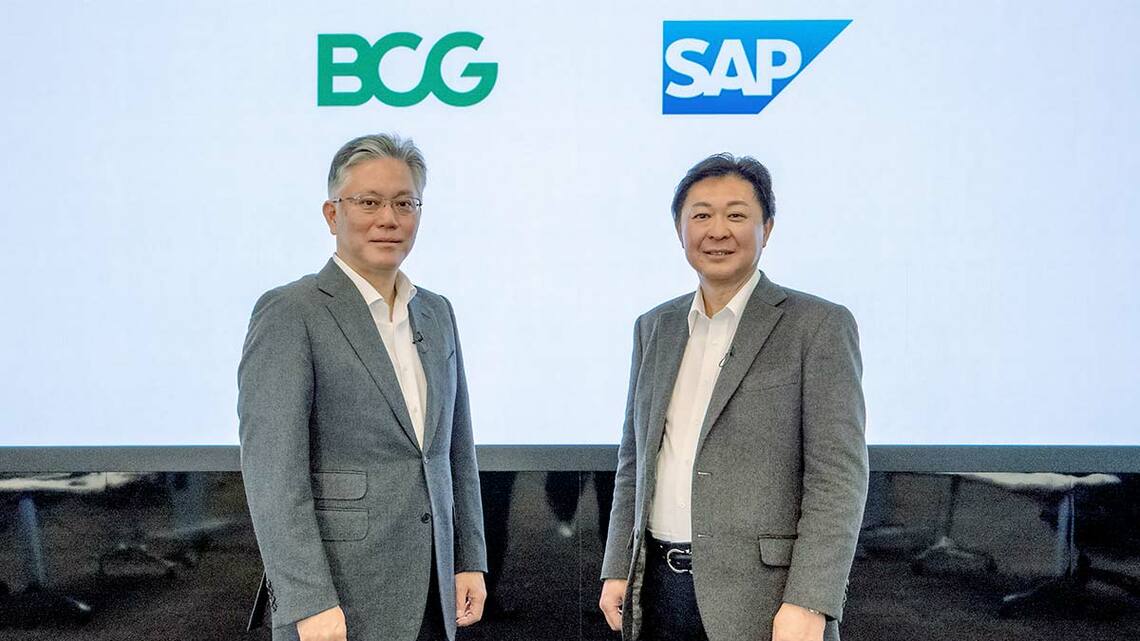
定型業務を標準化する
佐々木 急速な少子化で、今後、人手不足はますます深刻化します。生産性の向上が求められますが、現状をどう見ていますか。
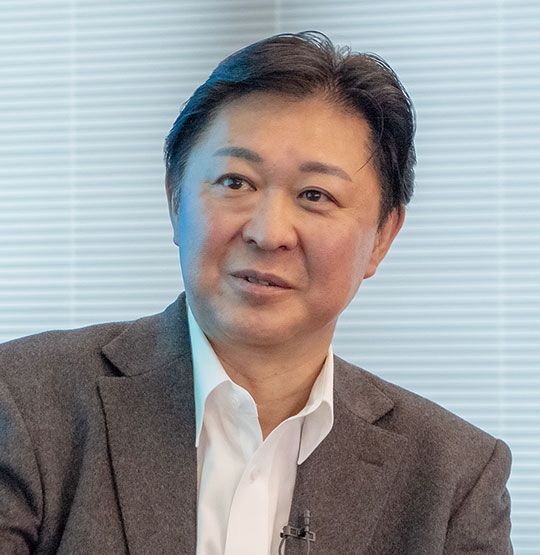
代表取締役社長
鈴木 洋史 氏
鈴木 私どもは、30年以上にわたってERPと呼ばれる統合基幹システムを提供してきましたが、思った以上に生産性が上がっていないというのが実感です。業務をシンプルにするため、世界標準の業務プロセスに合わせたERPでBPR(ビジネスプロセス再設計)のご支援をしているわけですが、導入に際し、現場の抵抗もあって、従来の業務のやり方を変えられないケースが少なくありません。結果として生産性が上がらないのはもちろん、システムに個別のカスタマイズが増え、維持・管理するコストがかさみ、データを一元管理するのも難しくなります。
佐々木 一方で、日本企業の強みは「現場力」にあります。この強みを生かしつつ、業務の標準化を実現するにはどうすればいいのでしょうか。
鈴木 現場力の強い部分と、標準化すべき部分をしっかり切り分けることが重要だと考えています。とくに定型業務は、個別のやり方を踏襲するのではなく標準に合わせるべきです。SAPでは「クリーンコア」戦略として、定型業務を担うコアの部分はクリーンに保ち、非定型で競争力に関わる業務を拡張機能として連携させる仕組みを提供しています。
佐々木 確かに日本企業は、戦略を構築する際にも、どこで競争するかの切り分けを苦手にしている傾向があります。
鈴木 日本はIT・デジタルというとコスト削減の側面が重視されがちでしたが、ビジネスの成長を支える基盤ですから、ビジネス戦略に沿ってIT・デジタル戦略を構築し、実行しなくてはなりません。IT部門に任せっ放しにせず、トップ主導で戦略的にプロジェクトを進める必要があります。
丸投げしない姿勢が大切
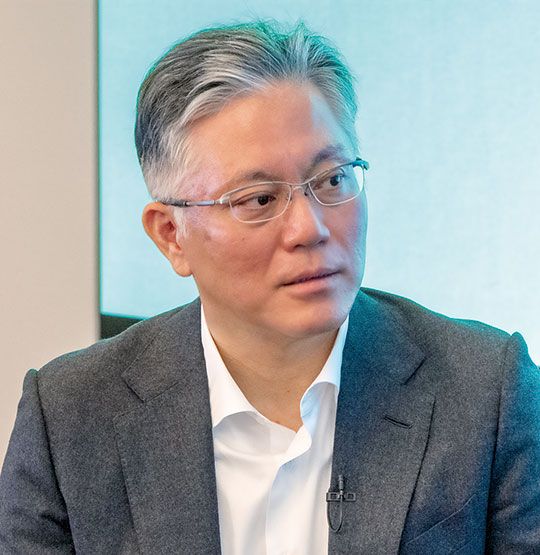
アジア・パシフィック会長
佐々木 靖 氏
佐々木 業務の標準化とともに、IT・デジタル人材の育成も急務だと考えますがいかがでしょうか。
鈴木 同感です。人材育成の際は、テクノロジーとビジネス双方の理解を促すことが大切でしょう。各現場の方々が、IT・デジタルのテクノロジーを熟知する方々と議論を重ね、お互いをよく知ることも非常に重要です。変化にやや慎重な企業文化の場合はSIerやBCGさんのようなコンサルティングファームをうまく活用して、ノウハウを吸収することが効果的でしょう。ただ、「丸投げ」にならないよう注意が必要です。
佐々木 しかし、とりわけIT・デジタルの取り組みでは「経験がなく知見を持つメンバーもいないからすべて任せてしまいたい」という気持ちになる企業も多いと思います。どうすればいいのでしょうか。
鈴木 例えばERPの導入で私どもを採用いただく場合、先ほど申し上げたように「定型業務はコア機能に合わせる」ことが有効です。重要なのは、現場に非定型業務を洗い出させ、それが経営戦略上必要なのかトップが意思決定を下すことです。そういったガバナンスを利かせることで、自ら取り組む姿勢が保てるのではないでしょうか。
佐々木 ガバナンスは非常に重要ですね。私たちは「ITデジタル勝利の方程式」として「10:20:70の法則」を提唱しています。10%はアルゴリズム、20%はその活用基盤となるデータ、残る70%はチェンジマネジメント、つまり人の行動をどう変えていくかが勝利を決定づけるバリューの源泉だという考え方です。行動をどう変えていくか、SAPさんやSIer、われわれのような第三者も入って検討していくのも有効ですね。
AIエージェントの時代
佐々木 昨今、AIの進化も目覚ましいものがあります。鈴木さんはAIのインパクトについてどうお考えでしょうか。
鈴木 業務効率化はもはや当然で、AIの活用によっていかに価値を創出し、競争力を強化するかが求められていると思います。SAPでは、AIが自ら意思を持って行動するAIエージェントを業務プロセスの中にすでに組み込んでいます。販売のAIエージェントが需要予測を行い、供給のAIエージェントがどれだけ供給できるか分析し、生産のAIエージェントが生産計画や調達計画を立て、全体の会計を会計のAIエージェントが把握する。これらすべてが連動し、自動化する世界が目前に来ています。
佐々木 そうした世界をいち早く自社で実現するにはデータが重要だと思いますが、どのような点に留意すべきでしょうか。
鈴木 まず、クラウド基盤が必要です。クラウドでデータを一元管理することでAIを最大限に活用できるからです。そして、アプリケーションと連携することで、必要なタイミングで経営の意思決定に役立つ情報が得られるようになります。その発想で「SAP Business Data Cloud」を開発しました。実際、SAPはすでに事業計画の策定から目標値に対する着地見込みまで、AIが予測しています。われわれ人間は、それをどこまでストレッチさせられるかに知恵を絞っています。
佐々木 AIが機能する環境を整え、さらなる成長のために知恵を絞る。こうして企業のポテンシャルを引き出し、成長戦略としていく時代になったといえそうです。
⇒ボストン コンサルティング グループの公式サイトはこちら
[対談全編を動画で配信中]
⇒【前編】生産性を高めるには業務の標準化が大切
⇒【中編】「丸投げしない」姿勢がIT人材を育てる
⇒【後編】AI・アプリ・データの3層が競争力の源泉




