生成AIの進化が日本企業にチャンスをもたらす 注目スタートアップのCTOが直言するAIの未来

生成AIの進化はこれからが本番
AIの進化の歴史を、Edwin Li氏はこう俯瞰する。
「広い意味でのAIは1960年代から研究が始まり、その後何度かの技術革新によるブームがありました。1つの技術が出てくると、その進化が急速に進み、一段落すると、ブームが終息するということを繰り返してきました。前回の技術が進化しきった2022年に登場してきたのが、現在大きな話題を呼んでいる生成AIです」

株式会社FLUX 取締役CTO
Edwin Li氏
東京大学工学系研究科修了(松尾研究室)。中国英語翻訳者資格最年少記録保持者(同社調べ)であり、学生時代には中国国内にて数学・天文学・物理学・化学オリンピックで優勝。ケンブリッジ大学コンピューターサイエンス学部に特待生で進学(中国全土で年間3〜5名が選ばれる特別選抜プログラムASTに選抜)。東京工業大学(現・東京科学大学)工学部卒業。機械学習、深層学習、大規模言語モデルが専門
Li氏は、今回の生成AI技術は、まだ進化の序盤だとみている。
「AIの3大要素は、『アルゴリズム』『学習データ』『計算能力』です。このうちAIの計算に使用されることで知られる半導体は、1年程度でバージョンアップしていますが、世代が変わるごとに10倍以上の性能向上を実現しています。これを見ると、生成AIの進化はこれからも続くと考えられます」
データについても、そのままではAIに使うことができなかったが、生成AIの時代になり、データを取り込めば取り込むほど精度が向上することが明らかになっている。
「例えば、『PCの操作方法ビデオ』のような、これまでは活用できなかったデータも生成AIに学習させることができます。人間の動作をまねるAIが注目されており、にわかにそうしたデータの需要が拡大しています」
逆の動きもある。限られた計算資源でも高い精度が得られるAIモデルの登場だ。なぜそうしたことが可能になるのか。Li氏はこう説明する。
「世の中に初めて登場するような生成AIモデルは、従来のモデルを上回る精度を目指して開発が進んでいます。いわば未踏の領域であり、暗闇の中を模索するため、莫大な開発費がかかります。しかし、いったん成果が披露されると、開発のテーマは一変します」
例えば、ある生成AIの最新モデルで達成された性能がわかれば、それがいったん目標として設定され、どうすれば途中の工程を省いて目指す性能を出せるか、エンジニアリングの領域へと開発の焦点が移るというのである。エンジニアリング領域では、一定の性能を安く、シンプルに実現することがターゲットとなる。しかもオープンソースであることも注目に値すると続ける。
「未踏の性能を目指すビッグテックと、その成果をエンジニアリングで効率よく実現するスタートアップによる2つの方向性で、生成AIはまだまだ進化していくと考えています」
日本企業の膨大な仕事の記録がDXの突破口になる
AIがこれ以上進化すると、人間が不要になるのではないかという懸念の声も聞かれる。しかしLi氏は、それを否定する。
「どれだけ進化しても、AIは人間のアシスト役という基本は変わりません。仮に、あるサービスの9割をAIが担っても、最終的に『良しあし』を判断するのは人間でなければいけません。そのサービスの提供を受けるのは人間であり、人間の好みや感性を100%AIにコピーすることは不可能だからです」
ただし、そうした人間の感性的な領域以外の大部分は、AIが代替する世界が目の前に来ている。
すでに欧米や中国などでは、ビジネスでのAI利用が当然のこととなっていると、Li氏は指摘する。
「とくに米国など海外のテック系企業では、エンジニアのプログラムコード作成などの大部分が、すでにAIに取って代わられています。一般のビジネスにもAI利用は当たり前になっていますが、日本もすぐに同じことが起こるかというと、私はそうは思いません」
なぜか。欧米や中国などでは新しい技術がよいとわかれば即座に企業が飛びつき、使い倒す文化があるが、日本は逆に、確信を得るまでは従来の技術を引き続き使い続け、置き換えるほうが明らかによいとわかった途端、一気に広まる傾向があるのだという。日本は今後3~5年は、AIに対して現在の状況と大きくは変わらないというのが、Li氏の見立てである。
日本の企業では当面、AIをビジネスに直接使うよりも、以前より後れを取っていたDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するためのデータのデジタル化に、生成AIの能力が生きるはずだとLi氏は話す。
「日本の業務プロセスをデジタルで標準化することが困難だった背景の1つに、マニュアルや日報、報告書といった紙ベースの記録など、膨大な非定型ドキュメントの存在があります。私から見ても、日本企業は記録を取るのが好きだと思います。それが今、これまで何十年も蓄積された業務の記録を、生成AIの進化によって容易に取り込むことができるようになったのです」
前述したように、オープンソースの低廉な生成AIの性能が向上し、基本的な知識ベースを学習させる必要がなくなった。そのAIに、自社が蓄積してきた膨大な仕事の記録を追加学習させることで、ほかにはない企業独自のAIを作ることができる。
「それまで、日本企業の生産性向上を阻害していた1つの要因でもある、さまざまな業務プロセスについて逐一ドキュメントに残すという習慣が、ここにきて重要な意味を持つようになったのです」
このデータこそが、日本企業の新たな競争力となる可能性を秘めていると、Li氏は強調する。
「先ほど触れた『アルゴリズム』『学習データ』『計算能力』というAIの3要素のうち、ビジネスの差別化につながるものはデータしかありません。世界の企業では、品質の高い業務データを求める競争が始まっています。日本企業が蓄積した業務データにも熱い注目が集まっているのです」
日本企業もその価値に気づいているため、簡単には手放すことがないそうだが、自社のデータの価値に気づくことが、DXを推進する1つのカギともなりそうだ。
AI時代に必要な対人コミュニケーションスキル
一方、企業がAIを活用する際に、懸念材料として挙げることが、AIそのものの信頼性とセキュリティーである。「もっともらしく不正確なことを言う」、ハルシネーションといわれる問題、あるいは学習させた社内データが外部に流出する可能性などが指摘されている。Li氏は、リスクを正しく認識したうえで積極的に使うべきだと話す。
「例えば、公開情報に基づく利用や、一般的な相談事などで使用する外部のAIサービスと、絶対に外部に漏れてはいけないデータを学習させるのは自社開発のAIと切り分けるなど、データの安全性を重視した運用が重要となります」
その一方で、AIのリスクを正確に把握せず、必要以上に恐れたり、「様子見」を決め込む企業も依然として存在するだろう。仮に、AIを使わない方針の企業がそれを続けた場合、どうなるのだろうか。Li氏はこう話す。
「ビジネスにAIを活用するという大きな流れは、変わることはないでしょう。いずれは、使うことになるのです。そのとき、出遅れた代償は思いのほか高いコストとなる可能性があります。現状では、生成AIツールの機能はまだシンプルで、覚えることがそれほど多くありません。今のうちから使い始めるほうが、後から一気に習得しようとするよりも時間も労力も少なく済みます」
これからのビジネスパーソンは、AIと共存し、連携していかなければいけない。
「AIは人間の指示によって動きます。つまり、AIにいかに適切な指示を出せるか、それがこれからのビジネスパーソンにとって極めて大事な能力になります」
AIを使いこなす、というと、AIが答えやすい指示の言い回しなど、テクニカルな話に思われがちだが、そうではないとLi氏は言う。
「先進的なAIは、人間から指示された内容の真意は何か、推論する能力を備え始めています。ですからなまじ言い方だけを整えても、AIが深読みしすぎて、ミスリードになりやすい懸念があります。むしろ、人間に対して話すときと同じく、しっかり論理立てた構造の文章で伝えることが大事だとわかってきました」
AI時代のビジネスパーソンには、より対人のコミュニケーションスキルが要求されるというから、面白い。
AIの本質を知るからこそAI前提でない支援ができる
AIのエキスパートであるLi氏がCTOを務めるFLUXは、AI時代における企業の戦略パートナーとして、AIトランスフォーメーションを推進するスタートアップ企業である。
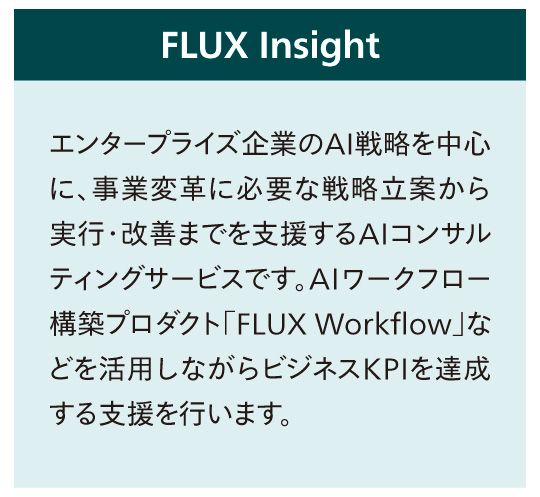
2025年6月には累計資金調達額が100億円に到達する新たな44億円の資金調達を発表した。昨今、同社には、AI活用についての相談が多数寄せられており、企業の期待の高まりを感じているという。
しかし、Li氏はAIに対して過剰な期待を持つ企業が多いとも指摘する。
「現在のAIに100%の精度を求めることは早計です。AI導入ありきでスタートすると、うまくいきません。大事なことは、自社が求めるレベルに対して今のAIは何が足りていないのか、判断基準を持つことです」
FLUXでは、AIの限界を見極めたうえで、顧客が保有するデータでどう補っていくのか、対話しながらアプローチを探っていく。その結果、数々のAI活用プロジェクトを成功に導いている。
AIは企業の成長に不可欠なツールとなるだろう。ただし万能ではないから、上手に扱い、味方にしていかなければいけない。専門家集団のFLUX自身も、ビジネスのためのAI活用の道筋を探求し続けている。




