「事業変革につなぐ」AI活用で勝機を得るには 3つのボトルネックを乗り越える具体策とは?

日本企業が抱える「3つの重大課題」
――日本企業におけるAI活用の現状と、抱えている課題についてどのようにみていますか。
首藤 生成AIを導入している企業はかなり増えました。しかし、本質的なビジネス変革が進んでいる企業は残念ながらごく一部です。その大きなボトルネックはいくつかあります。
1つは、PoC(概念実証)ばかりで変革が進んでいないことです。生成AIの導入による意義を見いだそうと、あまりコストをかけずに多数のPoCを推進する企業が多いです。しかし、適用するユースケースが狭いために肝心のROI(投資利益率)を把握できず頓挫してしまうケースをいくつも見てきました。
もう1つは、データ基盤の整備が進んでいないことです。そもそも、質量ともに十分なデータがなければ、AIから業務にインパクトのあるアウトプットを引き出すことはできません。
構造化データだけでなく、社内に散在しているテキストデータや音声、画像などの非構造化データまで活用に向けた整備に取り組むべきですが、そこまで進んでいない企業が多いのが現状です。

首藤 佑樹 氏
大山 当社が実施したアンケート(※)によると、経営層の多くが「AI活用には、データ整備の投資を伸ばさなければならない」と考えていることがわかっています。すなわちデータの重要性は理解しているわけです。
しかし、現時点で日本企業が業務システムで管理できているのは構造化データがほとんどです。これは、推論型や予測型のAIには有効ですが、その進化型である自律型のAI(AIエージェント)には不十分です。AIエージェントが人に代わって役割を担う中で伴う判断には、ノウハウや暗黙知のような非構造化データが必要になります。
経営者自身が非構造化データ整備の重要性を理解し、AIエージェント活用による効果を見いだすことが求められています。
首藤が解説した2つに加え、3つ目のボトルネックとして、AIに対する認識が「便利なツール」にとどまっている現状があると思います。デロイト トーマツでは、生成AI技術の研究・開発やプロジェクトへの展開、ノウハウの集約・モジュール化などを進め、各AIベンダーとのアライアンスを強化してきました。
その過程で見えたのが、「多くの企業が、AIを単なるITツールと認識している」現状です。AIを人に代わるワークフォースと捉えて、労働力不足やベテランの退職など、経営課題のソリューションと考えること。
この意識改革こそが今、経営者に突きつけられている課題といえるでしょう。
※出所: デロイト統合研究センター「 Deloitte’s series on the state of generative AI in the enterprise 」(2024年5月29日 )
ITシステム構築の「外注」が生んだ、海外との差
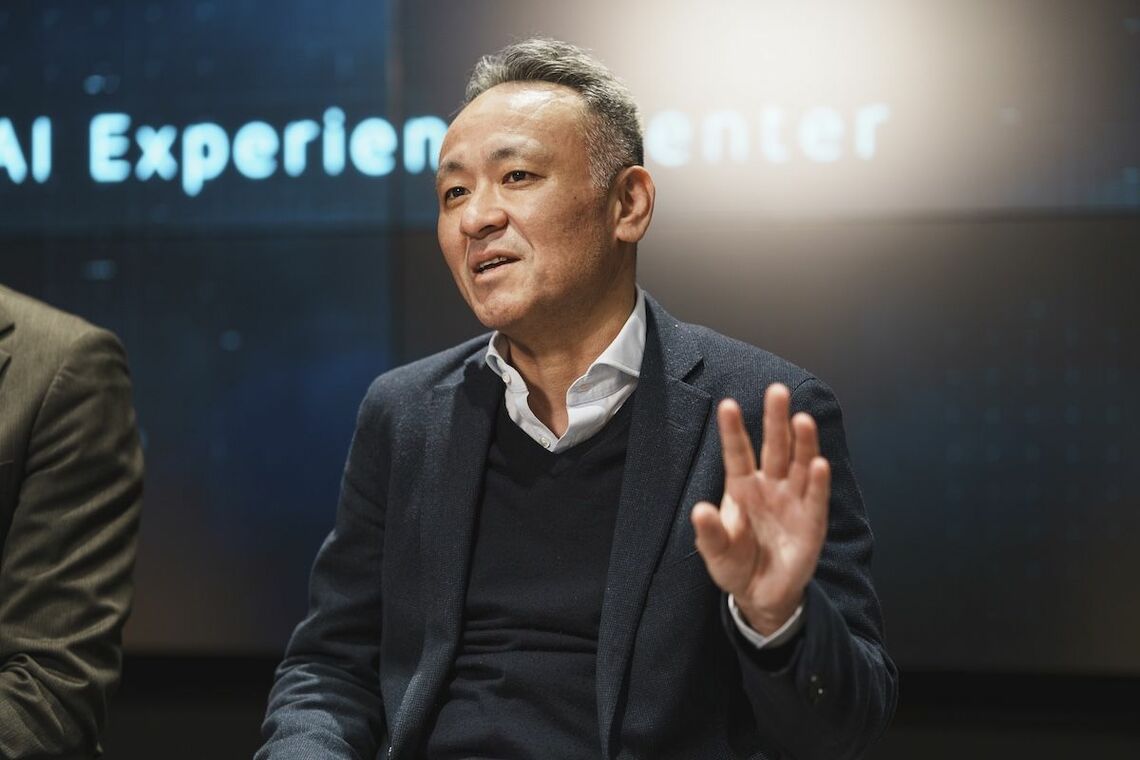
大山 泰誠 氏
平井 日本企業がAIを便利ツールとして捉えてしまう原因の1つは、ITシステムの構築を外注してきたことです。社内に情報システム部門はあっても、自分で企画から考えてシステムを構築してきた経験を持つ人が少ないのです。
そして、デジタルの経験を積み知見を磨いてきた数少ない人材は、ビジネスを考える立場にありません。プログラミングを駆使する人材が経営層にいる海外企業との差は、ここにあります。経営層は、AIを中心に据えた経営を考える必要があります。
私の担当する自動車業界では近年、ソフトウェアのアップデートによって商品の販売後もプロダクトを進化させていく「ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)」という考え方が注目を集めています。さらに海外では今「AI・ディファインド・ビークル」という言葉を用いるメーカーも出てきており市販化も始まっています。
すでに世界では「AIを軸としたビジネスをどう展開するか」という競争環境となってきているんです。

平井 学 氏
大山 AIに対する投資は、海外と日本で大きく差があります。とくに米国は桁違いですから、このまま数年経てば、日本は到底追いつけなくなってしまいます。すでに、米国のマーケットはかなり先を行っており、さまざまなAIエージェントサービスを提供するベンチャーが増加しています。
例えば政府機関に提出する書類を自動生成するAIエージェントサービスなどニッチな領域もあり、マーケットとして成熟しているのを感じます。日本にもAIエージェント提供ベンチャーが増えることを期待しています。
変革をドライブするのは「CxO」が描くイメージ
――海外からの遅れを取り戻して競争力を高めるために、経営層はどのようなマインドセットを持つべきでしょうか。
首藤 まず、経営者や役員つまり「CxO」クラスが具体的なイメージを描かなければ、事業変革は進まないということを理解する必要があります。新技術に慣れている現場の若手だけ活用して個人的に生産性が上がっても、それだけではPL(損益計算書)にはヒットしません。
また、既存の意思決定方法や業務を維持することを前提に、AIの活用方法をいくら考えても、効果的なアイデアは出ないでしょう。
そこで発想を一度真逆に振って、現在の方法をすべてAIに置き換えて考えてみることをお勧めします。そうすれば「この業務をAIで自動化したり、精度を上げるにはどんなデータをそろえる必要があるのか」「人間による承認・レビューはどのタイミングで行えばいいか」といった議論ができます。人間にしかできないこと、人間だからこそ価値を出せる業務もあぶり出されてきます。
大山 企業は、製造や営業、バックオフィスなど、数々の部門の機能で構成されています。企業全体を機能の塊として捉えることで、「どの部分(機能)をAIで置き換えられるか」を見極めやすくなります。そうすることで効果の試算も、経営課題とのひも付けも、スムーズになるでしょう。
あとは、体験することが大切です。AIを使うと何ができて、どんな課題が解決できるのかを明確にイメージできないと、経営戦略に落とし込むことはできません。生成AIに少し触れるだけでなく、社内のさまざまなデータを活用するとどんな世界が広がるのかを肌で理解しておく必要があります。

平井 AIはある意味「器」です。料理と同じで、器に何を入れるかで差が出ます。つまり、どんなデータを読み込ませて、どんなプロンプト(指示)を出すかでアウトプットが変わるんです。
大げさな話ではなく、AIのビジネス活用は早晩スタンダードになります。そうなる前に自社独自の味を出せないと、競争に参加できません。「失われた40年」に突入しようとしている現状から脱するためにも、早急にAI活用と事業変革のスタートラインに立つ必要があります。
共創型AI体験施設を東京・丸の内に開設
――そうした世界を目指し、デロイト トーマツではどのような施策を展開しているのでしょうか。
首藤 経営者が変革のイメージを膨らませるためには、実際にシステムが動く様子を見たり、手で触れたり、社外の人と意見交換したりすることが大切です。
そこでデロイト トーマツでは、2025年1月に共創型AI体験施設「Deloitte Tohmatsu AI Experience Center(AEC)」を開設しました。業界をリードするテクノロジー企業各社とアライアンスを組み、先端テクノロジーを体験できる場所にしました。
さまざまな領域のユースケースを用意し、クライアントの課題を事前にヒアリングします。そのうえで、その企業に合ったAI変革を、ストーリーとして体験できるように工夫しています。
平井 CxOの皆さんには、AECを通じて社外と有機的につながり、共創することでイノベーションの創出につなげていただきたいです。他業界も含むさまざまな企業と触れ合い想像を膨らませることで、変革に向けた具体的なイメージを描くことができるでしょう。
クライアントに「代わりにやります」とは言わない

――企業が変革のスタートラインに立つために、デロイト トーマツが果たせる役割について教えてください。
首藤 企業のAI変革は、社員が個々人でAIを使いこなすといった狭い範囲の話ではありません。AIを活用しながら新しい価値を創造したり競争優位を築いたりして、抜本的な経営変革をすることです。
そして、抜本的な変革には、複雑で解きづらい課題を解決する力が不可欠です。テクノロジーはもちろん、戦略策定からオペレーション、人材育成まであらゆる経営課題に対応できるのがデロイト トーマツの強みです。
そうした幅広いノウハウと、各インダストリーの専門チーム、さらに専門家のグローバルネットワークもあり、クライアントが抱える課題に合わせた柔軟な体制で支援しています。
大山 多様なサービスと専門家の組み合わせに加えて、デロイト トーマツは自らAI変革に取り組んできました。その1つとして社内AIを全社展開し、全員がプロンプトのスキルを向上させたのです。その結果、AI変革のイメージをより明確にクライアントへ伝えられるようになったと自負しています。
平井 私たち自身が、AIを使いこなす効果を実感できているので、本質的なチェンジマネジメントを伴走支援できるのです。
私は、クライアントに真の変革を促すうえで、コンサルタントがいちばん言ってはいけないのが「私たちが代わりにやります」だと思っています。システム開発を外部に依存し、使いこなし方がわからない状態を放置してきた企業は、たとえ大変でも、自走化しないと強くなれません。そこにコミットするのが、当社の支援です。
首藤 AIの進化によって、人間力が問われる時代がやってきたと感じています。コンサルティング業界も伝統的に調査や資料作成、コーディングにリソースを使ってきましたが、これからは人間としてのコンサルタントがクライアントに密着して伴走する時間を増やし、より実効性を高めていきます。
そうしてクライアントの変革を加速し、日本経済に貢献していく。これこそが、デロイト トーマツの使命だと考えています。






