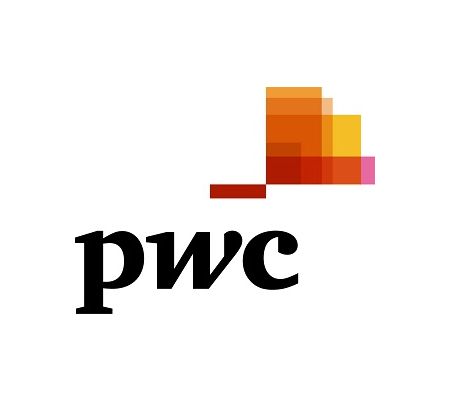「少し先の未来」を見据えた産官学連携のハブとは ルール形成から事業拡大まで一気通貫で伴走
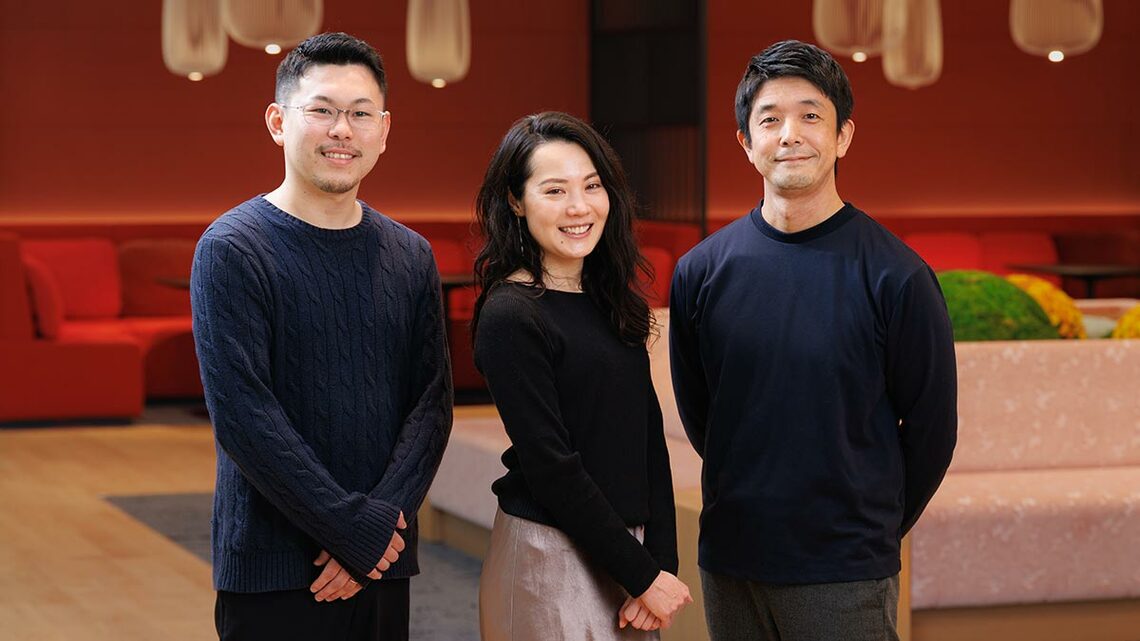
産官学連携のハブとして、イノベーションの加速を支える
――Technology Laboratoryとはどのような組織なのでしょうか。
岩花 Technology Laboratoryは、少し先の未来を見据えた新たなテクノロジーの可能性を検証し、社会実装に取り組んでいる組織です。「少し先の未来」というのがポイントで、例えば、AIだと生成AIの先にあるエージェント型AIやフィジカルAI、そのほか「空飛ぶクルマ」や量子コンピューティングなどもその範疇に入ります。まだビジネスとしては未知数ながら、日本が競争力を発揮できそうな領域に着目しているのです。

執行役員 パートナー
岩花 修平 氏
大手監査法人系コンサルティング会社などを経て現職。新たなテクノロジーの社会実装や、デジタルテクノロジーを活用した新規事業の推進、企業の業務改善の支援に従事している
新しいテクノロジーを社会実装していくには、利便性や安全性などを検証し社会受容性を高めなくてはなりませんし、法規制などのルール形成も不可欠です。そのうえで、ビジネスモデルを構築していく必要があり、これらすべてPwCのみでは到底できません。国や自治体、大学などの学術機関、研究機関、そして民間企業と産官学連携のハブとなって、多面的かつ多方面の支援をするのがTechnology Laboratoryの使命だと思っています。

丹羽 私は、現在、ルール形成に関わる案件を担当しています。海外の事例や制度、国際標準化の動向などをリサーチしながら、国の行政機関と意見交換を行い、制度設計にも関わっています。そもそも、新たなテクノロジーが活用される領域には、それに対応したルールがありませんので、社会のあり方を踏まえ、0→1(ゼロイチ)で生み出していく必要があります。
その意味では、まだ先が見えない未来を照らし、進む道を示すのがTechnology Laboratoryの役割だと思っています。未知の世界を切り開いていくことを、崖から海に飛び込むことに例えると、崖の高さはどれくらいで、飛び込んで潜ってから呼吸できるまでの時間はどのくらいあるか、その先のどこに陸地があるのか、といったさまざまな情報を提供することで、意思決定に寄与できます。こうしたプロセスに伴走でき、大きなやりがいを感じています。

シニアアソシエイト
丹羽 雄暉 氏
事業会社で新規事業開発などを担当。「Technology Laboratoryで、より幅広いソリューションを顧客と共につくり上げたい」とも
齋藤 先進的なテクノロジーに関わる機会が多いことが、Technology Laboratoryの大きな魅力だと感じています。研究開発現場でのアイデア段階からシーズ段階のテクノロジー、スケールアップ段階まで幅広く、0→1、1→10、10→100まで多様な段階をカバーしているのが特徴です。
PwCコンサルティングでは、知的財産を分析する独自のIPランドスケープツール「Intelligent Business Analytics」を開発しており、新規事業の構想具体化や事業戦略策定、アライアンスやM&Aの候補先探索、技術評価などの支援で活用する機会も増えています。こういったさまざまなユースケースのプロジェクトを通して、Technology Laboratory内だけではなくPwCコンサルティングのさまざまなユニットと連携する機会も増えており、とても刺激的です。

マネージャー
齋藤 望 氏
有機化学を学び博士号取得後、大学教員としてアカデミアの道に進み、戦略コンサルティングファームなどを経て現職。「テクノロジーやサイエンスを社会につなぐ役割を担いたい」と語る
シーズ段階からゼロベースで事業の立ち上げを支援
――Technology Laboratoryの開設から間もなく5年です。これまでの成果をお聞かせください。
岩花 幅広い領域でさまざまな成果が出ています。社会課題に対する領域では、例えば防災関連はAIやドローンの活用などでかなりの実績が積み上がってきました。そうした実績が新たな相談や依頼につながり、社会課題の解決に貢献できる組織として広く認知されてきたと感じます。
事業化の実績も増えています。シーズ段階のテクノロジーに関する相談も多いのですが、各種調査や分析だけでなく、事業の立ち上げから拡大まで、ワンストップで支援しています。PwCコンサルティングは戦略の策定から実行まで総合的な支援ができますし、PwC Japanグループには監査法人や弁護士法人、税理士法人など多岐にわたる分野の多様なプロフェッショナルがいます。そのケイパビリティを生かして、ゼロベースからビジネスをつくり上げることができるので、長いお付き合いになっている企業も少なくありません。
――事業として成果を出すまで伴走するのですね。
岩花 はい。クライアントとワンチームとして共に取り組んでいきたいという思いが強いですし、そうやって上げた実績が評価されていると感じています。また、社会への実装にしっかりコミットしている点も特徴だと思っています。中には、どうしても事業化が難しいと途中で判断せざるをえないケースもあるのですが、多くのテクノロジーに向き合っているからこそ、その見極めが迅速にできます。結果、「損害を最小限に抑えることができた」と評価いただくこともあります。
丹羽 先ほど、海に飛び込むという例え話をしましたが、情報提供のみで終わらず、どのようなアクションを取っていくべきなのか、具体的な実行支援まで一気通貫で支援できるのは、Technology Laboratoryの大きな強みだと思います。
Technology Laboratoryは、転職する際に想像していた以上にさまざまなことができる組織だと感じています。
齋藤 テクノロジーやサイエンスを社会とつなぐ役割を積極的に果たすことができること、社会実装までしっかり関与できることは、 Technology Laboratory で活動するメンバーからの視点という意味でも魅力的な点と感じています。メンバーが持続的に成長できる環境が整っていると実感しています。
相談しやすく、風通しのよい組織
――Technology Laboratoryはどのようなメンバーで構成されているのでしょうか。
岩花 メンバーの経験やスキルは、まさに多様性に富んでいます。コンサルティングファーム出身者が比率としては多いですが、産官学それぞれから集まっています。Technology Laboratoryは、新たなテクノロジーや事業アイデアを形にしていきますので、さまざまな視点が必要だと思っています。
齋藤 とても多様性を重視する組織だと感じています。専門性を尊重するのはもちろんですが、「この人はこれができない」ではなく「この人はこれができる」というところをしっかり見て、可能性を引き出してくれる組織文化が根付いています。
しかもアットホームで居心地がいいですね。「パートナーと話しやすい・相談しやすい環境で驚いた」ということがチームメンバー間で話題になったこともあります。気軽に近況を聞いてもらえたり、相談したりできる風通しの良さを痛感しています。
丹羽 組織文化で感じるのは、それぞれ職階ではなく役割で動いているということです。上長に声をかけづらいと感じたことはありません。私からパートナーの岩花さんにチャットを送ることも日常的にしていますし、わからないことがあったらどんな人にも積極的に聞ける雰囲気があります。
齋藤 相談したとき、親身になってくれるのが大きいと感じます。時には、「あの人なら詳しいかもしれない」とつないでくれるなど、相互に役に立とうという気持ちがさまざまなシーンで強く伝わってきます。全体的にそのような雰囲気があるので、おのずと相談しやすくなるのではないかと思います。
高い柔軟性と強いモチベーションが、確かな成果を生む
――Technology Laboratoryで一緒に働きたいと思う人物像をお聞かせください。
丹羽 テクノロジーの進化を俯瞰して感じるのは、知見を転用することの大切さです。1つの領域に深い知見を持つのはすばらしいことですが、そこだけにとどまるのではなく、ほかでどう生かせるかを積極的に考えられる人のほうがTechnology Laboratoryでは活躍できるのではないでしょうか。そういう考え方を持っていると、自らの役割をしっかり果たしたうえで、それを飛び越えてやるべきことも見つけられるはずです。そうした強い意欲を持つ人とともに働きたいですね。
齋藤 丹羽さんと本質的には同じことかもしれませんが、柔軟性とプライドをバランスよく持ち合わせている人と一緒に働きたいと思います。「ここだけは負けない」というプライドを持ってやりきることは、より成長しようという意欲にもつながっていきますし、柔軟性があれば壁にぶち当たっても軌道修正して持続的に成長できます。それぞれの強みを活かしながら足りないところを補い、刺激し合いながら成長していく環境がPwCコンサルティングには整っています。
岩花 先端テクノロジーは目まぐるしい変化が続いている領域です。状況に合わせてアジャストし、蓄積してきた経験を生かしていく柔軟性が求められます。実際、困難に陥ってもめげることなく、新たなイノベーションを起こしていくという高いモチベーションを持ち続けることができる人が、ここに集まっています。