釣具から「医工連携」を可能にした、開発者の挑戦 強靭なDAIWAのカーボン成形技術が奏功

日本製・医療機器のニーズを
肌で感じてきた医療現場
――今回の「医工連携」ではどのような開発をしているのでしょうか。
村山 脊柱管狭窄症(※)などの治療に使われる医療器具の開発です。一般的には緩んだ背骨を固定するために、スクリューを打ち込みロッドで固定するチタン製の器具ですが、MRIやCTでノイズが強く出るため術後評価などに影響もあります。今回は軽さや強度、MRIやCTへの影響を検討し、それほど太さがなくても長期的に使用できるものを開発中です。

東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座 主任教授
脳神経外科/脳血管内治療部 診療部長 脳卒中センター センター長
慈恵医大を卒業後、脳外科へ入局、UCLA神経放射線科へ留学。脳血管内治療で用いる画期的なコイルの開発を行う。カリフォルニア州の臨床ライセンスを取得、研究と臨床を両立する。 UCLA准教授、教授を経て、2003年慈恵医大脳外科へ帰局、同年より脳血管内治療部診療部長。13年より脳神経外科学講座主任教授。診療の傍ら、医療機器開発や学内発ベンチャーの立ち上げに携わる
――欧米を中心とする海外製の医療機器が主流だと伺いました。そうした中で日本の医療機器市場で「日本企業による独自技術」にこだわる意義についてお聞かせください。
村山 確かに日本の医療現場では、海外製の医療機器が広く使われています。しかし、それが日本人やアジア人の体格に適合していないケースも多いんです。だから、日本人はもちろん欧米人にも使用できる医療器具を生み出すことを目指したいと考えていました。それだけでなく、今回の開発に当たっては、私が脳神経外科医としての治療の際に感じてきた「金属疲労で折れやすい」「骨の負荷が大きくスクリューが緩みやすい」「手術後にMRI・CTで脊髄の評価ができない」という問題にも対応した器具を開発することが条件でした。
フィッシング(釣り)のロッドに活用してきた
カーボン成形技術を医療へ展開
――それで今回、特殊ネジ製品の製造を行うタカイコーポレーションと、釣用品などカーボン製品の製造を行っているグローブライドが参画したんですね。
及川 当社がこの医工連携に参画したのは、固有の技術を有する企業が出展する展示会でタカイコーポレーションのブースを私たちが訪問したのがきっかけでした。グローブライドは、『人生を豊かにするスポーツ』に焦点を当て、釣りやゴルフ等のスポーツ用品を製造、販売しています。中でも、より優れた製品を展開するためにカーボン成形技術を蓄積してきました。医療分野に関わることは正直、それまで想定していませんでしたが、これまでに培ったカーボンの成形技術をほかの領域に展開できないかと模索していたところでお声がけいただいたんです。
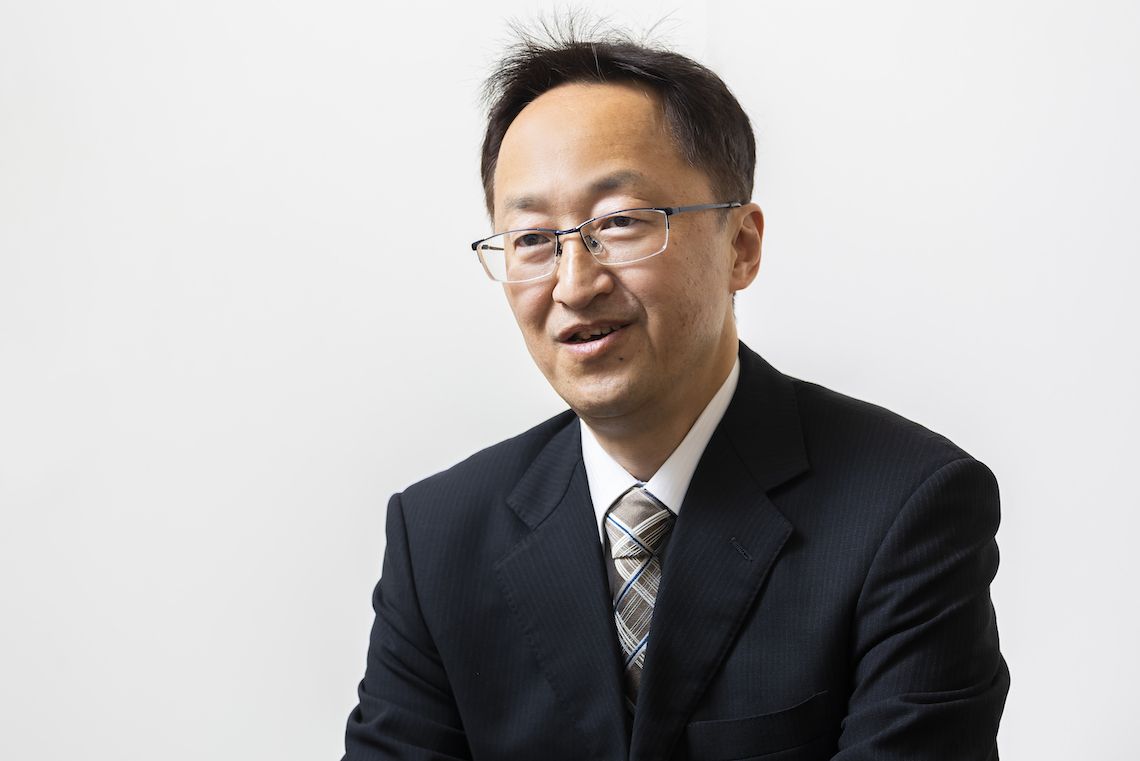
グローブライド フィッシング生産本部 AC事業準備室長
兼 研究開発センター 研究開発部 副部長
――医療器具に展開された、独自のカーボン成形技術とは具体的にどのようなものですか。
村山 カーボンは金属を上回るような強度があります。金属は長期的な荷重の繰り返しでポキッと折れてしまう場合がありますが、それに比べてカーボンは耐久性が非常に優れているんです。MRIやCTスキャンの使用に影響が出ないメリットもあります。
及川 ただ、一口にカーボンと言っても実は特性の違う材料が何百種類もあり、製法も何十種類もあるので、どういう組み合わせが最適かを選び出し、実際に使いこなすことはかなり難しい素材です。その点、私たちは1970年代からカーボンを釣り竿など製品の素材に採用し長期的に培った知見があるので、当社の強みを生かした開発ができていると思います。
「医工連携」を突き動かす
ビジョンと熱意
――日本企業の2社との異業種連携であり、とりわけ専門性が高く企業にとっては参入障壁の高い「医療分野」における協業はさまざまな苦労もあったのではないでしょうか。
村山 日本における医療機器開発で大変なことは、研究レベルではご協力をいただけても、その先のチャレンジには躊躇して踏み込めない企業が多いことです。今回は、2社がここまで諦めず、われわれ東京慈恵医科大学発のスタートアップ企業・スパインテックもリーダーシップを発揮しました。お互いの専門分野を生かして開発を進めることができたと思います。実のところ、スポーツレジャー企業の大手・グローブライドが医療の領域に踏み込んでチャレンジしていただけるか、個人的には少し心配していましたがよく踏み切ってくれました。
及川 われわれは釣り具の分野では先進的な技術を有していると自負していますが、新たな分野に入るのは不安やリスクがあります。医療分野で何ができるのかを考えたとき、「医療現場の立場ではどういうものが必要か」という知見はありませんでした。
そのため「どこまでできるだろうか」という期待と不安の両方を感じましたが、「A Lifetime Sports Company 人生を豊かにする」というグローブライドのビジョンの観点からスポーツだけでなく「医療」も私たちの目指す先にあるものではないかと考え、挑戦することとしました。今回の取り組みは大きなチャレンジとなりましたが、社会的意義や責任のあるプロジェクトに参画していると自覚しています。

村山 人生を豊かにすることに真摯に取り組んできたグローブライド社の想いが、医療にまで広がったことに感心しています。今後のステップとしてはまず国内で実績を作っていきたいと考えていますが、われわれはそこにとどまらずグローバル展開を構想しています。米国市場でポジションを築くことはなかなか高いハードルがありますが、米国の脳神経外科医の仲間にもアピールしてさらなる市場の開拓を目指していきたいです。
医工連携で生まれた
イノベーションの未来
――今回の取り組みは異業種連携により、うまくイノベーションが引き起こされたように見受けられます。
村山 医工連携を行う意味はイノベーションにあります。仮にすでに確立された標準治療で合併症が起こる可能性が5%あるとしましょう。そこに今までとはまったく異なる発想や技術を持ち込んで検証し、失敗したらなぜ失敗したかをリヴューして問題点を一つひとつ解決し、5%を4%、3%と引き下げていく。こうしたチャレンジをすることで、医療は進歩していくのです。
及川 今回、未知の領域での課題を見いだし新しいカーボン成形技術のチャレンジを行っているので、非常に意義のある取り組みができました。これまでもグローブライドは旧社名ダイワ精工の時代から挑戦を続けてきた企業だと自負しています。本プロジェクトへの参画により、スポーツを楽しんでいただくことだけにとどまらず、スポーツを楽しむための身体的能力を補助するためにカーボン成形技術を活かす将来性を追求し、さらに医療分野へ踏み出し新しいカーボン製品の可能性を見出しました。
村山 イノベーションが生まれないところに未来はありません。これからもAIのようなエマージングテクノロジーや工学、薬学などさまざまな技術を引き込んでいくことでお互いに技術革新が進められたらいいですね。
⇒医工連携に取り組むグローブライド




