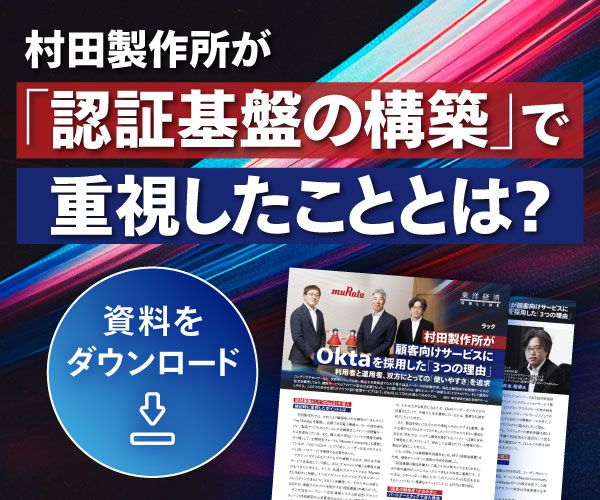村田製作所が抱えていた「アカウント管理」の課題 利便性向上へ「認証基盤」を構築、その裏側とは

スマートフォンや自動車などに欠かせない電子部品である積層セラミックコンデンサをはじめ、さまざまな製品で高いシェアを持つ電子部品メーカーの村田製作所。国内外の多くの電子機器メーカーと取引する中で、デジタルサービス提供の重要性が増してきていた。
そうした背景から、顧客である電子機器メーカーが、製品サンプルの提供リクエストや会員限定コンテンツの閲覧などができるポータルサイト「my Murata」を2013年から提供。
2020年には、製品を購入した顧客と村田製作所、あるいは顧客同士で情報交換ができる公開技術フォーラム「Murata Community」の運営も開始している。
しかし、my MurataとMurata Communityはどちらも会員制のサービスであるが、別々のアカウントを利用する形で運営されている。そのため同社では、今後のデジタルサービスの拡充を考えたときに、アカウントの乱立がユーザビリティを低下させる懸念を抱いていた。
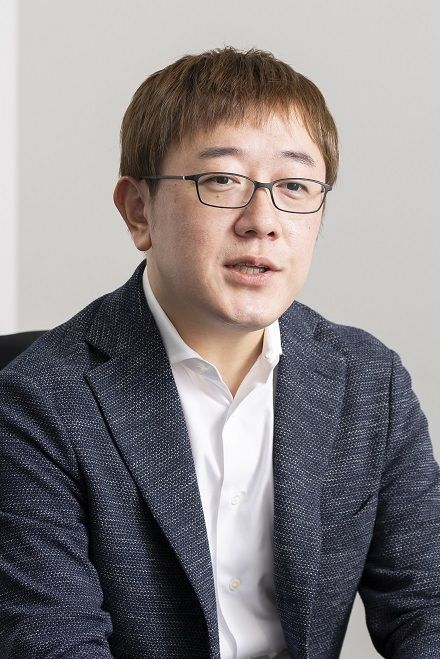
コーポレート本部 情報システム統括部
デマンドチェーンDX推進部
上村 直史氏
「今後顧客向けデジタルサービスの機能を追加していく構想もあり、サービスの背後でさまざまなWebアプリケーション(SaaS/スクラッチ開発)が動くことになる見通しです。
その際、すでに2つのアカウントがあるのに、お客様にさらにアカウントの追加をお願いすることはできません。
そこで、1つのアカウントで複数のサービスを利用できる『Murata ID』を作ることに決めました」(顧客向けデジタルサービスを担当する、村田製作所 コーポレート本部 情報システム統括部 デマンドチェーンDX推進部の上村直史氏)
Murata IDをキーにして、1つのアカウントで複数のサービスにログインすることを可能にするには、シングルサインオン(SSO)と呼ばれる機能が必要になる。この機能を実現する認証基盤の構築に向け、同社は必要な要件の整理に取りかかった。
結果として、SSOの実装などによるユーザーの利便性向上やセキュリティの強化を実現する認証基盤の構築に成功。Murata IDも正式にリリースしている。
実現の手段として村田製作所が選んだのは、クラウド型ID管理サービス「Okta」の導入だった。同社はなぜOktaを採用し、どのようにして顧客向けデジタルサービスのアカウント統合、認証基盤の構築を成し遂げたのか。そのプロジェクトの詳細は、ここからダウンロードできる資料で読むことができる。