ニップンが「食」から挑む持続可能な社会の実現 事業成長と社会価値創造の両輪で前進する

3年前倒しで目標を達成。総合食品企業としての強さ
将来的に売上高5000億円、営業利益250億円を目指す。ニップンがこれを長期ビジョンとして掲げたのは2022年のこと。併せて掲げた「26年度までに売上高4000億円、営業利益150億円」という中期目標は23年度に達成した。3年も早く達成できた理由を、香川敬三氏はこう分析する。
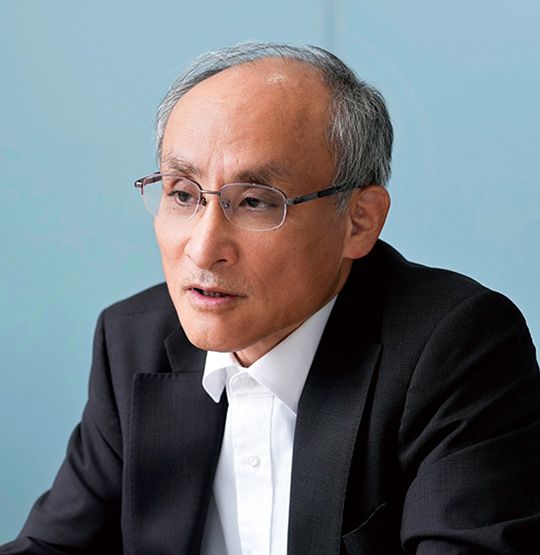
コーポレート部門・新規事業担当
EC事業室・ヘルスケア事業部管掌
香川 敬三氏
「前期はインバウンド消費と個人消費が回復するなど、需要全般が伸びを見せました。こうした中、以前から行っていたコスト削減と価格改定が効果を上げ、前倒しで中期目標を達成できました」
そして24年5月、長期ビジョン2030を発表し、総合食品企業として食による社会課題解決に挑み続けることを宣言した。
「長期ビジョン2030のポイントは3つあります。1つ目は売上高5000億円、営業利益250億円という目標の達成時期を30年度と明確にしたこと。2つ目は経済価値の追求と併せて社会価値の創造を掲げたこと。3つ目は当社を“総合食品企業”と位置づけたことです」
同社の基盤は祖業の製粉事業だが、近年は食品事業が大きく伸びている。
「『われわれは何者なのか』を議論する中で浮かび上がったのが“総合食品企業”としての姿。当社の事業は2つの軸で広がってきました(下図)。縦軸は製粉から食品素材、加工食品、冷凍食品、中食という加工の広がり、横軸は小麦、米・そばなどの原材料の広がりです。
原材料の加工技術やノウハウ、素材の特性の研究データなどが蓄積されており、それぞれの事業が強く結び付きながらプレミックス、パスタ、冷凍食品などの事業を展開してきました。今後も縦軸と横軸で事業をさらに拡大していく、という意味を込めて総合食品企業と定義づけたのです」
社会・生活者・従業員のウェルビーイングを目指す
長期ビジョン2030では、“総合食品企業”として2つの成長戦略を明らかにした。それが、事業成長戦略と社会価値創造戦略だ。
「事業成長戦略では製粉事業、食品素材事業、加工食品事業で収益を上げていきます。そして、その収益を冷凍食品、中食、ヘルスケアなどの成長事業に投資し、国内外の製造体制を強化。既存事業を拡大させるだけでなく、M&Aなどによるインオーガニック成長にも注力する予定です」
事業成長戦略に基づく投資は24年から26年で1200億円程度を予定している。一方、社会価値創造戦略で目指すのは、社会・生活者・従業員のウェルビーイングの実現だ。
社会のウェルビーイングの取り組みの1つとして植物育種研究の推進がある。同社では以前から外部機関と連携して小麦やトマトなどの育種研究を行っている。
「新品種の開発には10年単位の時間がかかります。農家数と耕作面積の減少という課題があり、高付加価値を生む品種を作ることで日本の農業の発展に貢献したいと考えています。
食の持続可能性に関心が高まる今、当社では厚生労働省の『健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ』に参画するほか、国産小麦の育種研究を通じ、国産麦の安定的な供給体制の構築にも取り組んでいます。また、TCFD※に賛同もしています」
生活者のウェルビーイングの取り組みとしては、フードバンクへの食品寄贈や栃木県小山市の子ども食堂の支援といった、地域と連携した支援活動がある。
「小山市は00年まで80年以上、当社の工場があった場所。現在はニップンスポーツというスポーツクラブを運営しています。『地域に根差した活動をしているからこそ解決できる社会課題がある』という考えから、子ども食堂への食品の提供を行っています」
ただ、と香川氏は続ける。
「こうしたサスティナビリティに対する取り組みを当社の社会課題解決型事業につなげていければと思いますが、昨今の社会課題は複雑化しており、一企業だけで解決できるわけではありません。
ソーシャルデザインという考え方もあるように、産官学・自治体と連携して社会全体で課題に取り組んでいくことも必要だと考えています」
※TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース。企業の気候変動への取り組みや影響に関する財務情報を開示する枠組み
海外投資と並行して進めるグローバル人材の育成
同社では海外売上比率の上昇を目指して投資を行っており、グローバル人材の育成に着手した。
「1つは、海外のビジネス感覚の醸成を目的とした若手社員の短期海外研修です。もう1つは約1年程度の現地実務研修を目的とした海外拠点への派遣。海外に関心を持つ人材の裾野を広げることが狙いです」
従業員のウェルビーイングに関する取り組みも行っている。
「従業員は企業価値創造の源泉であり、その成長が会社の成長の原動力です。業務上必要なデジタルツールの研修や、eラーニングプログラムなども用意しました」
これらと併せて働き方改革も進めている。従業員にはそれぞれのライフスタイルがあり、またキャリアプランに対する考え方も異なる。その中で勤務地の希望や、キャリアビジョンを把握し、一人ひとりと向き合うことが必要だと考えているという。
事業成長戦略と社会価値創造戦略の両輪で推進する、ニップンの長期ビジョン2030。興味深いのは、経営陣が各事業所や工場を回り、従業員に直接伝え続けている点だ。
「大切なのは従業員が腹落ちすること。直接話して日頃の課題や会社への要望などを聞き、お互いに理解を深めています。長期ビジョン2030をきっかけに、社内外を問わず、ニップンの理念や取り組みについて知っていただけるとうれしいです」





