CTCが描く「未来図」と最新テクノロジートレンド OpenAI長﨑氏も登壇「日本企業は大チャンス」

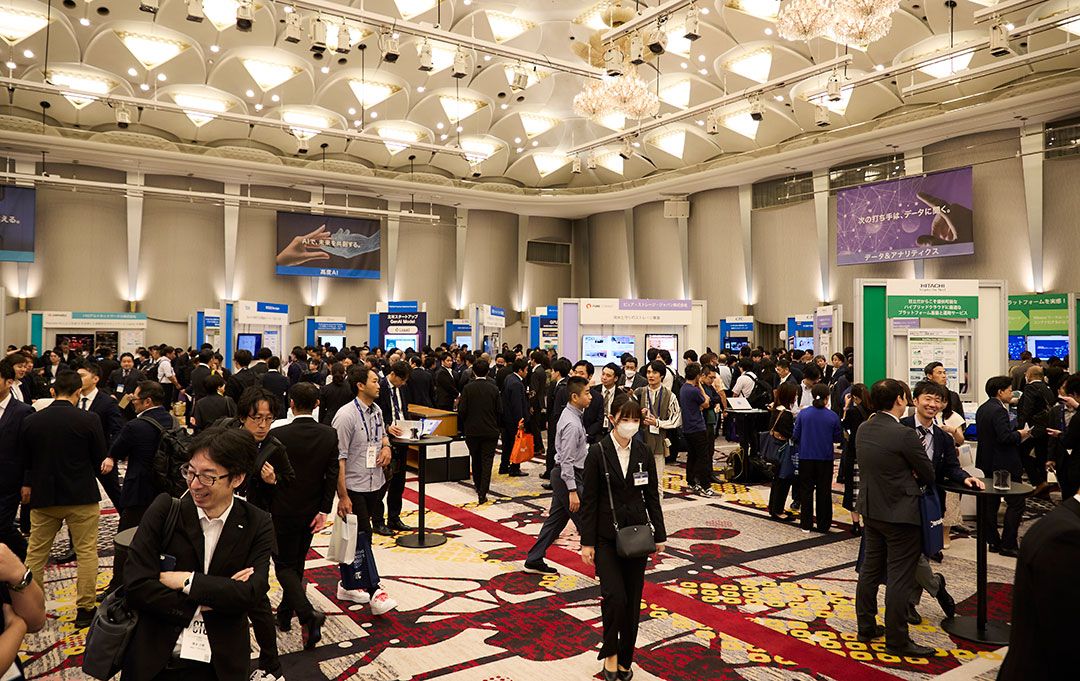
新たな技術によって、描ける未来図が変わってきた
「皆様、CTC Forum 2024にご参加いただき、誠にありがとうございます」
朝から1500人以上が入った基調講演の会場にある大型モニターに、CTC代表取締役社長の新宮達史氏の姿が映し出された。しかし、壇上に本人の姿はない。
「新宮社長、いらっしゃいますか?」
MCの田中大貴氏(元・フジテレビアナウンサー)が問いかけるが、返答はない。何度も呼びかけて出てきた新宮氏の服装は、モニターに映し出されたものとは違っていた――。

「この人物は、私を基にして生まれたデジタルヒューマンです。3Dモデリングとモーションキャプチャーの技術で生まれましたが、最初は表情も乏しく、発話もできませんでした。それが、CGとAIを使うことで、自信たっぷりなスピーチができる大人になりました。どうやら、自律型AIエージェントを組み込んで、社長の座を虎視眈々と狙っているようです」
ユーモアたっぷりに、最先端テクノロジーの現状を表現した新宮氏は、続いてCTC Forum 2024のテーマである「未来図を現実に」についてこう話した。
「生成AIをはじめ、次々と登場するテクノロジーにより、描ける未来図が変わってきています」
例として示したのは、2020年に文部科学省が発行した科学技術白書。20年先を見据えた未来図だった。しかし、技術革新のスピードは想定以上に進んでおり、そこに描かれた遠隔治療や即時自動翻訳などはすでに実現している。
「この技術革新のスピードを支えているのがAIです。科学技術白書の2024年版では、2020年版になかった宇宙観測なども描かれています。今後、AIはさらに大きなうねりを起こすゲームチェンジャーとして存在感を増していくことは間違いないでしょう」

代表取締役社長
新宮 達史 氏
これまでITの世界は、ゲームチェンジを繰り返してきた。インターネット、クライアントサーバ、仮想化、クラウド。CTCはその歴史とともにあったと新宮氏は話す。
「CTCはクライアントサーバに対する国内企業の期待に応えたことで、ビジネスの拡大が加速しました。その後も、仮想化、クラウドと国内外のパートナー企業とともにゲームチェンジに対応してきました。AI時代を迎え、CTC自身もゲームチェンジを進めてお客様と共に未来図を描き、共に現実にしていきます」
ワークフロー全体にAIが組み込まれる時代は目前にある
新宮氏に続いて基調講演を行ったのは、OpenAI Japan 代表執行役社長の長﨑忠雄氏。2022年にOpenAIが世に送り出したChatGPTは、瞬く間に生成AIブームを巻き起こし、史上最速でアクティブユーザー数が1億人を突破した。「AIのハードルを、ChatGPTというソフトウェアが劇的に下げたということです」と長﨑氏が語るように、現在は毎週2.5億人が利用しているという。

代表執行役社長
長﨑 忠雄 氏
「2年前には得られなかったAIツールを、誰もが平等に使うことができます。AIは今後も継続的に進化していきますので、使わない理由はありません」
仕事の仕方が変わり、AIをいかに活用するかが競争戦略になっていく。ところが、真の意味で事業戦略にAIを組み込んでいる企業は、まだグローバルで少ないと長﨑氏は指摘する。
「この状況は、日本の企業にとって非常に大きなチャンスだと考えています。では、どこからスタートしたらいいか。答えはシンプルです。社員の皆様に使ってもらうことです。現場の各部署で取り組むべき問題はまったく異なります。それが解けるのは現場の方々だけなのです。サービスや製品に組み込む前に、まずは社員の働き方をAIで変え、生産性と働く幅を大きく広げることによって、企業の競争力が上がると考えています」
「日本ではあまり知られていない」と長﨑氏は明かすが、OpenAIでは企業向けのセキュリティとプライバシー、そしてChatGPTの最強バージョン、ChatGPT Enterpriseも提供。世界の大企業が選ぶ信頼のプライバシー管理とセキュリティで、スピードも速いという。
「日々取り組むさまざまな業務、ワークフロー全体にAIが組み込まれる時代が、目の前まで来ています。進化も速いので、AIの最先端モデルに触れ、理解することが非常に重要です。AIの社会実装は、日本の国力を大きく上げるチャンスです。OpenAIは、さまざまな企業と連携することで、その第一歩を大きく踏み出したいと思っています」
これからの時代で重要な「情報編集力」の磨き方

元・リクルート フェロー
和田中学校・一条高等学校元校長
藤原 和博 氏
ビジネスの未来を語った長﨑氏に続き、デジタルを活用した学びの未来について基調講演を行ったのは、民間人として初めて東京の区立中学校校長に就任した藤原和博氏。参加者にブレインストーミングをしてもらうアクティブ・ラーニング・スタイルで、まず提示したお題が「お掃除ロボットをいかに面白くするか」。掃除以外の付加価値をいかに生み出すかを考えることで、「情報編集力」の重要性を伝えた。
「正解はAIやロボットが導くことができます。では人間は何をするべきか。モノ、コト、ヒト、情報といった異なる要素を掛け算して、今とはまったく異なるけれども、他者を納得させられる仮説、『納得解』を縦横無尽に出していくことが大切です」
AIやロボットが持つのは情報処理力であって、「頭の回転の速さ」とも言い換えられると藤原氏。対して、納得解を出していく情報編集力は「頭の柔らかさ」だという。
「今、皆さんがしている仕事も、正解がはっきりしているものはほとんどないはずです。仮説をいっぱい出しながら、他者の仮説もたくさん聞き、納得できる仮説を試して無限に修正していく。それが今後さらに重要になっていきます」
この話の後で藤原氏が再度参加者に提示したお題は「白が当たり前のものを20個以上挙げよ」。これには会場中から活発な反応が見られたが、次に「それを黒に変えて付加価値が高まるものを挙げよ」というお題が出されると、会場内には戸惑いも見られた。「黒に変えるのは難しかったという人は手を挙げてください」という藤原氏の問いかけには、ほぼ全員の手が挙がった。
「もちろん、情報処理は最初に行うべき重要な作業です。しかし、付加価値を生むには情報の編集が必要です。ヒットする商品やサービスは、いわば情報処理脳から編集脳への切り替えによって生まれるということが実感できたのではないでしょうか」
日本の学校は正解至上主義だと話す藤原氏は、情報処理力を情報編集力に移さなければならないと説く。そうやって付加価値を生み出していく力を養うことは、キャリアアップにもつながっていくと強調した。
AIの最新トレンドは「特化モデルの選択と組み合わせ」
基調講演の後に行われた80を超えるセッションでは、幅広い業種の企業による事例講演のほか、クラウド/クラウドネイティブ、セキュリティ、データ&アナリティクス、高度AIなど注目の最新テクノロジーが次々に紹介された。
生成AIの最新トレンドを紹介したのは、ITOCHU Techno-Solutions AmericaのPresident & CEO、田中匡憲氏による「〜北米スタートアップ企業から知る、生成AIのこれから〜北米の最新生成AIトレンド・テクノロジーとスタートアップの動向」。
田中氏は、直近のシリコンバレーのベンチャー投資は3分の1が生成AI関連で、現在のトレンドは「特化モデルの選択と組み合わせ」だと話す。
「AIモデルによって得意な領域がはっきりと見えてきました。エッジ、オンプレミス、クラウドのそれぞれにAIを搭載し、環境や用途に合わせて最適なモデルやインフラを選択する時代になってきています」
田中氏のAIモデル&アプリケーションセグメントにおけるトレンド解説では、注目スタートアップを紹介。特化型モデルとして、最小限の処理能力で順応性の高い機械学習を可能にするMIT(マサチューセッツ工科大学)発の「Liquid AI」(編注:CTC Forum 2024の開催後にCTCはLiquid AI, Inc.日本法人への出資を発表)。オーケストレーターとして、IntelからスピンオフしたAutonomous GenAI PlatformのArticul8。Liquid AIは、少ないニューロンで複雑なタスクを実行する線虫を題材とした生物学的研究からスタートしたことで、「従来は四則演算だったのが、関数計算をできるようになるイメージ」の進化を遂げたという。手のひらサイズのシングルボードコンピュータに搭載できるほどコンパクトなのも特徴だ。またエンタープライズのユースケースにおいてはより高い正答率と説明責任が求められる。Articul8はより高度なタスクに対して、特化型モデルを複数組み合わせて実現すると共に、モデルのスコアリングや参照データの確認をすることで説明責任を担保するという。
Articul8社と自律型生成AIプラットフォームの提供に向けた協業を開始

北米はAIセキュリティソリューションが活況
AIと共にセキュリティも進化している。「サイバーセキュリティ for AI:生成AI利活用におけるリスク対策」では、CTC サイバーセキュリティビジネス企画・推進本部 アソシエイトプリンシパルの伊藤英二氏が「サイバー犯罪の攻撃者側もAI技術を多用しています」とし、近年ディープフェイク技術が多用され、誤って40億円を振り込んだ事件も起こっている現状を紹介した。
そうした事態を受け、北米ではAI向けのセキュリティソリューションが活況。例えば、あるシリコンバレー発のAIセキュリティサービスでは、個人情報や機密情報が機械学習データに使われないよう規制できるほか、自動的にレスポンスを返さないよう制御も可能だという。

アグリテックで循環型社会を実現
環境や用途に合わせて最適なテクノロジーを選び、適切なセキュリティ対策を施す結果、描ける未来図は着実に広がってきた。その1つを示したセッションが「【みらい研究所】農業、畜産業とデータ活用の融合で目指す、三方良しの新しい農業 鉄触媒で実現する効率の良い農業、畜産業」だ。

LIFULL Agri Loop 代表取締役の岸大介氏によれば、「現在、化石燃料の燃焼や化学肥料の活用、さまざまな生物の糞便で排出される反応性窒素の量がかつてなく増えている」という。しかし、反応性窒素を単に減らすだけだと農業生産が安定しない。
そこで、糞尿に鉄触媒を入れて酸化を防ぎ、悪臭と温室効果ガスを大きく抑制しつつ窒素利用率を改善する取り組みを進めている。北海道の牧場では、それによって牧草収穫量も牧草の栄養価も向上させ、売り上げ50%アップを達成したという。
なお、このセッションには、LIFULL Agri Loopと協業を進めているCTCの取締役会長、柘植一郎氏も登壇。「テックから課題解決に入りがちですが、テックだけではうまくいきません。農業全体が収益性を向上できるよう、伊藤忠商事のビジネスネットワークも活用してアグリテックを提供します」とネイチャーポジティブ実現への意気込みを語った。
成長戦略をサポートするSIerとして、日本経済の再浮上に貢献する

――CTC Forum 2024は2500人以上を集める大盛況でした。「未来図を現実に」がテーマでしたが、CTCは具体的にどのような未来図を描いていくのでしょうか。
SIerとして、お客様企業と共に最適なITシステムを構築していく。これが当面の未来図です。CTC Forum 2024では生成AIやクラウドネイティブ、量子コンピューターといった最新のテクノロジートレンドを紹介しましたが、個々の技術を生かすには基盤づくりが重要です。例えば、レガシーなITシステムを見直す際、お客様と共に未来図を描き、それを現実化するテクノロジーを取り入れていくといった形です。
――セッションや展示では、セキュリティ関連の多さが目を引きました。
今回、展示ブースは100とCTC Forum史上最大規模でしたが、約4割はセキュリティ関連です。サイバー攻撃への対策は、あらゆる企業にとって喫緊の課題です。最新のセキュリティ技術をITシステムに組み込み、セキュアな基盤を整えることが、お客様企業が成長戦略を立てるうえで欠かせないと考えています。
これまでSIerは、お客様企業が抽出した課題や成長戦略のアウトプットとして、システム構築を依頼されてきました。しかし、変化の激しい時代において、真にお客様の成長に寄与するITシステムを実現するには、システムインテグレータがつねに伴走し、成長戦略としての未来図を共に描いていくことが求められると考えています。
――26年度までの中期経営計画では、「前例のない領域へ」というコンセプトを掲げられています。どのような思いが込められているのでしょうか。
CTCは北米の最先端テクノロジーを発掘し、実装する目利き力で高い評価をいただいてきました。また、日本国内には数千社のお客様がいて、これは業界でも屈指だと自負しております。一方で、SIerとしてはまだ2番手集団に属しているというのがわれわれの認識です。業界のトップ集団に入り、数千社のお客様の成長に貢献して日本経済再浮上の一助となるため、今まで以上に前例のない領域に踏み出し、自らのポテンシャルをもっと引き出していきたいと考えています。




