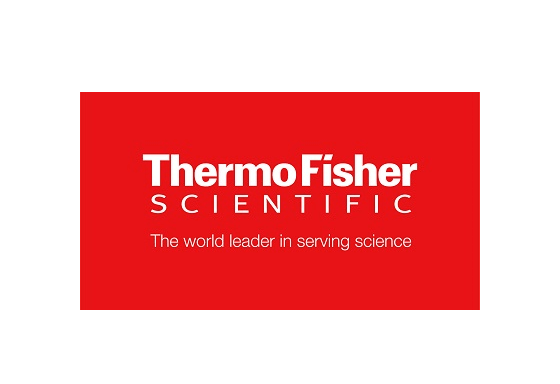日本のバイオ医薬産業化の鍵となる「2つの施策」 「人材育成」と「異業種連携」が求められる理由

バイオ医薬品製造に関わる人材育成を手がけるバイオロジクス研究・トレーニングセンター(以下、BCRET)で専務理事を務める神戸大学特命教授の内田和久氏と、ライフサイエンスを含む総合的なサイエンスソリューションを提供するサーモフィッシャーサイエンティフィック(以下、サーモフィッシャー)の開田強氏に話を聞いた。
バイオ医薬品開発で日本が後れを取っている理由
――近年、バイオ医薬品市場が成長している背景について教えてください。
内田(BCRET/神戸大学) そもそも「バイオ医薬品」とは、細胞培養技術や遺伝子組み換え技術を使って生み出されたタンパク質などを利用して作られる薬のことです。化学合成で作られる従来の「低分子医薬品」とは異なり、人間の体内にある機能分子を利用しているため、体への負担が少なく、副作用も軽減されやすいという特徴があります。
とくに、バイオ医薬品の一種である抗体医薬品は、特定の標的に対して作用する性質を持ち、少ない副作用で高い効果を上げることで期待されています。そのため、がんや希少疾患の治療において使用頻度が増すなど、ニーズが非常に高まっているのです。

バイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET) 専務理事 企画担当理事
内田 和久氏
開田(サーモフィッシャー) 生活習慣病などの患者数が多い疾患については、既存の低分子医薬品がおおむねカバーしています。一方で、希少疾患や遺伝子疾患などの比較的患者数が少ない病気というのは、低分子医薬品では対応が難しい領域でした。
しかし技術の進展により、バイオ医薬品を用いることでそうした病気にも対応できるようになってきました。そこで製薬企業も、大衆をターゲットにした低分子医薬品に代わる次のビジネス領域として希少疾患にフォーカスし、バイオ医薬品の事業を強化する動きが見られています。
――日本は海外と比べてバイオ医薬品開発で後れを取っているといわれています。新型コロナウイルス禍では、コロナウイルスワクチンの供給の大部分を輸入に頼らざるをえない状況となりました。日本の課題はどこにあるのでしょうか。
内田 日本では、バイオ医薬品の開発や製造に必要な新しいテクノロジーの育成や製造施設の整備がまだ十分とはいえない現状があります。
長い間、日本の製薬産業は低分子医薬品の製造技術において高い水準を維持してきましたが、バイオ医薬品のような新しい治療分野に対応するための技術基盤や製造インフラへのシフトが十分にできていないのです。
そのような状況のときにコロナ禍に見舞われたことで、ワクチンを作るための部材や施設が不足し、開発品も十分に準備できていなかったのではないでしょうか。国内でのバイオ医薬品製造能力を強化し、自前での生産基盤を整えることが今後の課題であり、将来的な競争力を左右する重要な要素だと考えています。

バイオプロダクション ダイレクター 開田 強氏
開田 製薬市場のグローバル化の影響もありますね。日本は薬価制度により薬の価格が下がりやすく、人口も減少しているため、製薬企業が利益を求めて海外市場に向かう傾向が強くなっているのです。
そのため、米国や欧州など薬価が高く人口も多い市場が拡大する一方で、国内のバイオ医薬産業の発展が遅れてしまっている現状があると思います。
内田 そうした反省もあって、現在は経済産業省や厚生労働省の旗振りでバイオ医薬品の製造拠点の整備が急速に進められています。しかし、製造拠点をつくっただけで解決とはいきません。それを回せる「人材」も少ないのです。
バイオ医薬品の製造には、高度な技術と専門的な知識を持つ人材が不可欠ですが、現状はその育成が十分に進んでいるとはいえません。低分子医薬品の製造においては、日本は長年培ったノウハウがありますが、細胞や遺伝子を扱うバイオ医薬品に必要なスキルセットや開発の経験を持つ人材は限られています。
国内の製造基盤が整っていないだけでなく、技術を持つ人材の不足がさらなるボトルネックとなっているのです。
「バイオ人材」育成へ、着実に進む取り組み
――そうした課題がある中で、BCRETではバイオ医薬品製造のプロセスや品質管理に精通した人材によって国内での製造能力を高めていくために、人材育成に取り組んでいます。
内田 BCRETは、バイオ医薬品の開発や製造技術を備えた「バイオ人材」の育成を目的に設立された組織です。2017年8月に、日本医療研究開発機構(AMED)や医薬品医療機器総合機構(PMDA)、日本製薬工業協会(製薬協)、神戸大学の協力を得て開設し、18年4月から本格的にバイオ人材の育成事業を開始しました。
産官学の連携を促進する中立的な立場の一般社団法人として、製薬企業や大学、政府機関と協力しながら、座学と実習による教育プログラムを展開しています。これまでに座学で約1500人以上、実習で約450人以上が受講した実績があります。
――BCRETが育成する「バイオ人材」とは、具体的にどのようなスキルを持った人材なのでしょうか。
内田 バイオ医薬品の研究開発から製造に必要な「CMC(化学、製造、品質管理)開発人材」と、製品の品質や製造工程を適正に管理する「GMP(適正製造規範)製造人材」の育成に重点を置いています。
バイオ医薬品の製造においては、細胞などの「生き物」を利用するため扱いが難しく、気にかけなければならないことが数多くあります。
そのような中でも、薬剤の設計や培養、製造、品質といった一連のプロセスを管理して医薬品を作り上げることのできる研究開発人材から、製造段階で実際にGMP基準に基づく工場での製造を担当できる人材まで、幅広く教育プログラムを提供しています。
開田 人材育成と同時に、製造手法の属人化を防ぐことも大切だとサーモフィッシャーでは考えています。製造プロセスが特定の技術者の経験やスキルに依存していると、効率化や品質の一貫性が難しくなります。これを解決するためには、製造工程の標準化と自動化が重要です。
こうした課題に取り組むため、サーモフィッシャーは22年に「再生医療クリエイティブ・エクスペリエンス・ラボ」(以下、T-CEL)を東京都港区のオフィス内に開設しました。
T-CELでは、グローバル展開するときにもお使いいただけるような装置・技術をそろえ、新薬の「種」を生み出してから世に出すところまでを迅速化できるような製造プロセスを作るお手伝いができればと考えています。
実際に、開設から2年間で1600人以上の方々にお越しいただきました。製薬企業や研究機関、規制当局などさまざまな方々が集まり、課題を共有しながら共に解決策を探す場となっています。
――BCRETとサーモフィッシャーの両者は現在、がん治療のために患者の免疫細胞を改変して強化した「CAR-T細胞」の開発・製造に関する人材育成プログラムの開発で連携されているそうですね。
内田 CAR-T細胞製造においては、海外で開発・標準化された先端技術や、製造工程に関するノウハウや装置が必要であり、日本国内で早急に人材を育成するためには、さまざまなパートナーの協力が欠かせません。サーモフィッシャーもそうしたパートナーの1社です。
BCRETでは、サーモフィッシャーの装置を含む先端の技術を導入しながら、CAR-T細胞製造に必要な知識を持つ人材育成を進めようとしています。実際の人材育成プログラムも、来年には提供できる予定です。
開田 グローバルに展開するサーモフィッシャーとしては、海外の技術や情報をいち早く日本に届けることが役割と考えています。BCRETと連携することで、より多くの製薬関係者に技術を提供し、国内の技術力向上を支援していきたいです。

内田 サーモフィッシャーのような装置メーカーと連携することで、教育プログラムがより実践的かつ現実に即した内容になります。
例えば、CAR-T細胞の製造には高度な技術と知識が必要ですが、サーモフィッシャーの装置や技術を活用することで、学習する人は現場で役立つ技術を習得できるのです。
国内でのバイオ医薬品製造が早期に実現し、グローバルにも対応できる人材の育成が可能になると考えています。
より迅速に薬を届けるために、「異業種連携」の重要性
――現在、製造プロセスの自動化やデジタル化を推進する「ファーマ4.0」が、日本でも進みつつあります。日本の製薬産業の競争力を高めるためには重要な取り組みですが、そこではどのような人材が必要になるのでしょうか。
内田 製薬業界では患者さんの安全性を確保するための厳しい基準や規制が求められているため、デジタル化が他の産業界よりも進みにくい現状があり、実際に一部の先進的な企業を除いては進んでいるとはいえません。
ファーマ4.0を実現するためには、IT業界との連携が不可欠。そこで、製薬とITの知識を併せ持つ「トランスレーター」人材を育成していかなければならないと考えています。
トランスレーターが橋渡しとなってお互いの業界に関する知識を共有できれば、製薬のデジタル化が進み、より迅速に、より多くの患者さんへ薬が提供できる仕組みが整えられるようになるのではないかと思います。
開田 自動車業界や半導体業界のような効率化と自動化の取り組みが参考になりそうですね。製薬プロセスでのロボットや自動化技術の導入によって、少ない人材で効率的にバイオ医薬品を製造できる体制が整えば、日本においても持続的な産業基盤を築くことが可能になると思います。
人口減少や人材不足が進む中、製薬業界が生き残っていくためには、他業界の知見から学ぶべき点が多くあります。
――バイオ医薬品市場における異業種連携と今後の展望についてメッセージをお願いします。

内田 今後の医薬品市場は変化がますます速くなり、それに対応するためには、IT業界だけでなくさまざまな異業種との連携が不可欠です。例えば米国のボストンには、製薬企業やバイオテクノロジー企業、大学、研究機関などが集まり、バイオ医薬品や先端医療の研究開発を活発に行うエコシステムが形成されています。
ボストンのようなクラスター(産業集積地)を日本国内でも形成し、多様なノウハウを持つ人材が集まることで、医薬品の国内製造と供給の体制を強化していく必要があります。国民の安全を守るためにも、製薬業界全体が一丸となって取り組むことが重要です。
開田 サーモフィッシャーとしても、医薬品市場の課題解決に向けて異業種との連携を強化し、ワンチームとなって取り組みを推進しています。日本発の治療法が世界で通用するよう、技術やノウハウを広く共有し、日本のバイオ医薬品業界の発展に寄与していきたいです。