逆境に立ち向かう「攻め」と「守り」の企業変革 TRANSFORM SUMMIT 2023

協賛:Sansan、マネーフォワード、セールスフォース・ジャパン、ログラス、ヤプリ
ごあいさつ

代表取締役社長
田北 浩章
1895年の創業以来、紙の出版事業を続けてきた東洋経済新報社は、近年の環境の変化を受け、データ事業とオンライン事業を新たに展開してきた。フォーラムの冒頭、代表取締役社長の田北浩章は「逆境の中で事業生産性を向上させることは経営者の醍醐味かもしれない。人・組織を変革することで時代の大きな波を乗り越えられると信じています」とあいさつした。
特別講演
事業成長、イノベーション推進の為にリーダーが考えるべきこと

経営管理研究科
早稲田大学ビジネススクール
教授
入山 章栄氏
経営環境が激しく変化する中で、企業が成長するにはイノベーションが欠かせない。「リーダーシップには大きく3つのタイプがあるが、イノベーションを創出するためには、トランスフォーメーショナル型が重要になる」と、早稲田大学ビジネススクールの入山章栄教授は語る。
トランスフォーメーショナル型は、遠い未来に向けた方向性を示して部下を啓蒙し、内発的動機を引き出すタイプのリーダーシップ。イノベーションを創出するためには、遠いところにある社内には存在しない知を収集し、社内にある既存の知と掛け合わせ、新たな知と知を組み合わせる「知の探索」が必要だ。無駄や失敗にめげずに探索を続けるには「部下を腹落ちさせるストーリーを示す『センスメイキング』や、暗黙知を言葉に表現して伝える『言語化』ができるリーダーが必要」(入山氏)になる。
このほかに、従来の管理職というよりコーチとして部下の話を傾聴して良好な関係を築く「トランザクショナル型」や、チーム内で自由闊達な議論ができるようにファシリテートする「サーバント型」のリーダーシップスタイルを身に付けることも、組織の多様性の力を引き出し、イノベーションにつながる。「リーダーは最終的な意思決定をしなければならない。その力を磨くために『決める経験の場数』を踏むことも大事」と付け加えた。
協賛講演
営業組織の生産性向上に今必要なデータ活用とは

Sansan事業部
Product Marketingグループ
シニアプロダクト
マーケティングマネジャー
鳴海 佑紀氏
労働人口の減少、働き方改革による労働時間削減の中でも営業成果を上げていくには、営業の生産性向上が不可欠だ。Sansanの鳴海佑紀氏は「営業担当の業務時間の半分以上は、顧客提案の準備など間接的な顧客関連活動に費やされている。これを減らし、顧客と直接向き合う時間を増やすことが重要」と語る。
顧客提案準備に時間がかかるのは、社内の顧客情報がバラバラに管理されているため、提案先の状況を理解するために必要な情報を探すのに手間取ることが一因だ。この課題を解決するために同社は、部門を超えて顧客情報を共通のデータベースで一元管理する体制を構築。情報探しの手間を減らすことで、商談1件当たり40分以上かかっていた準備時間を約15分へと大幅に短縮できた。
この成果の背景にあったのが、同社が提供する「Sansan」だ。Sansanは今まで「クラウド名刺管理サービス」として訴求してきたが、顧客とのあらゆる接点情報を蓄積できる「営業を強くするデータベース」へと提供価値を拡張。
企業情報を標準搭載し、名刺情報のほか、顧客とのメール、商談内容、セミナーの参加申し込みなどのマーケティング情報も取り込めるようにした。顧客企業や、営業活動で会う個人の情報を最新に保ち、CRM(顧客情報管理)などと連携させることで分析精度を高めることもできる。「全社的に共有したデータを使って行動する環境が、営業生産性を高めるポイント」と語った。
特別講演
知見と、挑戦をつなぐ
~ビジネス情報収集のインフラの実現を目指して~

代表取締役 CEO
端羽 英子氏
ビザスクの端羽英子氏は、金融業界などを経て起業を検討していた当時、あるECビジネスのアイデアを思いついた。そこで、 知り合いのつてをたどって紹介されたEC事業の起業経験者に意見を求めたところ、1時間にわたってダメ出しをされ「もっと簡単に有識者に出会え、手軽に話が聞けるような場をつくりたい」と思った。 この時の経験から、端羽氏はさまざまな知見を持つ多くの有識者が登録するデータベースを構築。課題やニーズに対して最適な知見を持つアドバイザーをマッチングしてインタビューを時間単位で提供するサービス「ビザスクinterview」を立ち上げた。その後、中長期間プロジェクト等に最適な有識者が伴走支援するサービスなど、顧客からの要望に応えて知見データベースを活用したさまざまなサービスを展開している。
採用が前提の人材サービスと違い、「ピンポイントのニーズに対して必要な知見を持つ社外にいる人を、スポットで活用できる」のが特徴。2020年に東証マザーズ(現・ 東証グロース)上場後、米国の同業大手を買収し、 世界7拠点のグローバル体制を構築。登録有識者数も190カ国60万人超に達した。端羽氏は、「日本でも働き方改革やキャリア形成意識の高まりから、自身の知見を社会に生かしたいと考える人が増えている。言語や地域の壁を超えて世界中から最適な知見を入手できる体制を強化したい」と、目指す未来を語った。
協賛講演
経理部門で「攻めと守り」を実践するために必要なこととは

グループ執行役員
経理本部 本部長
松岡 俊氏
デジタル化、クラウド化による経理業務改革を2019年から進めてきたマネーフォワードの松岡俊氏は「経理部門は直接的に売り上げ・利益を生まないコストセンターとされているが、企業価値向上に貢献することも可能だ」と訴えた。
経理の経営に対する攻めの貢献の1つが情報提供のスピードアップだ。グループ内のシステム統一とプロセス標準化で部門間のデータ連携を効率化。部門別の管理会計PL作成・報告にかかる日数を10営業日から4営業日に短縮した。「経理情報は生鮮食品のようなもの。早ければ早いほど、経営判断に資する価値が高まる」(松岡氏)。2つ目はコスト削減だ。時代においては、グループ会社の経理業務の集約や、アウトソーシングの活用により、経理部門を筋肉質な組織にしてまずは自部門の費用削減を徹底。取引先別・部門・PJ別に費用のデータベース構築することによる見える化、適切な稟議ワークフローの構築、クラウド化・ペーパーレス化によるオフィススペースの削減、ポイント還元率が高いコーポレートカードの利用も有効だ。
経理業務効率化で浮いた時間は、開発チームにプロダクトフィードバック、マーケティングや営業活動に同伴するなど、付加価値活動に使う。松岡氏は「経理の仕事の枠を積極的に超え、企業価値向上に貢献することが重要」と語った。
特別講演
絶対悲観主義

特任教授
楠木 建氏
困難や失敗に直面してもやり抜く力「GRIT(グリット)」や、立ち直る力「レジリエンス」の概念が人気を博している。だが、誰もがそんなポジティブさを持ち合わせているわけではない。「僕は根性も闘争心も希薄」と言う一橋ビジネススクールの楠木建氏は、同様の気性の人々に向けて「絶対悲観主義」と名付けた仕事への心構えを提案する。
やり抜く力や回復力を求めるのは「うまくやらねばと思い込み、少しでも思いどおりにならないと大変な逆境に直面している気になるからだ」(楠木氏)。事前に成功を期待していなければ、グリットもレジリエンスも必要ない。そもそも仕事は、制御不能な顧客に対して価値を提供することなので、周囲の状況などに関係なく、思いどおりにはいかない。それを受け入れるのが「絶対悲観主義」だ。
自ら実践する楠木氏は、心のつまみを悲観方向に回すだけなので実装が容易。失敗を嫌がらなくなり、計画どおりに進まないリスクへの耐性がつく。過剰な準備で仕事への取りかかりが遅れることもなくなる──とメリットを説明。「実際の仕事は、心構えだけでなく、失敗しながら能力を磨くことも必要。『どうせうまくいかない』と思えば、うまくやろうとするのではなく、内発的な動因に従って、好きなことを思い切りできるようになる」と語った。
特別講演
企業成長を加速させる心理的安全性の本質

代表取締役
ピョートル・ フェリクス・グジバチ氏
テクノロジーの発展で、ホワイトカラーの仕事の基礎は、勤勉・服従・知識から、創造性・情熱・率先へとシフトしている。その中でチームマネジメントはどうあるべきか。グーグル日本法人で人材開発などに従事後、組織開発コンサルティングのプロノイア・グループを設立したピョートル・フェリクス・グジバチ氏は、情熱を持って仕事に取り組めるようにするポイントは「仕事に対する価値観は人や世代によって異なる。何のために仕事をして、何を得たいか、自己実現に必要な要素を認識してもらい、それを周囲に開示できる心理的安全性の高い環境を提供すること」と説明する。
グーグルが2012年に開始したリサーチ、プロジェクトアリストテレスでは、組織の生産性と相関性が高い項目は、個々のメンバーの能力などではなく、チームの心理的安全性だという結果が示された。心理的安全性が高く、失敗が許容されれば、実験的な取り組みをする意欲、コラボレーションが増す。ただし、やさしさだけでは成果の出ない「仲良しクラブ」に陥る懸念もある。そこでピョートル氏は、高い成果基準も同時に求めるべきだと強調する。「高い成果基準があれば、心理的安全性は残酷なほどの率直さを生むことになり、個人の希望と、組織のパフォーマンスの両立が可能になる。そこに心理的安全性の本質がある」と語った。
協賛講演
企業の意思決定の“質”と“速度”を向上させる、DXの最後の1ピースとは
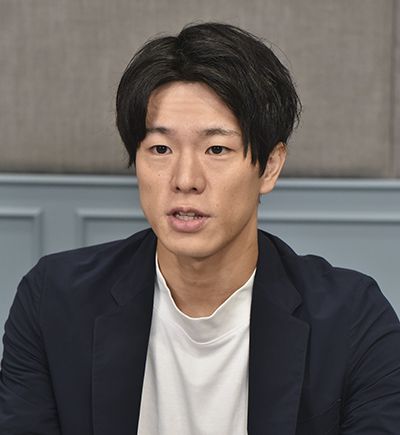
マーケティング部
Partner Alliance責任者
高野 光平氏
予想できない環境変化が続く時代に、期初に立てた計画を守って事業活動を続けることは難しい。予算の策定・管理、経営資料作成等の業務プロセスを改善するクラウドサービスを提供するログラスの高野光平氏は「環境変化に対して即座に対応するため、経営データを可視化してスピーディーで的確な意思決定を実現する守りのDXが必要」と語る。
日本企業の予算・計画の見直し頻度は、米国企業に比べて著しく低くなっている。その原因の1つに、経営情報インフラの整備不足が挙げられる。現状の予算見直し作業は、経営企画担当の属人的な手作業に依存し、作業負荷も大きいため頻繁に行えない。そこで、ITツールを使って経営情報収集を効率化し、削減できた作業時間を付加価値の高い業務に回す業務高度化が「DX成功のラストワンピースになる」(高野氏)。
データ管理を担ってきた基幹システム(ERP)に比べて、EPM(Enterprise Project Management)のログラスは、データを見やすく加工してアウトプットする機能や、特定の店舗・部門に絞ってドリルダウンして詳細データを閲覧できる機能などに優れている。「詳細データを知りたいときに、わざわざ問い合わせる必要がなくなり、経営と現場の間の“データの断絶”を乗り越えるツールになる」とアピールした。
特別講演
絶滅危惧種のチェーン店を再建!ドムドムバーガーの「思いやり」経営

代表取締役社長
藤﨑 忍氏
日本最古のバーガーチェーン、ドムドムハンバーガーは1990年代に約400店を展開していたが、親会社のスーパーが衰退して店舗数が急減し、「絶滅危惧種」とも呼ばれた。その立て直しに挑んだ異色の経歴の経営者、藤﨑忍氏が「社内風土改革と独自性模索」の取り組みを語った。
藤﨑氏は、短大卒業後に結婚して以来、専業主婦だった。しかし、夫が体調を崩したため、39歳でブティックに初めて就職。その後、居酒屋を経営していた時にドムドムの経営を引き継いだ事業再生事業会社の子会社に誘われて入社し、9カ月後に社長に就いた。
「元居酒屋のおばさんの社長がいきなり信頼を得るのは難しい」と、自ら店頭に立ち、手紙やSNSでスタッフとコミュニケーションを重ね、本部と店舗の間の信頼関係を醸成。イベントやアパレルブランドなど異業種とのコラボを推進し、新たな顧客層開拓に取り組んだ。
さらに「顧客・スタッフに寄り添うブランド」「期待の上を行く商品開発」を掲げて、大手寡占の業界の中で独自性を模索。店舗で手間をかけて解凍・調理する「丸ごとカニバーガー」など、業界のオペレーションの常識にとらわれないチャレンジで黒字転換を達成した。「今後もスタッフやお客様の幸せを追求する思いやり経営に愚直に取り組みたい」と語る。
協賛講演
社内の雰囲気が変わる組織エンゲージメントとは

取締役執行役員
ピープル&カルチャー本部長
山本 崇博氏
リモートワークの普及や人的資本の重視から、企業と従業員の間の信頼関係「組織エンゲージメント」が注目されている。従業員が前向きに仕事に取り組めるようになり、生産性に影響するからだ。モバイルアプリをノーコード(プログラミング不要)で開発できるプラットフォームを提供するヤプリの山本崇博氏は「アプリはECなど消費者向けのイメージが強いが、組織エンゲージメント強化のために社員向けアプリを利用するケースが増えている」と語る。
組織エンゲージメントの強化には、①帰属意識を高める理念・ビジョンの浸透、②専門的な商品知識の学習ツールなどを使った成長機会の提供、③社内コミュニケーション促進によるカルチャー醸成、④業務効率化──がポイントになる。アプリは、紙の社内報やマニュアルに比べて使い勝手がよく、必要なときに欲しい情報を簡単に見ることができる。多数のコンテンツを整理する情報ハブになり、社員に質問の答えをアウトプットしてもらい定着を確認するなど、一方的な情報発信にしない工夫もできる。
ヤプリは、アプリ利用状況を会社側が把握できるダッシュボードや、組織エンゲージメント強化に向けた「ヤプリユナイト」サービスなども提供。「アプリ開発のハードルを下げ、便利なテクノロジーを気軽に使える世界にしたい」と語った。







