過度な「食の自然信仰」を生む心のカラクリとは 「人工は悪」と決めつける認識はなぜ生まれる?

では、なぜ過度な「食の自然信仰」が生まれるのだろうか。疑似科学にまつわる科学リテラシーを研究している明治大学の石川幹人教授と、鳥取で農業法人「トゥリーアンドノーフ」を経営し、農業において科学的視点の重要性を発信している徳本修一氏が語り合った。
「自然=幸福」という危うい人間の直感
――鳥取で農業法人を経営している徳本さんは、「食の安全に関する事実に基づかない情報が、農業の持続的な発展を阻んでしまう」と危惧して発信に取り組んでいます。そう考えるようになったきっかけは何でしょうか。
徳本 修一(以下、徳本) メディアやSNSで農業や農薬に関するいろんな情報が飛び交っているのですが、生産者からすると事実と乖離している内容が多いんです。
とくに問題だと感じたのは、インフルエンサーが根拠なく「あの成分は危ない」と偏った情報を拡散していること。であれば、生産者自らが農業経営の実態に即したファクトを発信することが必要だと考え、活動してきました。

徳本 修一 氏
東京都内でのIT関連会社役員を経て鳥取に帰郷し、農業に参入。2012年に農業法人トゥリーアンドノーフを立ち上げ、現在は約80ヘクタールの農地で米や飼料作物を生産している。科学的視点やデータを重視し、新しい栽培技術・テクノロジーを積極的に取り入れながら生産性向上をつねに追求している。「ファクトに基づく」をポリシーとして、ブログやSNSなどで積極的に発信を行っている
その中で、ある除草剤の使い方について発信したんですね。すると、批判的なコメントが殺到しました。私たちは、科学的な情報に基づいて安全で適切な使用・管理を行っており、農薬の知識も身に付けています。
なのに、一部の情報を鵜呑みにして「二度とお前の米を市場に出すな」といった批判をする人がいるんですね。同じように風評被害を受けている同業者も非常に多くいます。
仮に、そのような批判に忖度(そんたく)して栽培方法を変えてしまえば、安定的に作物を作ることが難しくなるおそれもあります。農業の持続可能性を高めるためには、生産者自身が発信し、消費者と積極的にコミュニケーションを取るべきだと考えました。
――昨今はさまざまな「危険説」があり、いわゆる陰謀論なども出回っています。なぜこうした非科学的な言説が受け入れられてしまうのでしょうか。
石川 幹人(以下、石川) まずは、「科学」とは何かについて考えてみましょう。科学の原理とは、日常体験で同じようなパターンを経験した際に、それに基づき法則を作っていくというプロセス自体です。例えば、「赤いお花が咲いたら、果実が取れる」といったように。

石川 幹人 氏
東京工業大学理学部応用物理学科(生物物理学)卒。同大学院物理情報工学専攻、新世代コンピュータ技術開発機構研究所などを経て、1997年に明治大学文学部助教授。2004年より現職。専門は認知情報論および科学基礎論。14年に共同研究者とともに「疑似科学とされるものの科学性評定サイト Gijika.com」を開設。著書に『なぜ疑似科学が社会を動かすのか』(PHP新書)、『だからフェイクにだまされる』(ちくま新書)など
しかし世間では、学校で学ぶような「理論」を科学だと認識しています。でも、科学は本来、「プロセス」なんです。理論は成果の一部であり、重要なのはその裏側で行われている観察や実験、データに基づく検討です。
環境や状況などの前提が変われば通用しない理論はたくさんあります。例えば、ある成分が安全か否かは、その成分が投与される量や対象によって大きく異なります。
今の世間では、前提やプロセスをスルーして「インターネットやSNSでたくさんの人が言っているから正しい」と、疑似科学を信じ込んでしまいがちです。
ただし、ある程度仕方がないという側面もあるのです。実は私たちには、見知らぬ他人の意見を、周りの親しい人の意見と同じように信頼して受け取ってしまうという傾向があります。進化心理学の観点では、狩猟採集をしていた先史時代に、周りの仲間と協力するように私たちが進化をしてきた結果だと考えられています。
――農薬や遺伝子組み換え作物など「人工的なもの」を忌み嫌う言説もよくあります。
石川 太古の昔、自然の中で生きてきた人類は、知恵を使わなければ決して繁栄することができませんでした。なぜなら、自然にある獲物や食物は数が限られており、人口が増えれば賄うことはできない。
そこで、科学技術で乗り越えようとして文明を発展させた結果、食べ物を増やすことができ、人類の繁栄につながりました。文明によって人類が生き延びてきたという認識がないと、「人工的なものは悪」と捉えてしまうでしょう。

日本には、公害の時代がありました。川が赤や青に染まるくらい工業排水が垂れ流され、社会問題となりました。それを目の当たりにすると、工業は悪いものだと思うのもやむをえません。ですがその後、工業排水の規制が行われ、水質は戻ってきました。
重要なのは、水質を取り戻すのも科学技術であるということ。「工業を維持しつつ、工業排水を問題なく処理する」という技術開発によって実現されているわけです。
このように、科学が果たしてきた役割を認識する必要があります。ましてや、人間は「直感的に」自然を好むので、直感に頼っていては歪んだ方向に向かうおそれがあります。
――直感的に自然を好むとはどういうことでしょうか。
石川 大自然の中で狩猟や採集をして生きてきた時代がとても長かった人類にとって、より獲物や食べ物が多く、水も豊かな里山を直感的に好むのは当然です。「自然=幸福」と捉えるのはそうした感性が残されているからです。
徳本 実は私も、農業に参入する前はそうでした。東京で暮らしていたので、メディアで目にするロハスなライフスタイルのイメージにも引っ張られ、「これからはオーガニック農業だ」と飛び込んだんです。
化学肥料の発明が、人類を食料危機から救った
――今は慣行農業※1をされていると聞きましたが、オーガニック農業から撤退したのはなぜでしょうか。
徳本 当時は露地栽培※2で大規模に展開して、高級スーパーと提携してうまくいった時期もありました。しかし、安定的に生産ができなかった。殺菌剤が使えないために大雨が続くと病気で全滅することもあります。
すると販売先の信頼も失いますし、従業員も疲弊していきます。不確実な天候で結果が大きく左右されるギャンブルをしていたようなものでした。
「どうにかしないと」と思い、オーガニック生産者の方々と意見交換をしつつ、土壌や農薬について一から学んで、とくに科学的視点を持つようになってからはオーガニック農業にこだわる必要がないことに気づきました。あくまでもオーガニックは手段の1つ。
安定生産や持続的な農業のためには、気候や土地に適したやり方を選ぶことが重要です。例えば、乾燥しているカリフォルニアと、高温多湿で台風などの自然災害が多い日本では適する農法が違ってきます。
※2 露地栽培:温室や温床などの設備を使わず露天の耕地で栽培を行うこと

石川 オーガニック農業だけに頼っていたら、地球上の食料供給はすでに破綻しているでしょう。国連の推計によれば、2022年の人口は約80億人ですが、この100年で約4倍に増えているんですね。急激な人口増加に食料供給がなぜ追いつけたか。それは、化学肥料の技術が生まれ、少々荒れ地でも作物が作れるようになったからです。つまり、私たち人類の食は、すでに科学技術に支えられているわけです。
「自然とのふれあい」の農業体験から脱却すべき
――トゥリーアンドノーフではどのような農業が展開されているのでしょうか。
徳本 私たちはトラクターにGPSを付け、アプリで農作地を管理し、遠隔でも確認ができるようにしています。農業は、「額に汗して手塩にかけることが美徳」だという風潮がありますが、想像以上にこなすべきことが多く、効率よくやらないと安定的に売り上げを計上できません。
以前、都会の人は「家庭菜園」の延長線上に「農業」を置いているのでは、という指摘を目にしたことがあります。家庭菜園の「癒やし」のイメージが農業に持ち込まれている、と。しかし、趣味としての家庭菜園と、生業としての農業は別物だと捉える必要があると思います。
石川 農業に対する見方を根本から変えていく取り組みが必要でしょう。学校での芋掘りや田植えなどの農業体験は情操的で、「自然とのふれあい」といった受け止め方にとどまりがちです。それでは、いつまで経っても科学技術を自然に相反するものと考えてしまう。
それよりも、「なぜ安全かつ安価に作物が供給され、食が守られているのか」という観点から農業テクノロジーの歴史や、社会の仕組みを知ることが重要です。
徳本 アジア各国では人や環境に配慮しながら、品質や収量を安定的に確保できるバイオテクノロジー農業が広がってきています。先日、フィリピンで行われたバイオテクノロジーの最新知見を共有する国際的なプラットフォーム「Pan-Asia Farmers Exchange Program」に参加してきました。
そのプログラムの中で、飢餓対策や環境保全対策がいかに重要であるか、テクノロジーがそれをどう解決しうるかについて、小学生のうちからプログラムを組んで教えている取り組みも紹介されていました。日本でも、そうした教育が必要だと強く思いました。
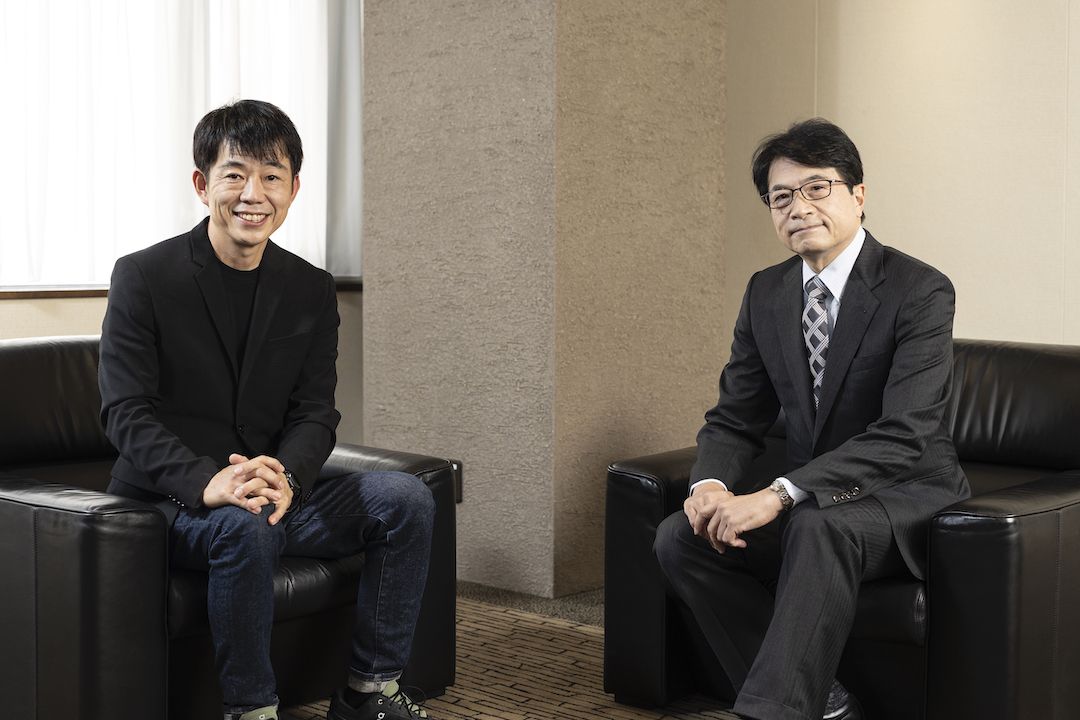
――海外にも目を向けているのですね。
徳本 実は、世界で農場を展開することを構想しています。バイオテクノロジーを含め、さまざまなテクノロジーを取り入れ、規模の大きさや雇用創出など社会への貢献によって話題性を狙いたい。そうしたケーススタディーを作ることで、新しいテクノロジーの有用性が社会で理解されていくと考えています。
石川 実行力に敬服しますね。現場の取り組みや、生み出した実績こそが世の中を変えていけると思います。徳本さんのようなオピニオンリーダーや行動力のある人を育成することが、食を守り、正しい情報が定着するために重要になってくるでしょう。




