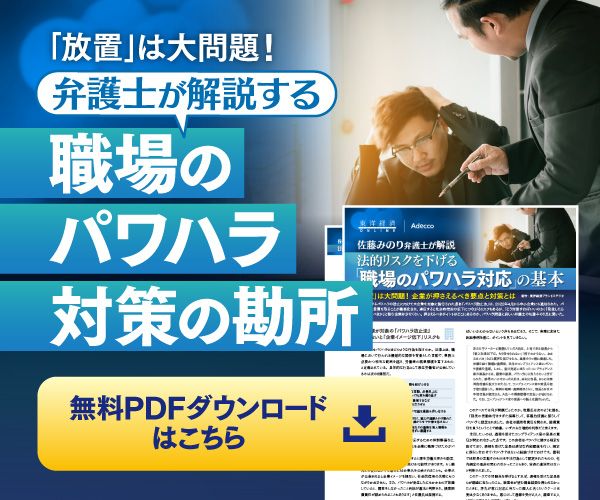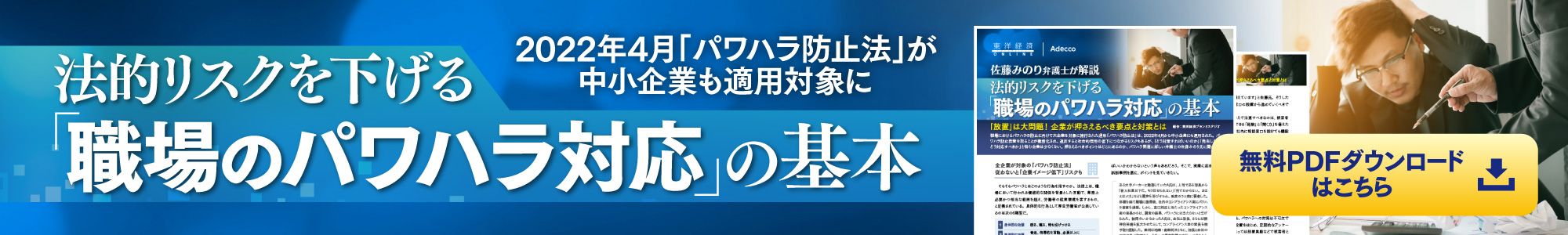弁護士が解説「職場のパワハラ」で起きうるリスク 22年4月「パワハラ防止法」が全企業で適用に

行政の勧告に従わなければ「企業名の公表」の可能性も
企業経営における「人」の価値が再認識され、働きやすい職場づくりに注力する企業が増えている。一方で、その流れに逆行するかのように、パワハラのニュースが後を絶たない。訴訟には至らないまでも、個人で記録した音声や動画がネットで拡散し、世間からの批判にさらされ炎上するケースは枚挙にいとまがない。

佐藤みのり 弁護士
神奈川県横浜市出身。2012年3月、慶應義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。13年、弁護士登録。複数の法律事務所で勤務したのち、15年5月に佐藤みのり法律事務所を開設。主に子どもの権利や学校トラブル、ハラスメント問題などを取り扱う
パワハラ防止に向けて雇用管理上必要な措置を講じることは今や企業の義務だ。2022年4月、パワハラ防止法の適用対象が中小企業にも拡大された。パワハラ問題に詳しい弁護士の佐藤みのり氏は、「この法律に罰則規定はないものの、パワハラ防止措置を講じていないと、厚生労働省から助言や指導、勧告を受ける場合があります。行政の勧告に従わなかったときは、企業名が公表される可能性もあります」と指摘する。
企業が取るべきパワハラ防止措置とは何か。厚労省によると、「パワハラ防止に向けた方針等の明確化および周知・啓発」「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「パワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応」「そのほか併せて講ずべき措置(パワハラの相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること、相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること)」などが必要とされている。
「企業のパワハラ対策は安全配慮義務の一環と見なされており、対策が不十分だと法的なリスクが上昇することになります。万が一訴訟になった場合にも、適切な措置を講じていたかどうかで、会社が負う法的責任は大きく変わってきます」と佐藤氏は警鐘を鳴らす。
先行してパワハラ防止法が適用されていた大企業では、すでに先述のような防止措置が取られていることが多く、中には独自の取り組みでパワハラの抑止を図っている企業もある。ただ、「社内に相談窓口を設けているものの、利用すべき対象者が利用をためらってしまう」といった声も聞かれるなど、必ずしも「適切」な措置が取れているとは限らない。また、今年4月に適用対象となった中小企業においては、まだ十分な措置を取れていないことも少なくないのが現状だ。
職場のパワハラに対する世間の注目度は高く、問題が生じたときに適切な方法とタイミングで対応できなければ、あっという間に社会的信用が低下し、事業や採用活動にも影響しかねない。改めて、自社のパワハラ防止措置を見直し、新たな対策を検討してみるのはどうだろうか。
ここからダウンロードできるPDF資料では、佐藤氏の解説の下、実際の裁判例に基づく企業のパワハラ対応の問題点や、パワハラ事案が発生したときに適切に対応するためのポイント、法的リスクを下げるパワハラ防止の取り組みなどについて紹介。パワハラを発生させず、あるいは問題が起きたとしても適切に対応できる体制を構築し、社員が働きやすい職場を実現するために、ぜひ参考にしてみてほしい。