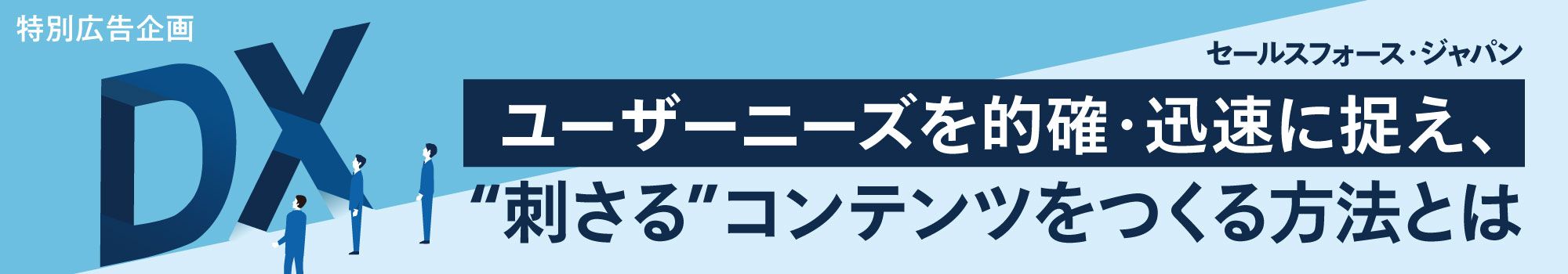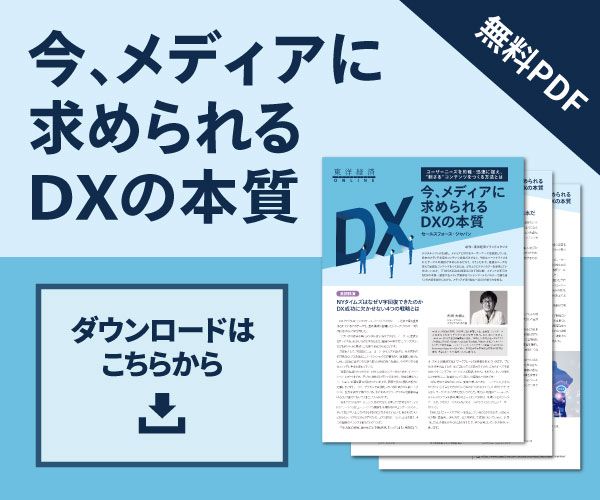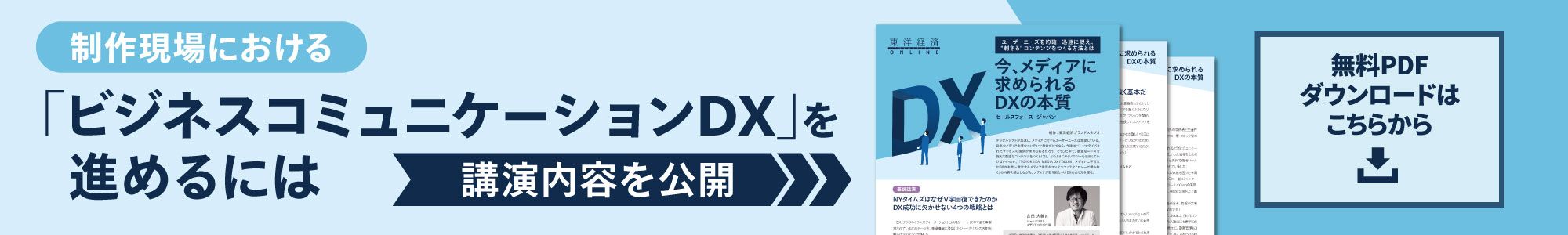ユーザーの「サブスク疲れ」、メディアの突破口は これからのメディアに不可欠なDX戦略を学ぶ

「よいコンテンツ」だけではもはや通用しない
デジタルシフトが加速し、メディアに対するユーザーのニーズは激変している。従来のメディア主導のコンテンツ発信だけではなく、今後はパーソナライズされたサービスの提供が求められる。2022年1月にオンライン開催された「TOYOKEIZAI MEDIA DX FORUM メディアに不可欠なDXの本質 激変するメディア業界をコンテンツ×テクノロジーで勝ち抜く」では、メディアが取り組むべきDXのあり方について講演が行われた。
基調講演で登壇したのは、ジャーナリストでメディアコラボ代表の古田大輔氏。新聞記者からウェブメディアの創刊編集長とキャリアを重ね、メディア戦略の変遷を身をもって体験する中で、「コンテンツがどういう経路をたどってどういう人に届くのか」「課金メディアであれば課金・継続といったジャーニーをどのように構築するのか」を徹底的に考えるようになったという。古田氏が、自身の経験から導き出したメディアのDXに必要な要素とは。
メディア業界のDXを支援しているセールスフォースも登壇。セッションの1つでは、「デジタル・サブスクモデルの拡大に向けて」と題し、メディアにおけるサブスクモデルの拡大に不可欠な視点について語られた。ユーザーの「サブスク疲れ」も指摘される中、メディアはどうすればユーザーの満足度を高めることができるのか。より消費者を理解した「ユーザー起点」のサービスの提供がカギとなる。
他のセッションでは、メディアの現場でコンテンツの制作担当者が抱える課題についても言及された。質の高いコンテンツを多く供給することが求められる中で、社内外の多様な人材とコラボレーションするなど業務の複雑性が増している。コンテンツ制作現場において急務である「ビジネスコミュニケーションDX」はどう進めればいいのだろうか。
そのほかにも講演では、激変する読者・視聴者のニーズを迅速かつ的確に捉える方法や、“刺さる”コンテンツの作成方法などが紹介されている。詳細はこちらから無料ダウンロードできる講演レポートにまとまっているので、ぜひ確認してほしい。