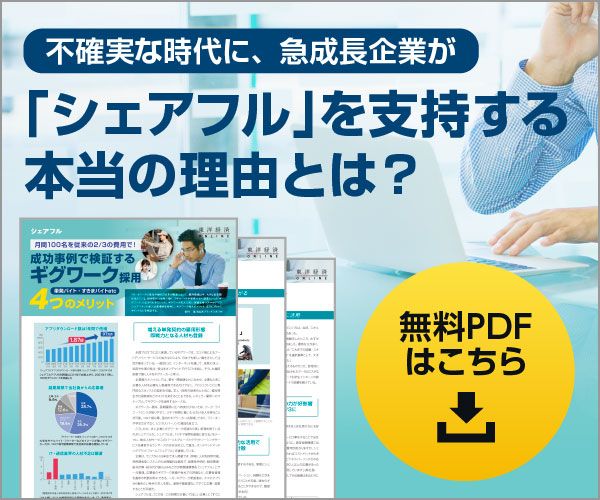不確実な時代に「ギグワーク」を活用する意味 急成長企業がシェアフルを支持する本当の理由

雇用環境の変化や副業解禁で注目高まる
街中を自転車で駆け抜ける姿を頻繁に見かけるようになった、フードデリバリースタッフ。彼らに代表されるギグワーカーとは、インターネットを通じて単発・短時間の仕事を請負、報酬を受け取る人々のことを指す。
もともとは米国でミュージシャンが仲間と即興演奏を行うことを「ギグ」と呼び、そこから単発の仕事を「ギグワーク」と称するようになったといわれている。米国では2000年代初頭から、宅配やフードデリバリーなどの配送サービス、配車サービスのドライバー、プログラム開発のエンジニアでギグワーカーが増加。現在ではさまざまな職種に広がり、働き方の選択肢において大きな位置を占めるようになっている。
日本国内ではコロナ禍をきっかけに、雇用環境が大きく変化。業務量のばらつきやリモートワークに対応するため、ギグワークを導入する企業が拡大する一方で、副業解禁や失業、スキマ時間を活用したい人々によって、ギグワーカーも急増している。
ギグワーク導入の成功には、使い勝手のよいプラットフォームが不可欠
しかし、発展途上にある日本のギグワーク市場においては、人材のスキルや採用、労務管理などでまだまだ課題が多い。ギグワークの導入を検討したが頓挫したり、導入はしたものの継続的な活用に至らなかったりするケースも見られる。
こうしたギグワーク市場で高い評価を獲得しているのが、総合人材サービスのパーソルグループに名を連ねる『シェアフル』だ。企業はウェブから1日単位で求人掲載でき、ニーズに応じた人材を採用可能。掲載料は無料で、労務関連業務もオンライン上で一元管理できる。