個人と組織の変革を促す「重ねる」という思想 新しいマネジメントスキルで組織を変えていく

欧米型ワーケーションと日本型ワーケーション
ワーケーションの源流は2000年代半ばごろに始まった、欧米のデジタルノマドたちのワークスタイル、ライフスタイルに求めることができる。フリーランスが増え、スマートフォンやモバイルPCの浸透とモバイル環境が整備される中で、民泊などのシェアリングエコノミーや格安航空会社が台頭し、世界的に観光が盛り上がったことなどを背景に新しいワークスタイルが加速した。
日本にワーケーションが輸入されたのは2010年代後半あたり。個人主導で広がった欧米型ワーケーションとは異なり、日本型ワーケーションは地方創生、働き方改革という文脈で理解され、主なリード役は自治体や企業。一般的には、個人は従業員として制度を利用する側という形になっている。また、地域住民を含めて多様な人々が交流することによって、何らかの社会課題を解決したいというモチベーションがあることも、日本型ワーケーションの特徴の1つだ。
2020年以降は新型コロナウイルス感染症が転機となって、自治体、企業の取り組みのスピードと方向性は大きく変化した。もともとスポーツイベント開催に伴い、19年ごろから首都圏の官公庁や企業などで積極的にテレワークを推進していたが、コロナ禍によって想定以上のテレワーク、ハイブリッドワークが進展した。
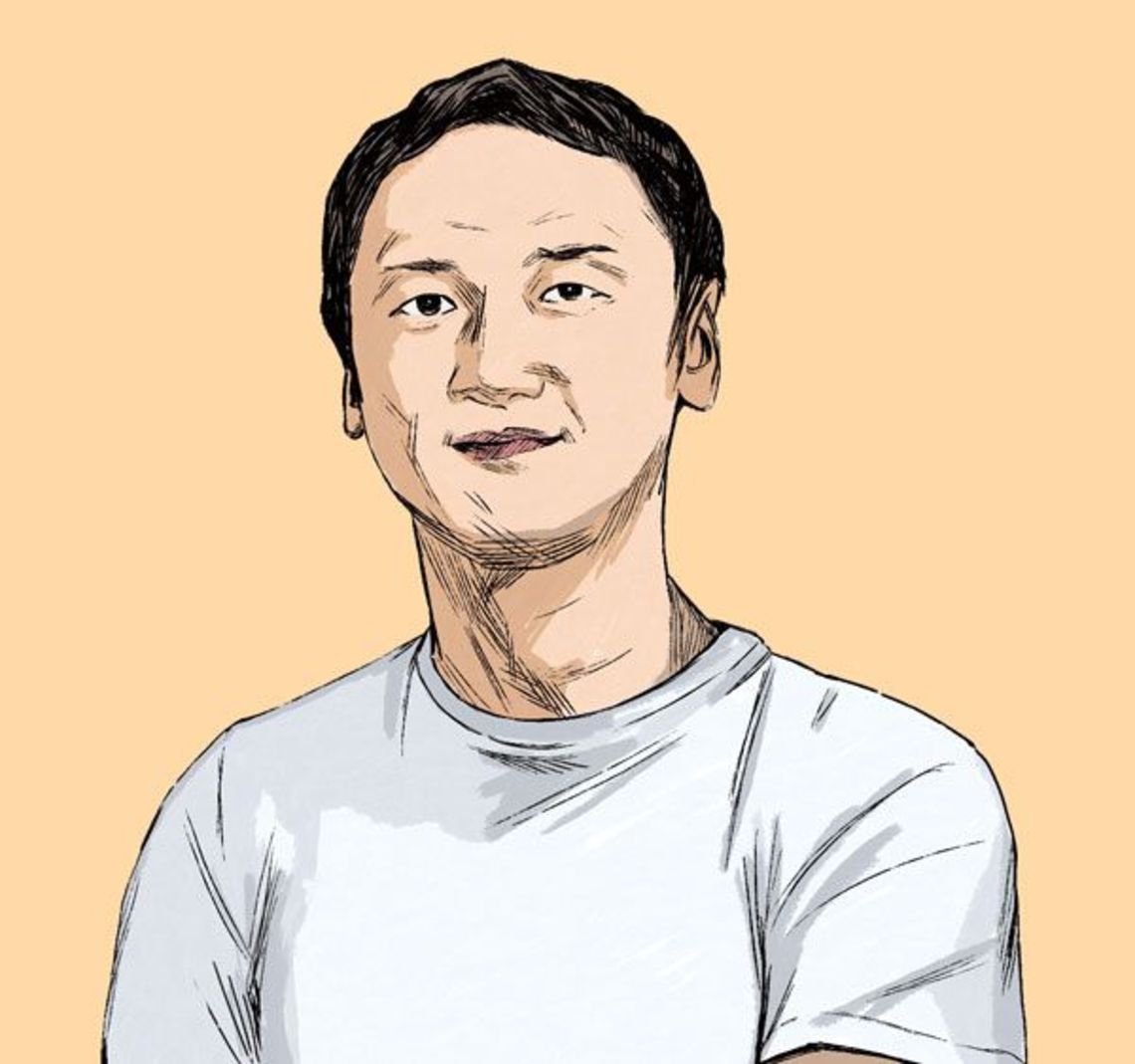
関西大学社会学部教授
博士(文学)。京都大学文学研究科、フィンランド・タンペレ大学ハイパーメディア研究所研究員、ベルリン工科大学訪問研究員、実践女子大学人間社会学部などを経て現職。主な著作として『ワークスタイル・アフターコロナ』『モバイルメディア時代の働き方』など
松下教授はこの状況を「強制社会実験」と評している。「課題はあるけれども、やってみたら案外できたという実感が、テレワークの社会的認知度を上げ、自治体、企業、ワーカーが新しい働き方に大きな関心を示すようになりました。ワーケーションにしても、はじめから『正しい』ワーケーションのあり方を求めるのではなく、むしろワーケーションを実施した結果、そこで生まれる人材交流やウェルビーイングな環境などによってもたらされる、予測不能な化学反応に期待したほうがうまくいくはず。そして、その結果、生産性が高まることも期待できる。それは予定調和がないイノベーションと同じです」と松下教授は語る。
「スーパーインポーズ、重ねる」というコンセプト
そもそもワーケーションとは何か。松下教授は「ワーカーが休暇中に仕事をする、あるいは仕事を休暇的環境で行うことで取得できる休み方であり、働き方。また、仕事に効果があると考えられる活動を伴うこともある」と定義。「目的ではなく手段だと意識することが重要」と強調する。
「ワーケーションが盛り上がる以前から、仕事の前後に休暇を『足す』、Bleisure(ブリージャー)はありました。例えば金曜日の出張後に現地で家族と合流して土日を過ごすというやり方です。ただ、ワーケーションは足すとか、オンとオフを切り替えるとかではなく、『スーパーインポーズ、重ねる』というイメージ。あれか、これかと選択を迫るのではなく、あれも、これも重ねて受け入れる、と言ったらよいでしょうか。これまでの考え方や常識では理解が難しく、だからこそ『これぞワーケーションの王道』を求めてしまうのかもしれません」
松下教授はワーケーションをわかりやすくするために「Vacation as Work/福利厚生型・地域課題解決型」と「Work in Vacation/合宿型・サテライトオフィス型」に分類している。前者は仕事を持ち込むことで休暇を取得できるもの、例えばメールをチェックしたり、オンライン会議をしたりしながら観光地に1週間滞在するといったタイプ。後者は休暇的環境で仕事をするというもので、涼しいところで1週間、集中的に個人やチームでサービス開発に取り組むといったタイプだ。要は休暇に仕事を重ねるか、仕事に休暇を重ねるかして、新たな付加価値を生み出そうということだ。
この付加価値こそが、ワーケーションの導入メリットだ。企業面から捉えると「健康、刺激、採用」の3つのメリットを挙げられるだろう。「健康」は従業員のウェルビーイングに深く関わり合う。生産性を下げるであろう心身にとって不快なもの、例えば花粉症や暑さなどを避けられる環境を用意することで、ウェルビーイングの向上が図れる。それは健康経営や健康資本の蓄積にもつながってくる。
「刺激」は、個人もしくはチームが非日常的環境に身を置くことで得られるもの。例えば、地域との交流によって得た気づきがイノベーションや新規ビジネスなどへ発展する可能性も期待できる。「採用」は、ワーケーションを含めたフレックスタイム・フレックスプレイスの働き方を認めている企業だという対外的評価の向上をもたらすだろう。
また、仕事とプライベートを上手に「重ねる」ワーケーションは、自ら主体的に課題を見つけて取り組んでいくという自律型人材育成のきっかけや呼び込む引力になるのではないだろうか。
マネジメント層こそワーケーション体験を
「重ねる」ことによって価値を創出していくために企業のマネジメント層に求められるのは「ハイブリッド・ワークスタイル時代のマネジメントスキル」。これは、制度導入のためのルール作り以上に重要な視点となる。
米国のIT企業でも、フルリモートワーカー、ハイブリッドワーカー、フルオフィスワーカーの割合を模索している。最適な割合は企業ごとに異なってくるだろうが、これからは恒久的なリモートワークやハイブリッドワークの社員も当たり前に存在することがスタンダードになっていくだろう。
「そのとき、マネジメント層は自社の戦略、あるいはサプライチェーンや取引先の状況も踏まえたうえで、最適な働き方、リモートワーカーとオフィスワーカーの割合、人材の配置・構成を決定していかなければなりません。そこから、転勤などの制度設計、オフィスのファシリティーマネジメントを考えていくこととなります。その中でワーケーションのような新しい働き方を容認したり、整えたりする発想も必要でしょう」
そのためにも、「マネジメント層が、自らワーケーションを体験してみることをお勧めします」と松下教授は言う。ワークスタイルとライフスタイルを重ねる経験と、そこから見えてくる価値観に基づいて仕事の環境を見直し、ワーカーにより賢い選択を促すことができるようなノウハウが重要になっていくだろう。ワーケーションを考えることが、新しい組織像、人材像を見直す1つのきっかけとなるはずだ。



