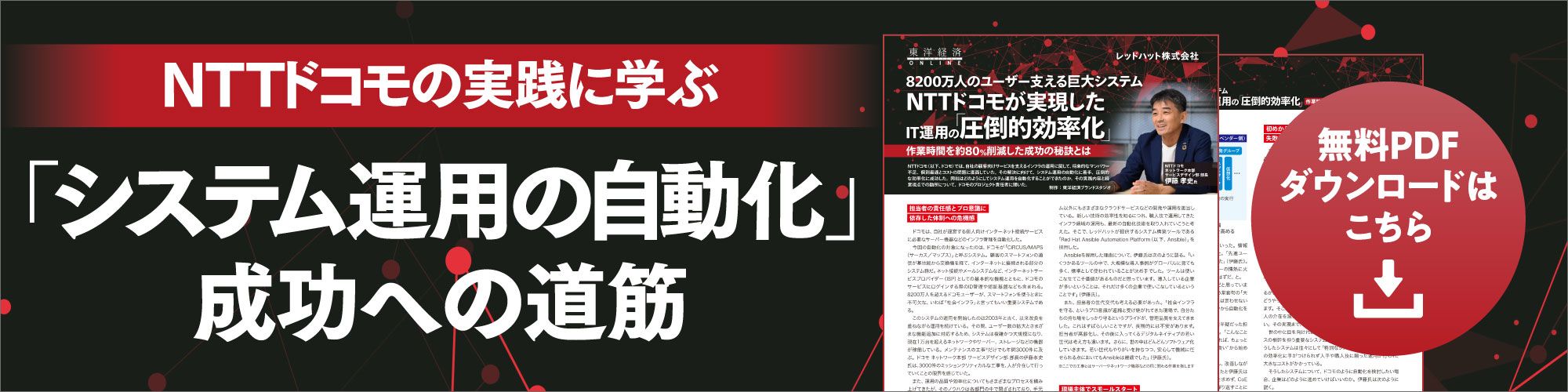ドコモが実現、ITシステム運用の「圧倒的効率化」 8200万人利用「特別なITインフラ」の自動化へ

「個別最適」「プロ頼み」から脱却へ、運用の自動化に着手
ドコモが「CiRCUS/MAPS(サーカス/マップス)」と呼ぶシステムは、同社のビジネスの根幹を担っている。ネット接続やメールシステムなど、インターネットサービスプロバイダー(ISP)としての基本的な役割と、ドコモのサービスにログインする際のID管理や認証基盤なども含まれる。8200万人を超えるドコモユーザーが、日々知らずに利用している社会インフラと言ってもよい重要なシステムだ。
このシステムの運用を開始したのは2003年。以降、改良を重ねながら運用を続けている。その間、ユーザー数の拡大とさまざまな機能追加に対応するため、組織とシステムはしだいに複雑かつ大規模になっていき、現在では1万台を超えるネットワークやサーバー、ストレージなどの機器が稼働している。その維持のために年間3000件に及ぶ工事を人が介在して行っていくことの限界を感じていた。
また、運用開始以来、品質と効率の向上にも取り組んできたが、そのノウハウは各部門の中で閉じており、個別最適な状態になっていた。失敗の許されない作業を、さまざまなグループが密に連携し実施する。
幸いにして、これまで、連携ミスが原因で運用上の問題が起きたことはない。だがそれは、運用担当者がプロフェッショナルとして、最後までやりきってきたからだと、ドコモ ネットワーク本部 サービスデザイン部 部長の伊藤孝史氏はみている。

サービスデザイン部 部長
伊藤孝史氏
「社会インフラを守る、というプロ意識が連綿と受け継がれてきた現場で、自分たちの持ち場をしっかり守るというプライドが、管理品質を支えてきました。これはすばらしいことですが、長期的には不安があります。担当者が高齢化し、その後に入ってくるデジタルネイティブの若い世代は考え方も違います。さらに、世の中はどんどんソフトウェア化していきます。この問題を解決するために、自動化は避けられない道でした」(伊藤氏)。こうした理由により、同社はシステム運用の自動化に着手する。
ドコモはどうやって、従来の運用管理から脱却し、社会インフラとして特別視されてきたシステムの運用自動化を成功させたのか。伊藤氏は「スモールスタート」「自動化の自走化」が大きなカギだったと語る。ここからダウンロードできる資料では、それぞれの詳細と自動化の成果を読むことができる。システム運用に課題を持つリーダーや、ITの経営効率を高めたいと考える企業幹部にとって必読の内容だ。