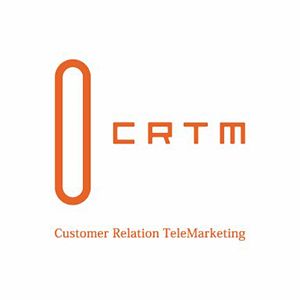「昔は良かった」を語る経営者の落とし穴 過去の成功談には求心力がないと気づけるか

「BPR」(業務効率化)から始まるビジネス改革
――BPRが注目を集めている理由を教えてください。
田中 BPRという言葉自体は20年ほど前に登場し、生産現場における業務を「改善」するという意味で使われてきました。しかし現在は意味合いが変わってきていて、業務プロセス自体を1から「再設計」する動きが中心です。そもそもBPRの目的を一言で言えば、無駄な仕事を極限まで減らし生産効率を上げること。
それに向けて仕事のやり方をどう変えるのか、ひいてはビジネス全体をどう組み換え、設計し直していくのか。こうした考え方に重点が置かれるようになってきました。近年は特に、いわゆる働き方改革というトレンドが加わったことで、BPRが経営課題として認識されるようになりましたね。

田中 壽一
東京大学大学院工学系研究科航空学専攻修了。「制御できる経営」を実現するための業務プロセス改善、情報マネジメントシステム、内部管理体制等の整備支援、コンサルティングを展開している。専門分野は情報システム、内部管理体制、グループ経営、リスクマネジメント、業務プロセス改革など。『次世代インターネットがわかる本』(オーム社、2001年)などの著書がある
――BPRの中でも、特にBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)はどう役立つのでしょう。
田中 BPOは、BPRをわかりやすく実現する手法として間違いなく有効です。ただしBPOを実行するにはまず、自社のビジネスを正確に定義し、またプロセスを正確に把握する必要があります。業務を細部まできちんと整理できていないと、そもそも外注できる部分とそうでない部分を線引きすることはできません。
逆にそこをしっかりとできてさえいれば、効率的なBPOが可能になります。アウトソーシングすることでより多くの人的リソースをコア業務に充てられますから、単純に工数を減らしコストを抑える以上の、多くのメリットが期待できるでしょう。
――海外と比べると、日本の状況はどうですか。
田中 日本はかなり遅れています。理由としては2つあり、まずは労働環境の違い。欧米の労働市場では一般に「ジョブ・ディスクリプション」(職務記述書)が用いられ、各人の業務内容が明確に規定されています。
一方、日本では「仕事が人にひもづいている」状態が多い。新卒一括採用を経て部署配属、その後は定期的な部署異動があり年功序列で昇進……という文化は、特に大企業で未だに根強く残っています。部署ごとの役割分担はあっても、各社員の役割分担はそれほど明確に定められないため、BPOとの親和性が低いという事情があるのです。
逆に、BPRを行うに際して各人の仕事内容を明らかにすれば、属人的な仕事の進め方を変えることにもつながります。ビジネスプロセスを整理して、業務を”標準化”することが必要になっているのです。
もう1点は、現場によくある「現状維持バイアス」です。アウトソーシングすることで、自社の情報やノウハウが外部に流出してしまうのではないかと懸念を抱く企業が少なからずあり、業務フローにテコ入れをすることにどうしても抵抗が生まれてしまうのです。まずはBPRによってどんなメリットが得られるのか具体的に明らかにし、組織全体に意識を浸透させることが必要です。
――BPRの障壁は、やはり人に行きつくということでしょうか。
田中 はい。BPRへの認識が誤っていて「誰かがリストラされるのではないか」と不安を抱く労働者もいます。しかし、単に人員削減して組織をスリム化するのは、決してBPRの本質ではありません。そもそも日本企業は今、業種・業態によらず深刻な人手不足に苦しんでいる状態です。だからこそ、少ない人的リソースを有効活用するために、BPRは避けて通れない道なのです。
たとえばホワイトカラーの仕事については、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)によって効率化・自動化が進められるようになってきていますが、こちらも実際に効果を出していくためには、導入する人のモチベーションが何より重要です。
RPAというツールを使って、いかに多くの時間と手間をコア業務に割き、自分の仕事を楽しくできるか。そうした視点が必要になっているのです。
「良い無駄」と「悪い無駄」があることを認識すべき
――ただ、無駄の中にこそ、ノウハウが詰まっている、無駄をなくしてしまえば、むしろその企業独自の良さが消えてしまうと指摘する向きもあります。
田中 無駄をなくす、という一辺倒ではいけません。無駄には「良い無駄」と「悪い無駄」があるということに注意する必要がある。中には、イノベーションを起こすためにあえて無駄な時間をつくり、社員の自由な発想を仕事に生かそうと取り組んでいる企業もあります。まさにこれは「良い無駄」で、業務効率化を経てわざわざ生み出されたものです。
逆に「悪い無駄」とは、たとえば会議のためにと不要な資料をつくって自己満足を得ているような時間のことを指します。どちらかというとベンチャー企業よりも大企業で、こうした「悪い無駄」が今なおはびこっているように見えます。
――BPRを進めるため、経営層に求められるものとは何でしょうか。
田中 まずは、BPRの重要性をしっかりと認識してほしい。デジタル化、グローバル化の波が押し寄せる中、BPRは業種・業態によらず、どんな企業にとっても避けて通れないものだと考えてください。今取り組まなければ、将来生産性が落ち、企業全体が切羽詰まった状況に陥ってしまうでしょう。そして企業のトップとして具体的なビジョンを打ち出し、BPRにコミットメントしていくのだという強いメッセージを発信するべき。
そのためにも、過去の成功談ばかりではなくぜひ「失敗談」を語ってほしい。「昔は良かった」ではなく「昔は失敗したが、今ならもっと良くできる」という前向きな姿勢が求心力を高め、現場を動かします。
人手不足の中で企業間の競争は激化しており、一方で消費者の嗜好もめまぐるしいスピードで移り変わる時代です。中国の台頭もあり、古き良きビジネスのやり方ではもはや通用しなくなっているのです。今はBPRにもさまざまなツールが開発されており、導入コストも昔に比べてずっと低く抑えられています。
経営者がこうしたツールをうまく使いこなすことは、生き残っていく企業の第一条件。新たな付加価値を生み出して数十年、数百年と発展し続ける企業になるためにも、まずは業務の見直しから始めましょう。